一条真也です。
『妖怪学新考』小松和彦著(講談社学術文庫)を読みました。「妖怪からみる日本人の心」というサブタイトルがついています。本書は、1994年に小学館から単行本として刊行された本を文庫化されたものです。著者は1947年東京都生まれ。東京都立大学大学院社会人類学博士課程修了。信州大学助教授、大阪大学教授を経て、現在は国際日本文化センター名誉教授(元所長)です。わたしは、異色の民俗学者である著者の本はほとんど全部を読んでいますが、ブログ『神隠しと日本人』、ブログ『呪いと日本人』、ブログ『異界と日本人』で紹介した本に続いて、本書を再読しました。
カバー裏表紙には、以下の内容紹介があります。
「妖怪とはなにか? 科学的思考を生活の基盤とし、暗闇すら消えた世界においてなお、私たちはなぜ異界を想像せずにはいられないのか――?古代から現代にいたるまで妖怪という存在を生みだし続ける日本人の精神構造を探り、『向こう側』に託された人間の『闇』の領域を問いなおす。妖怪研究の第一人者による刺激的かつ最高の妖怪学入門書」
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「はじめに――新しい妖怪学のために」
第一部 妖怪と日本人
一 妖怪とは何か
二 妖怪のいるランドスケープ
三 遠野盆地宇宙の妖怪たち
四 妖怪と都市のコスモロジー
五 変貌する都市のコスモロジー
六 妖怪と現代人
第二部 魔と妖怪
一 祭祀される妖怪、退治される神霊
二 「妖怪」の民俗的起源論
三 呪詛と憑霊
四 外法使い――民間の宗教者
五 異界・妖怪・異人
「おわりに――妖怪と現代文化」
「あとがき」
「注」
「解説――小松和彦の世界」
「はじめに――新しい妖怪学のために」の冒頭には、「人間文化の進歩の道程に於て発明され創作された色々の作品の中でも『化物』などは最も優れた傑作と云はなければなるまい」という寺田寅彦の言葉が紹介されています。
「妖怪学とはなにか」として、著者は「人間は想像する。その想像力はまた、さまざまな文化を創りだす創造力でもある。そしていま私たちはその創造力が作りだした膨大な種類の文化を所有しているわけであるが、そのなかでもっとも興味深いものの1つが『妖怪』と称されているものであろう。この『妖怪』を研究する学問が、ここでいう『妖怪学』である」と述べ、妖怪学を定義しています。
また、著者は「妖怪学」について、「学問としての『妖怪学』の整備の遅れの理由は、研究者の不足もあったが、『妖怪』が近代の科学において撲滅すべき『迷信』とされたことが大きかったように思われる。妖怪は近代人には必要ないものであり、妖怪研究はその妖怪撲滅・否定のための学問か、あるいは滅びゆく『迷信』を記録する学問で、近代における人間の生活にあまり積極的な意義を見いだせない研究とみなされたのである」と述べています。
続けて、著者は以下のように述べています。
「近代の科学、物質文明の発達・浸透は現実世界から妖怪を撲滅してきた。しかし、現代においても妖怪たちは滅びていない。活動の場を、都市の、それも主としてうわさ話やフィクションの世界に移して生き続けている。その意味で、現代人も妖怪を必要としているのである。このことは、妖怪が『迷信』としてかたづけてしまうわけにはいかない、つまり人間にとってとても重要な存在なのだということを物語っている。それは人間の精神生活の根源にかかわる事柄と関係しているらしいのだ。それが何なのか。それを明らかにするための学問として、新しい『妖怪学』は整備される必要があるといえる」
それでは、「妖怪学」の輪郭とはどのようなものか。
著者は、以下のように述べています。
「新しい妖怪学は、人間が想像(創造)した妖怪、つまり文化現象としての妖怪を研究する学問である。妖怪存在は、動物や植物、鉱物のように、人間との関係を考えずにその形や属性を観察することができるものではなく、つねに人間との関係のなかで、人間の想像世界のなかで、生きているものである。したがって、妖怪を研究するということは、妖怪を生み出した人間を研究するということにほかならない。要するに、妖怪学は『妖怪文化学』であり、妖怪を通じて人間の理解を深める『人間学』なのである」
続けて、妖怪学はいろいろな問題を設定するとして、「なぜ人々は妖怪を想像するのか、そのような妖怪のイメージはどのように形成されたのか、どのような種類の妖怪(妖怪種目)があるか、あるいはそうした妖怪を創造することの利点や欠点はどこにあるのか、日本の妖怪文化と諸外国の妖怪文化との違いはどこか、現代の科学ではかつての人々が妖怪現象とみなしたことをどのように説明できるか、等々」と述べます。
続けて、著者は「この『妖怪学』の研究領域は大きく2つのレベルに分けられる。1つは現実世界において妖怪現象、妖怪存在を信じている人々の語る妖怪に関する研究であり、もう1つは文学や芸能、絵画などに物語られ、演じられ、描かれる、フィクションとしての妖怪についての研究である。だが、やっかいなのは、この2つの領域は互いに影響関係にあり、現実世界で語られている妖怪をめぐる話の多くが、こうした研究領域つまりフィクションとノンフィクションの境界から立ち現れていることであろう」とも述べます。
さらには「妖怪学」について、著者が考えている「妖怪学」は、「妖怪」に関する研究を可能なかぎり網羅するような形で構想されているとして、「したがって、いうまでもなく1人の妖怪研究者がすべての分野にかかわる必要はない。人文科学、社会科学、そして自然科学の諸分野に属する妖怪研究者が、それぞれの立場から妖怪を研究すればいいわけであるが、その成果を共有し総合していくための場として『妖怪学』の必要を提唱しているのである」と述べるのでした。
「妖怪学の3つの潮流」として、著者は「私自身の妖怪研究は、『妖怪の民俗学』『妖怪の社会学』『妖怪の口承文芸学』『妖怪の宗教学』といった分野に属している。そうした分野からみると、妖怪学の流れとして、次の3つが目立っている。その1つの研究の流れが、妖怪現象や妖怪存在を信じる人々に対して、科学的知識を動員してそれを否定していく研究である。簡単にいえば、妖怪を『迷信』としてとらえ、それを科学で撲滅し、人々を迷信から解放しようという目的での『妖怪学』である。『タヌキ囃し』と信じられていたのは、タヌキの仕業ではなく、遠くの祭り囃しが風の関係で近くで聞こえるように感じられたものだったとか、夜道で出会った大入道は、月影が作った大木の影を見誤ったものだ、といった具合に合理的に解き明かし、妖怪を信じる人々のそれまでのコスモロジー、つまり世界の認識の体系を破壊し、近代の科学的・合理的なコスモロジーを身につけさせようとするわけである」と述べています。
続けて、著者は「日本で最初に『妖怪学』という学問を提唱した井上円了の妖怪学は、このような意味での妖怪学であった。したがって、この種の妖怪学者は、この世から妖怪を信じる者が一人もいなくなるまで妖怪退治を続けることになる。この研究を支えているのは、妖怪がいなくなることが人間の幸福な生活だとする信念である。井上は明治中期から大正にかけて精力的に妖怪現象を調査し、その撲滅を続けた。井上のような妖怪を迷信とみなして撲滅する『妖怪学』と並行して、同じような妖怪撲滅・否定を行なっていたのが、黎明期の近代医学であった。人間は自然との関係や人間関係のなかで生活しており、そのなかから生じるさまざまな不安や恐怖、精神的あるいは肉体的疲れから、『妖怪』を生み出し呼び招くことがある。たとえば、幻覚や幻聴、妄想現象などのなかの『妖怪』がそれである。そして不安が高じると社会生活を送っていくことが困難な状態つまり病気になることもあった。社会学的あるいは心理学的には妖怪は存在し体験されていたのである。それはたとえば「キツネ憑き」のような現象であった。これを近代医学は『精神病』(当初は祈禱性精神病などと称された)と診断した」と述べています。
その一方では、妖怪を迷信とみなして撲滅すべきだといった具体的対応はとりあえず脇に置き、日常生活を送っている人間が信じている妖怪とその社会的背景を調査し、その機能や信仰生活、コスモロジーを探っていくことを目的とした社会学的「妖怪学」や、妖怪伝承を採集し、その分布から妖怪信仰の変遷の過程を復元する民俗学的「妖怪学」も存在していたといいます。こうした「妖怪学」を構想していたのが、民俗学者の柳田国男でした。そして、その柳田国男の「妖怪学」の延長上に、その後の必ずしも多いとはいえない妖怪研究が展開されてきたようであると、著者は言います。そして、著者の研究もこの流れのなかに位置づけられるべきものだと考えているそうです。
「柳田国男の妖怪学」として、著者はこう述べます。
「柳田の民俗学において妖怪研究はあまり強調されているとはいえない。主な仕事としては、『妖怪談義』以外には『幽霊思想の変遷』『狸とデモノロジー』などがあるにすぎないのだが、『巫女考』『一目小僧その他』を初めとして多くの民間信仰・伝説・昔話などについての著作が妖怪にも関係する研究であって、見方によっては柳田の民俗学は妖怪研究と密接な関係をもった内容になっているといっていいだろう」
「柳田は、妖怪と幽霊を次のように区別する。妖怪(お化け)は出現する場所が決まっているが、幽霊はどこにでも現れる。妖怪は相手を選ばないが、幽霊の現れる相手は決まっている。妖怪の出現する時刻は宵と暁の薄明かりの『かわたれどき』(たそがれどき)であるのに対し、幽霊は夜中の『丑満つ時』(丑三つ、まよなか)である。この分類はその後の妖怪・幽霊研究の指標となった」
また、柳田の研究を発展させようとした研究者も妖怪と幽霊を区別しようとしているが、柳田の分類にあてはまらない事例が多いのに苦しんでいると指摘して、著者は「たとえば、池田弥三郎は『日本の幽霊』のなかで、多くの例外のあることを認めつつ、妖怪・幽霊のたぐいを、特定の場所に出る妖怪、人を目指す幽霊、家に憑く怨霊、の3つのカテゴリーに分けており、諏訪春雄はさらに慎重に『もともと人間であったものが死んだのち人の属性をそなえて出現するものを幽霊、人以外のもの、または人が、人以外の形をとって現われるものを妖怪というように考えておく』としている」と述べています。
柳田は日本人の信仰の歴史をふまえつつ、神の零落=妖怪への人間の対応の変化を「カッパ」を例にしながら4つの段階に区分しています。
「第1段階は人間がひたすら神を信じ、神が現れれば逃げ出すという段階で、カッパ(水の神)が人間の前に出現して相撲をとろう、といっても逃げ出すことになる。その結果、出現場所はカッパの支配地となる。第2段階は神への信仰が半信半疑となる時代で、カッパを水の神として信仰する気持ちがまだある一方で、その力を疑う気持ちが生じてきたというわけである。この時期がカッパが神から妖怪へと変化する過渡期ということになる。第3段階はカッパを神として信じなくなり、知恵者や力持ちがカッパと対決し、これを退治してしまう時代である。カッパが完全な妖怪になってしまったわけで、これが現代(大正から昭和初期の時代)だという」
そして第4段階として、愚鈍な者がカッパにばかされる程度になり、やがて話題にもされない時代がくる、と予想しています。著者は述べます。
「その時代が私たちの現代ということになるだろう。この仮説のいちばんの問題点は、日本の信仰全体の歴史を繁栄から衰退へと変化しているということ、個々の妖怪の歴史もやはり繁栄から衰退へと向かうということ、それぞれの時代にはその時代なりの神や妖怪がいることを、はっきり把握し区別しないまま論じているために生じているように思われる」
日本の妖怪の歴史をたどってみると、古代に勢力をふるった妖怪、中世に勢力をふるった妖怪、近世に勢力をふるった妖怪、等々、時代によって妖怪にも盛衰があると指摘し、著者は「たとえば、天狗の盛衰史、鬼の盛衰史、幽霊の盛衰史、カッパの盛衰史、口裂け女の盛衰史などを、私たちは個別に描きだすことができるが、これは信仰盛衰史とは直接関係するものではない。実際、信仰盛衰史の最先端に位置する現代でも、あいかわらず幽霊は活躍しているのだ。つまり、中世に勢力を誇った天狗族は近世になってあまり元気でなくなるが、その一方で、中世にはみられなかったカッパ族が農村を中心に勢力を誇るようになるというわけである。さらに、妖怪一つひとつの個体史についても、その盛衰・属性変化を認めることができる。つまり、人々に害を与える妖怪が、祀られて人々に繁栄をもたらす神になったり、追放・退治されたりする。妖怪の個別史ともいうべき個体史のレベルでも、神の零落としての妖怪という仮説は、その個体史の部分的な把握にすぎないのである」と述べます。
そして、「柳田以降の妖怪学」として、著者は「妖怪学は、というか日本の妖怪文化は、近年、まったく新しい時代に入ったかにみえる。多くの人々が妖怪に関心をもちだし、かなりの数の妖怪研究書や妖怪図絵、解説書のたぐいが刊行されだしたからである。それらの著作の内容ははっきりいって玉石混交である。しかし、こうした妖怪ブームの到来は、しっかりした内容の妖怪研究が期待されていることを物語っているのである。それに対応できるような『新しい妖怪学』が構築されねばならないのである」と述べるのでした。
第一部「妖怪と日本人」の一「妖怪とはなにか」では、「恐怖・空間・妖怪」として、著者は「人間を取り巻く環境は、自然であれ人工物であれ、恐怖つまり『警戒心と不安』の対象に変貌する可能性を含んでいるのである。その恐怖心が人間の想像力を動員して超越的存在を生み出し、共同幻想の文化を作り上げ伝承する。恐怖に結びついた超越的現象・存在――それが『妖怪』なのである」と述べています。
続けて、著者は以下のように述べています。
「妖怪はあらゆるところに出没する可能性をもっている。『警戒心と不安』を抱かせる存在は至るところに存在しているからである。のどかな田園の風景のなかにも、自分の家の居間にも、超近代的なビルのなかにも、妖怪は出没することができるのである。もっとも、そのなかでも、妖怪が出そうな空間というものが存在している。これは人間がのっぺらな漠然とした空間を分割し、安全な空間と危険な空間に分類しているからである」
「不思議・災厄・妖怪」として、著者は「妖怪研究の基本的前提は、人々が『不思議だ』と思う現象が自分たちの生活世界に存在していることである。そのような現象が存在しなければ、神や妖怪たちも人々の生活世界のなかに存在する余地がない。超越(超自然)的存在や超越的力の存在を想定して、それによってその不思議な現象を説明しようとするときに、神や妖怪が発生してくる(後にくわしく説明するように、ここでいう『神』とは、人々に祀り上げられている超越的存在であり、『妖怪』とは祀り上げられていない超越的存在のことである)」と述べます。
また、「妖怪を定義する」として、著者は「妖怪とは、日本人の『神』観念の否定的な『半円』なのだということが明らかになってくる。つまり、伝統的神観念では『妖怪』は『神』なのである。そうだとすると、さきに疑問を投げかけた祟る道祖神は『妖怪』なのだということがはっきりしてくるであろう。東北の有名な『妖怪』であるザシキワラシも『神』であり、傘のお化けも『神』なのである。それが人間に対して多少でも否定的にふるまったとき、妖怪研究者からみれば『妖怪』になるというわけである」と述べます。
続けて、著者はこう述べています。
「したがって、人間に否定的に把握された不思議現象は、すべて妖怪現象であり、その説明に引き出される超越的存在も妖怪存在ということになる。ということは、極端なたとえを出せば、大日如来も人に災厄をもたらせば『妖怪』であり、アマテラスオオミカミも人に祟れば『妖怪』ということになる。逆にいえば、人を驚かす『傘のお化け』も人に幸福をもたらせば『悪神』ではなく『善神』となり祀り上げることもできるわけである。こうして、東北のザシキワラシが『神』か『妖怪』かという問題も解決することができる。すなわち、ザシキワラシはいつでも伝統的神観念に従えば『神』である。それが祟りをなしたり悪さをしたりするとき、研究者は『妖怪』というラベルをはることになる、ということなのである」
「妖怪の予防と駆除」として、人々は空間の境界、時間の境界にも注意をはらい、そこにさまざまな魔除けの仕掛けを用意するが、それでも侵入し危害をもたらすに至った妖怪に対しては、どのようにふるまえばいいのだろうかと問題提起し、著者は「儀礼的なレベルでいえば、神社仏閣にお参りしてその霊験を期待するのも1つであるが、多くは妖怪退散の儀礼を宗教者に依頼することになる。神話的なレベルでは、酒呑童子退治のような物語となるわけである。こうした妖怪退治にとくに能力を発揮したのが、密教系の僧であり、陰陽道系の宗教者であった。多くの妖怪退治の物語は、彼らが行なう妖怪退治=病気などの災厄除去の儀礼の効果を語り示すために語り出されたという側面をもっている。中世に制作された『玉藻前草紙』などは、陰陽師の安倍泰成による、上皇に取り憑いて病気にした妖怪狐祓いの儀礼の物語であり、妖怪=悪霊退治儀礼と妖怪退治物語の深い関係を如実に描き出しているといっていいだろう。つまり、妖怪に攻撃され苦しめられたときには、呪験の優れた宗教者に助けを求めるのが最良の方法であったのだ」と述べています。
また、「『生活社会』の三類型と妖怪」として、著者は「『マチ』は『ムラ』とは異なり、基本的な生業形態を貨幣経済を基盤にした『交換』に置いている地域社会である。『マチ』の語源が『間+路』であり、『ミチ』(道・路)や『イチ』(市)、『チマタ』(巷)の類縁語であることからもわかるように、近隣のムラやマチから人々がさまざまなものを交換するために集まってくるところである。そこで当然のことであるが、それは交通の要所に形成される。この社会は二重構造になっていて、「ムラ」とは異なり、交換する目的でやって来る人々に対して社会はつねに開放されているが、その一方では『マチ』の定住構成員は彼らの「生活社会」を形成し、その社会のレベルでは『ムラ』と同様に、強い社会的紐帯をもった排他的な地縁集団を作っている。これに対して、『都市』は『マチ』をこえたところに成立している社会である」と述べます。
二「妖怪のいるランドスケープ」では、「水木しげる少年の妖怪体験」として、「近年たいへんな人気を呼んだ漫画家の水木しげるの描く妖怪画の主だったものは、近代以前からの妖怪たちで、その多くはマチやムラで伝承されてきたものであった。水木しげるは、高度成長期以降、急速に衰退・消滅していったこれらの妖怪たちへの深い哀惜の思いから、まるで記念写真を撮るかのように絵筆をとって、彼の創作妖怪だけではなく、民間伝承のなかの妖怪をもカンバスに描き込んだ」と書かれています。
続けて、水木しげるについて、「彼は現在の鳥取県境港市の海浜地域(港町)に生まれ育った。米山俊直の小盆地モデルでいえば、完全な小盆地宇宙ではなく、美保湾に面した『疑似半円形盆地』でしかも『盆地底』には湖に相当する『中海』が広がっていた。したがって、そこは典型的な農村とはいささか異なる、漁村とそれを背景にした町場を主体とする地域であったといっていいだろう。しかし、家々の祀りごとに関与する『のんのん』と呼ばれる巫女のたぐいの老婆が、幼少期の水木に語ったという妖怪の話は、いわゆる私たちが『田舎のコスモロジー』と呼んでいる、日本の多くの地域で伝承されていた妖怪文化とそれほど違いがあるわけではない」と書かれています。
最初に登場するのは「天井なめ」という妖怪で、「のんのんばあは、薄暗い台所の天井のシミを見ては、『あれは、夜、寝静まってから「天井なめ」というお化けが来てつけるのだ』と教える。水木は、それらしきシミを見つけて、『天井なめ』の存在を確信する。こうして彼の想像力が目に見えない世界を作り上げてゆくのである」と書かれています。帰り道では、カモメのような、猫のような声を聞くと、のんのんばあは、あれは「川赤子」の声だといい、どこかでゴーンと鐘の音がすると、あれは「野寺坊」という妖怪が人の住まぬ荒れ寺で鐘を鳴らしているのだと言います。桟橋のかたわらにあった廃屋をのぞこうとすると、「白うねり」という古ぞうきんのお化けがいて、首にからみつくと言うのでした。
こうして、このちょっとした「旅」で、水木少年は、この地方に棲む妖怪たちの幻影を、その景観のなかに見いだしたのであったとし、著者は「神ごとを行なうのんのんばあの思考は、私たち現代人とちがった形で働いている。ばあは私たちの五感がつかまえることのできる世界の事象を、目に見えない霊的な世界とたえず結びつけて理解しようとしている。彼女は、私たちよりもうひとつ次元の高い世界観から世界を見ていると、いったほうがいいかもしれない。同じ風景や事物を見ていたとしても、ばあと私たちとではずいぶんちがった読み取りをするのである」と述べるのでした。
また、著者は「もう1つ重要なことは、季節の折々にも妖怪や異界を体感させてくれるようなときがあったことである。正月の注連を集めて焼く『とんどさん』、この期間は海で泳いではならないとされた『お盆』と最後の日の『灯籠流し』、子どもたちが掘り出した石の地蔵を祀り上げた『地蔵祭り』、親戚の『葬式』、『モバをとらせた』(海草をとらせた)と語られた『間引き』、海での漁船の遭難除けなどの年中行事や人生儀礼、そして事件が、直接あるいは間接的に目に見えない世界と結びつき、この地方の人々の生活に陰影をもたらし、景観に奥行きを与えていたのである」とも述べています。
四「妖怪と都市のコスモロジー」では、「平安京の恐怖空間」として、著者は以下のように述べています。
「近世は、人間の内部の『闇』に起源を求める妖怪=幽霊と、自然の『闇』に起源を求める妖怪=キツネが活躍した時代であったが、しだいに幽霊(怨霊)のほうへと関心が向かっていったようである。というのも、都市の人々を取り囲む空間がますます人工的になり、ますます自然とは離れた人間関係を中心とする世界になっていったからである。近世の都市は、妖怪論の立場からすると、自然起源の妖怪と人間起源の妖怪たちがその存亡をかけて勢力を競いあっていた時代といっていいかもしれない」
五「変貌する都市のコスモロジー」では、「『闇』の喪失」として、著者は「大正童謡には、近代資本主義システム・科学文明のなかに人々が編入されて新たな文化環境を受容していく過程で消滅しつつあった『闇』や民俗社会・伝統的社会の古層からの『声』が託されているのだ。このことを見事に分析したのが朝倉喬司であった。彼もまた、『後ろの山』とか『背戸』といった大正童謡にたびたび登場する言葉には、民俗社会のわらべ唄『かごめかごめ』に歌われる『後ろの正面』とも通底する『闇』つまりは『死』の領域を想わせる不気味な響きが託されているという」と述べています。
また、「後ろの山」とか「背戸」といった空間は居住空間としての家のレベルで意識された「闇」の空間ですが、これをより抽象的に表現したものが「奥」という観念であろうと指摘し、著者は「『奥』は『表』や『前』にある程度対立する言葉であるが、『裏』や『後ろ』に対応する概念ではなく、『表』や『前』からの『深さ』ないし『距離』をともなった『裏』や『後ろ』である。『奥座敷』『奥山』『奥義』『奥宮』『奥の院』といった言葉には、神秘的で閉ざされた『闇』の空間・領域といった意味合いが暗黙のうちに含まれている。『奥』は身体的・生理的体験を通じて把握される。それは身体によって感受される空間の陰影であり、厚み・深みである」と述べています。
さらに「奥」について、著者は「〈奥性〉は最後に到達した極点であるが、極点そのものにクライマックスはない場合が多い。そこへたどりつくプロセスにドラマと儀式性を求める。つまり高さでなく水平的な深さの演出だからである。多くの寺社に至る道が屈折し、わずかな高低差とか、樹木の存在が、見え隠れの論理に従って利用される。それは時間という次数を含めた空間体験の構築である。神社の鳥居もこうした到達の儀式のための要素にほかならない」と述べます。
「妖怪の近代」として、近代から現代に至る百数十年は、妖怪たちにとってまさに存亡の危機に直面した時代であったことを指摘し、著者は「危機は複合した形で襲ってきた。まず、西洋から輸入された新しい知識や科学的合理主義の考え方にしたがって、怪異・妖怪現象の類の多くが合理的に説明され、そうした現象を霊的存在や神秘的力によって説明することが否定されることになった。たとえば、幽霊は幻覚・気の迷い、『タヌキ囃し』のような怪音は遠くの祭り囃しの音が風の関係などで近くから聞こえるように感じられたもの、キツネ憑きによる病気は精神病、等々というように次々に否定されていった。妖怪博士との異名をとった哲学者の井上円了は、そうした妖怪僕滅運動の急先鋒であった。井上は驚くほど多くの妖怪談を書物や新聞・雑誌、さらには実地調査によって、採集・検討し、その正体を科学的見地から説明を加えている」と述べます。
そして、著者は「妖怪は人々の心が生み出す存在である。人々が心に『闇』を抱えもち、人々がさまざまなことに恐怖する心性をもっているかぎり、人々は妖怪を生み出し続けるはずである。では、いま、人々はどこにいるのだろうか。妖怪はどこにいるのだろうか。その答えははっきりしている。もちろん、それは都市である。日本の人口の大半が集中している大都市こそ、妖怪の発生しやすい空間なのである。だが、すでに見たように、大都市は、近代以降、激しい妖怪撲滅=否定の運動・教育が推進されてきたところであり、妖怪の出没しやすい『闇』も消滅してしまっている。そのような大都会にも、妖怪は出現可能なのであろうか」と述べるのでした。
六「妖怪と現代人」では、「現代の妖怪の特徴と現代人の不安」として、現代人はまだ人間の死後の霊魂の存在を信じている、あるいは信じようとしているのであると指摘し、著者は「このことは、さらに次のような事態をも表現している。もはや、現代人は自然との関係を断ち切り、それゆえ自然を恐れる心を失ってしまっているらしいということである。現代の都市空間で、人間を恐怖させるのは人間だけだというわけである。もし現代人の心をのぞくことができたならば、きっと人間への恐怖がうず巻いていることだろう」と述べます。
続けて、著者は「しかし、現代においては、この幽霊さえも衰退の一途にあることは明らかである。というのは、現代の怪談を検討してみると、幽霊の姿を見たとする話がだんだんと少なくなっていて、それに代わって、手だけ、声だけ、怪しい音だけ、といった話へと変化しつつあるかにみえるからである。将来は、それさえ話のなかに登場せず、ただ怪異・不思議現象だけがなんの説明もなく語られるようになるのかもしれない」とも述べています。
第二部「魔と妖怪」の一「祭祀される妖怪、退治される神霊」では、「『神』と『妖怪』の相違」として、「多くの民俗社会の妖怪たちが次第に消滅しつつあるなかにあって、突然に都市に出現した『口裂け女』の場合、現代文化に固有の出現理由があったにちがいない。しかし、『口裂け女』の属性が『山姫』や『山姥』『雪女』などの民俗社会の妖怪の属性ときわめて類似していること、最初の出没が山の中であったらしいこと、などから考えると、『口裂け女』を育てた環境は現代文化であったが、彼女を生んだ母胎は日本の民俗文化であったと思われる」と書かれています。
柳田国男は「妖怪」を「神霊」の零落したものとして把握しました。すなわち、前代の信仰の末期現象として現れたのが「妖怪」なのであって、カッパは水神の、山姥は山の神の零落したものだと理解したわけです。柳田国男は、こうした考え方を「我々の妖怪学の初歩の原理」と述べています。著者は、「柳田の妖怪論の『初歩の原理」には、多くの問題点が含まれているように思われるのだ』と述べます。柳田の説に従って妖怪を考えようとすると、いろいろと不都合なことが生じてしまうからだとして、「たとえば『妖怪』が『神霊』の零落したものだと仮定すると、日本文化や人類文化の発展の一段階において、『妖怪』が存在せず、『神霊』のみが信じられた時期があったと仮定しなければならない。なぜならば、『妖怪』が最初から『妖怪』として人々の前に登場しえないからである。善良な人々とそうした人々に富をもたらす善なる神々と善なる自然のみからなる社会・文化が、人類文化の発展過程のある時期に存在したとは、とうてい考えられないことである。それはあまりにも現実離れした夢物語であろう」と述べます。
さらに、著者は以下のように述べています。
「人類は自分たちの合理的知識では統御しえないものを彼らの環境のなかに認め、それを概念化したとき、私たちが『超自然的力』とか『超自然的存在』とか呼ぶもの、つまり『神霊』や『妖怪』たちが生み出されたのではなかっただろうか。人類の長い歴史のなかで、それがいつ生じたのかは定かではない。しかし、人類が直立歩行し、火を管理し、道具を創り、言語を用いるようになったときには、『神霊』や『妖怪』たちも生まれていたにちがいない。そうした時代にあっては、柳田説とは逆に、未知のことが多いがために、自然の脅威にさらされていたがために、『妖怪』たちの活動領域は多岐にわたっていたと思われる。したがって、遠い昔、日本列島に人が住むようになったとき、彼らの文化のなかにすでに『神霊』や『妖怪』たちも棲んでいた、とみなすのが妥当のように思われるのである」
著者は、「超自然的存在」を「妖怪」とか「魔」として記述する場合の定義について、
「『妖怪』とは、世界に生起するあらゆる現象・事物を理解し秩序づけようと望んでいる人々がもつ説明体系の前に、その体系では十分に説明しえない現象や事物が出現したとき、そのような理解しがたいもの、秩序づけできないものを、とりあえず指示するために用いる語であるということができる。古代人は、これを『もの』と呼び、その出現の徴候を『もののけ』と呼んでいた(かつては、『もの』『化け物』などと並んで『百鬼夜行』『妖物』『魑魅魍魎』などといった言葉も用いられていた)」と述べています。
つまり、「妖怪」とは、正体が不明のものであり、正体不明であるがゆえに遭遇者に不思議の念、不安の念をいだかせ、恐怖心を生じさせ、その結果「超自然」の働きをそこに認めさせることになる現象・事物を広く意味しているのです。「いいかえれば、民俗社会がもつ2つの説明体系、つまり『超自然』を介入させない説明体系と『超自然』を介入させた説明体系、のあいだをゆれ動いている正体不明のものが、人々の認識過程の第一段階の『妖怪』なのである。そして、正体不明であるがゆえに、人々に不安や恐怖心を起こさせるので、この段階の『妖怪』も、人々にとって好ましいものではないといえるであろう。しかし、この段階では、まだ人に対して危害を加える邪悪なもの、といった明確な判断を下すまでには至っていない」と、著者は述べます。
続けて、著者は以下のように述べます。
「それでは、こうした2つの異なった説明体系の裂け目に立ち現れてきた正体不明の『妖怪』を、民俗的思考はどう処理し秩序づけようとしたのであろうか。それは、結局、人々が所有する思考体系が、『超自然』(超越的なもの)の介入に頼らずに『妖怪』の正体を究めることができるか、それとも、それができないために『超自然』の領域に組み入れて説明しようとするか、2つのうちのいずれかを選ぶことによって決まることになる」
さらに、著者は「『超自然的力』や『超自然的存在』もしくは『霊的存在』は、大きく2つに分類することができる。1つは、人々に富や幸いをもたらすもの、いま1つは人々に災厄をもたらすもので、前者は『神』と呼ぶことができ、後者は『妖怪』とか『魔』と呼ぶことができるはずである。すでに述べたように、『魔』という語は、もともとは『仏』とその一党に敵対するものであったが、日本では、本来の意味よりも広い意味で用いられるようになっていたようである」と述べています。
わたしたちはこれまで、民俗社会の「神」や「妖怪」あるいは「魔」を規定するために、人々の思考のプロセスに着目してきたと指摘されますが、日本の「神」や「妖怪」は、キリスト教などの神や悪魔といったものと大きく異なっているとして、著者は「キリスト教にあっては、神はつねに神であり、けっして悪魔となることはなく、悪魔はつねに悪魔であって神になることはない。悪魔はつねに神に対立して存在し続けているのである。映画の『ドラキュラ』や『エクソシスト』などを思い出していただければ、そのことがすぐに理解できるはずである。ところが、日本人の神観念では『神』とされていたものが『妖怪』となったり、『妖怪』であったものが『神』になったりする。日本の『霊的存在』はたいへん可変性に富んだ性格を示しているのである」と述べます。
さらに、「マイナスかプラスかを知る指標としてもっとも適切なものと思われる一連の行為が浮かび上がってくるとして、著者は「それが『祀り上げ』と『祀り棄て』という行為である。人々は『妖怪』を『神』に変換するために祭祀を行なう。また、人々の祭祀が不足すると、『神』は『妖怪』に変貌することになるのだ。『神』とは人々によって祀られた『超自然的存在』であり、『妖怪』とは人々に祀られていない『超自然的存在』なのである。別のいい方をすれば、祭祀された『妖怪』が『神』であり、祭祀されない『神』が『妖怪』ということになるのである」と述べます。
二「妖怪の民俗学的起源論」では、「怨霊と御霊」として、「怨霊の示現の仕方には、可視的なつまり直接的な仕方と、不可視的つまり間接的な仕方の2つのタイプがあるが、通常、社会的な問題となるのは、不可視的な示現である。これは『祟り』として理解される。たとえば、社会に疫病が流行したり、天変地異が続いたり、次々と死人が出たりしたとき、その原因を怨霊の祟りと判断するような場合である。9世紀以降、宮廷の史書などに『御霊』という文字が記され始めるが、この御霊とは一言でいえば、こうした怨霊の祟りを鎮めるために祭儀を催して、『神』に祀り上げた霊を意味している」と書かれています。
三「呪詛と憑霊」では、「呪詛――魔に身を任せた人々」として、反社会的行為には、殺人、放火、食人などさまざまな行為があるが、そのなかでももっとも邪悪で恐ろしいのは、人目を忍んで行なわれる、「呪詛」つまり「呪い」であったとして、著者は「呪詛とは、一定の所作や言葉によって超自然的な力や存在に働きかけ、憎むべき敵を殺したり病気にしたりしようとする行為で、文化人類学では『邪術』と呼びならわしている。呪詛の記述は、早くも『古事記』や『日本書紀』にみえている」と述べています。
四「外法使い――民間の宗教者」では、「陰陽師と式神」として、「妖怪」や「魔」の類を操作する呪術師としての宗教者の思想は、平安時代にはすでに形成されていました。そしてその中でも最も重要な宗教者が、「式神」を操るという陰陽師であり、「護法」を操る祈禱僧(験者・山伏)であったと指摘し、著者は「陰陽師とは、陰陽五行思想に基づいて占いや祭儀を執り行なう宗教者で、律令体制下にあっては、政府内の陰陽寮という役所に依拠して、さまざまな祭儀の教育と研究を行なっていた。しかも、大陸からこの思想が輸入された当初は、科学・技術的側面が強かったようであるが、しだいに呪術的色彩を強め、王朝時代には、鬼神を操り呪いをかけたりする恐ろしい存在とみなされるようになっていたのであった。この背景には、奈良時代に廃止された呪禁道の思想が陰陽道のなかに吸収されたということが関係していたように思われる」と述べます。
また、陰陽師について、著者は「陰陽師は、物を覆い隠してそのなかにあるものを占い当て、『もののけ』の正体を見破り、十二神将(陰陽道で占いに用いる占盤を守護している、十二の方位に配置された神格)や三十六禽(一昼夜十二辰の神で、一辰にそれぞれ3つの動物が配置される)を動かし、『式神』を操り、符法によって鬼神の目を意のままに開閉し、男や女の魂魄を自由に出し入れできるというのである。なんとも恐ろしい存在である。まさに身は人間の姿をしているが、その能力は神や鬼に近く、この世にあるが、心は天地のものである、と評されるのもうなずけるというものである」と述べています。
さらに、「外法神」として、「護法」にしろ「式神」にしろ、それは修験道や陰陽道の秘事にかかわる神霊の総称であったとして、著者は「平安末期から鎌倉初期の動乱期には、祈禱や祭儀を行なう修験者や陰陽師たちは、貴族や武士をはじめとする多くの人々に自分たちの法力が秀れていることを誇示する一方、多くの神秘的な法術や祭式を編み出し、それが人々のあいだに浸透していったのであった。現世の利益を追求する民衆、アニミズム的な世界観を基調とする民衆・民俗社会に浸透するためには、それにみあった信仰に仕立てなおしたり、新しい内容を作り出したりする必要があったにちがいない。また、修験道と陰陽道との混淆も宗教者たちの手によって徐々に行なわれていったようである」と述べます。
五「異界・妖怪・異人」では、「秩序・災厄・異人(妖怪)」として、著者は「生理的不安が、人々に『妖怪』を見させることもある。しかし、それにもまして、『私』や社会に恨みを抱いている人々がいるという信念もまた『妖怪』を生み出す。したがって、そうした信念を抱いている人々に災厄が生じたとき、その原因は、『我々』に恨みを抱いている『妖怪』、あるいはそれと深い関係をもつ『彼ら』に求められることになる。『彼ら』は共同幻想の内部にあっては、まぎれもなく『妖怪』なのである」と述べています。
続けて、著者は「しかし、真に問題となるのは、『魔』や『妖怪』を必要としている『我々』のほうなのではないだろうか。そして、そう問うとき、妖怪や魔の問題は、怨み・憎しみ・妬みといった人間の心の問題に置きかえられるはずである。冒頭において、『妖怪』を論ずることは、古代から現代に至る日本人の生き方に触れる問題と述べたのは、このような意味からであった。妖怪研究とは人間の心の研究であり、人間の社会の研究というべきなのである」と述べるのでした。
「おわりに――妖怪と現代文化」では、著者は「口裂け女」に言及し、著者は「『口裂け女』はほぼ全国を駆けめぐって立ち去っていった。いまはもう過去の妖怪である。私たちはこの妖怪について、猛威をふるっていた当時からその理由をあれこれ推測してきた。はっきりしているのは、こうしたうわさを語った人々の心の内部にある『闇』(=恐怖)がこのような妖怪を生み出したということである。しかし、その『恐怖』とは具体的になんなのだろうか。たしか『教育ママ』の象徴的表現だとする説もあった。私は女性を支配する『美』の価値観に対する『恐怖』がこの『口裂け女』を生み出したとの説を唱えた」と述べています。
続けて、著者は「いずれにしても、現代の妖怪は現代の都市生活・環境に適応した形で登場してくる。そして現代人が心に『闇』を抱えるかぎり、妖怪撲滅をはかる『科学者』たちの目をくらますようにして、絶えず出没するのである。柳田国男が予見したように、100年後、200年後も妖怪たちはその時代にふさわしい姿にばけて出現することだろう。出現しないような時代が到来したとしたら、その時代は人間がいないか、人間が人間でなくなってしまった時代ではないかと私には思われてならないのだ」と述べています。
また、妖怪への関心は現代文化においてけっして孤立した現象ではありません。人間の心・内面にかかわるさまざまな社会現象、たとえば、密教、新々宗教、神秘主義、占い、予言、臨死、怪獣、バーチャルリアリティ体験といった事柄への関心の高まりとも通底する現象であるとして、著者は「こうした社会現象の背景にあるのは、いうまでもなく現代の閉塞状況である。ここ数十年の間に、私たちの時代は大きく変わった。科学文明・物質文化の浸透によって都市空間から『闇』が消滅し、明るいそして均質化された世界が私たちの日常生活の環境となり、そこで単調だともいえる毎日を繰り返してきた。ところが、私たちはこの日常生活をしだいに苦痛に思うようになってきたのである」と述べています。
さらに、人々の心の中の「闇」が広がりつつあるとして、著者は「『妖怪・不思議』は、科学主義・合理主義が生み出した便利さや物質的豊かさを享受しつつ、その世界を支配している価値観に疑問をもったり、それにしたがって生きることに疲れた人々の前に立ち現れてくる。『妖怪・不思議』は現代社会を支配している価値観、つまり人々の生きている『現実』世界をこえたものである。人々はそうした『妖怪・不思議』を、フィクションを通じてであれ、うわさ話としてであれ、自分たちの世界に導き入れることで、自分たちの『現実』にゆさぶりをかけたり、そこからの離脱を試みているのである」とも述べています。そして、最後に著者は「『妖怪・不思議』は、私たちに『もう1つの現実』の世界を用意し、そこで遊ぶことを、そして、それが人間にとってどれほど大切なことかを教えてくれるのである。妖怪学が必要な理由の1つはここにあるといえよう」と述べるのでした。
本書は、妖怪研究の第一人者である著者が、井上円了や柳田国男といった妖怪研究の先達たちを乗り越えて、まさに「現代人にとって妖怪とは何か」ということを考え尽くした名著であると思います。国学や日本民俗学の系譜を受け継いだ「妖怪学」とは、そのままでも「人間学」であることを痛感しました。新型コロナウイルスが感染拡大すると、疫病を防ぐとされるアマビエという妖怪の話題で持ち切りになりましたが、日本人の「こころ」には今でも妖怪が生きています。
2020年8月31日 一条真也拝



























 長い間、お疲れ様でした !
長い間、お疲れ様でした !


 バート・スターン(映画公式HPより)
バート・スターン(映画公式HPより)
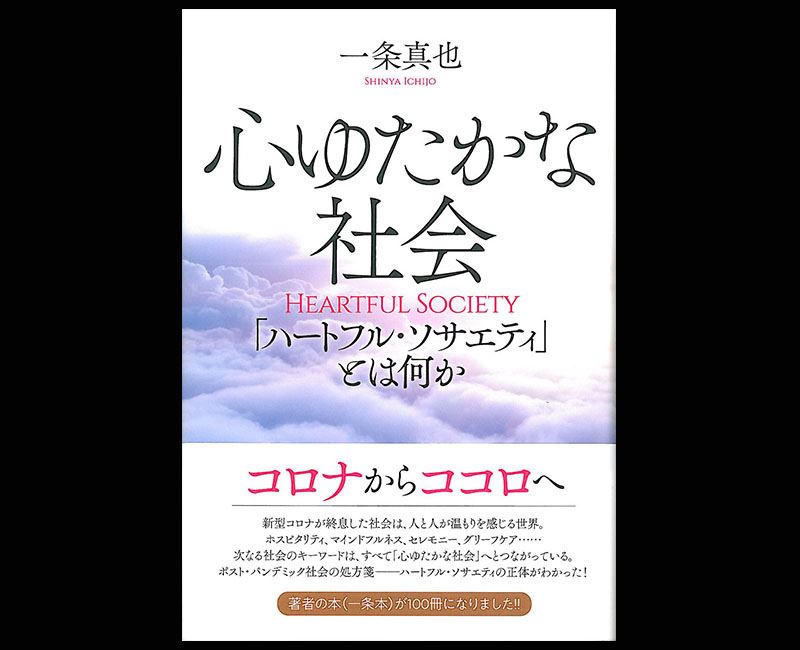 『
『
 コロナ禍でも人生を楽しまねば!
コロナ禍でも人生を楽しまねば!







