一条真也です。
『悲しみの力』スーザン・ケイン著、坂東智子訳(ディスカヴァー・トゥエンティワン)を読みました。著者は、プリンストン大学、ハーバード大学ロー・スクール卒業。ウォール街の弁護士を経て、ライターに転身。『ニューヨーク・タイムズ』紙、『タイムズ』紙などに記事を寄稿。他にも、メリルリンチや法律事務所や大学などで交渉術の講師も務めます。
スーザン・ケインは、リンクトインによる「世界のインフルエンサー」トップ10にも名前が挙がっています。初の著書『内向型人間の時代』は世界の40を超える言語に翻訳され、数多くのベスト作品リストに名を連ねました。彼女が「内向型人間の力」について語っているTEDトークは、は4000万回以上視聴されています。

本書の帯
本書の帯には、「アダム・グラントグレッグ・マキューン、ダニエル・ピンク絶賛」「別れ・死、愛の喪失、不安・・・・・・なぜ、心の痛みに向き合い、受け容れるべきなのか?」「ニューヨークタイムズ・ベストセラー『内向型人間の時代』著者最新作!」と書かれています。

本書の帯の裏
帯の裏には、「ネガティブな感情をないがしろにして、太陽のように明るく模範的な自分を演じたとしても、あなたは『健康』にも『幸せ』にもなれない――」「この本は、『憂うつ質』についてのものだ。この気質を私は『ビタースイート』と呼んでいる。『ビタースイート』であることは、『静かな力』であり、『生き方』であり、『多くの物語の伝統的なテーマ』でもあって、人間としての可能性にあふれている。『ビタースイート』であることは、不変の美しさを備えながらも大きな欠陥のある世界で生きていく、という課題に対する、確実で気分を高めてくれる『答え』でもある。そして何より、『ビタースイート』であることで、『苦痛』への対処法が見えてくる。つまり、『苦痛』を抱えていたら、それを受け容れ、ミュージシャンたちがやるように、それを『芸術作品』に転換したり、何か『癒しになるモノ』、『新しいこと』、『心の栄養になるもの』に転換したりすればいいのだ。(「はじめに」より抜粋)」と書かれています。
カバー前そでには、「メランコリックな人が持つポジティブな力とは」として、
「『ビタースイート』な人は、『明』と『暗』、『誕生』と『死』――つまり『ビター』と『スイート』――は永久に対をなすことに気づいてもいる。(中略)そうした二元性――『明』もあれば『暗』もある――を十分に受け入れることが、逆説的ではあるが、二元性を超越する唯一の方法なのだ。(「はじめに」より)」と書かれています。
 アマゾンより
アマゾンより
アマゾンの内容紹介には、「著者は、大学生時代、寮の一室で、友人から〝葬式の曲〟と言われるような悲しげな音楽をよく聞いていた。そうした曲を聴くと、『悲しい』のだが同時に『愛』を感じ、心が開かれていく。そして自我が消え去るような超越のひとときが訪れる。どうして切ない曲を聴くと、妙に気持ちが高まるのか? その疑問をきっかけに著者は25年考え続け、それが本書に結実した。本書は、『明と暗』『誕生と死』つまりビターとスイートは、永久に対になっているという前提にもとづいている。『常にポジティブであれ』といった社会的圧力から『悲しみ』や『切なる思い』『喪失感』といった感情に蓋をするのではなく、インスピレーションとして受け入れることが、創造力を高め、より深く豊かな人生を達成することにつながるのだという。つまり、『苦痛』を『創造力』や『超越する力』『愛』に転換するという考え方が、本書の核になっている」と書かれています。
 アマゾンより
アマゾンより
また、アマゾンの内容紹介にはこうも書かれています。
「『悲しみ』『切なる思い』を受け入れることに、どんなメリットがあるのだろうか。著者は『悲しみ』の共有から『思いやり』『人とのつながり』が生まれると指摘している。『悲しみ』というのは、他人を思いやり、他人に利益をもたらす感情であり、愛情を生み出し、人と人をつなげる手段にもなる。すべての感情の中で、最高の『接着剤』になるのだ。『悲しみ』は創造力を駆り立てる主な感情でもある。「創造力」のある人は苦痛を直視し、それをもっといいものに変えることができる。悲しい気分は注意力を研ぎ澄まし、集中力を高め、記憶力を向上させる。また、思考や判断の偏りを修正することもできるようになる。『切なる思い』とは、クリエイティブでスピリチュアルな状態への入り口だ。私たちの感情を解き放ち、気分を高め『魂の交わり』とか『畏敬の念』といった気高い状態を生み出してくれる」

アマゾンより
さらに、アマゾンの内容紹介には、「『切に思う』ことは、心のふるさとに行く手段となり、そのこと自体が、心理的な癒しにもなる。さらに、つらい感情を受け入れる能力は長期的な成功にもつながる。習慣的にネガティブな感情を受け入れている人の方が、大きなストレスを経験したばかりであっても、プレッシャーを感じない。また、幸福感も強いことがわかっているという。本書では、古今の『ビタースイート』な人々の様々な財産が紹介される。そうした財産をうまく生かすことで、あなたのやり方(創造のしかた、子育てのしかた、リーダーの務め方、愛し方、死に方)を改善することができる。本書を、あなたが自分自身を知り、他の人たちと理解しあうための一助にしていただきたい」とも書かれているのでした。
本書の「目次」は、以下のようになっています。
「読者にお伝えしていきたいこと」
序章 サラエボのチェリスト
はじめに「ビタースイート」の力
第1部「悲しみ」と「切なる思い」
第1章 「悲しみ」は何の役に立つのか?
第2章 私たちはなぜ「完全で無償の愛」を切望するのか?(そのことと、私たちが「悲しい歌」や「雨の日」、「神聖なもの」が大好きなこととは、どんな関係があるのか?)
第3章 「創造力」は「悲しみ」や「切なる思い」「超越する力」と関係があるのか?
第4章 愛を失ったときには、どうしたらいいのか?
第2部「勝者」と「敗者」
第5章 多大な「悲嘆」の上に成り立った国家が、どうやって「笑顔」が当たり前の文化を築いたのか?
第6章 職場などで「ポジティブ」を強要されるのを乗り越えるには、どうしたらいいのか?
第3部「人の死」と「命のはかなさ」
、「死別の悲しみ」
第7章 私たちは永遠に生きることを目指すべきか?
第8章 私たちは「死別の悲しみ」や「命のはかなさ」を吹っ切ろうとすべきなのか?
第9章 私たちは親や祖先の「苦痛」を受け継いでいるのだろうか? もしそうなら、何世代も前の苦痛を転換できるだろうか?
おわりに「心のふるさとに帰るには」
「謝辞」「備考」
「はじめに『ビタースイート』の力」では、今から2000年ほど前、古代ギリシャの哲学者アリストテレス(紀元前384~322年)が、「偉大な詩人や哲学者、芸術家、政治家たちがたいてい『憂うつ質(メランコリック)』なのはどうしてだろう」と疑問に思ったことが紹介されます。彼がそんな疑問を抱いた背景には、古代の人々の次のような考え方がありました。それは、人間の体には4つの体液(血液、粘液、黄色胆汁、黒色胆汁)が含まれていて、その4つそれぞれが、4種類の気質「多血質(陽気、楽天的)」、「粘液質(冷静)」、「胆汁質(攻撃的、積極的)」、「憂うつ質/黒胆汁質(悲観的)」を形成するという考え方です。そのころは、4つの体液のうち、どれの割合が多いかで性格が決まると考えられていました。有名な古代ギリシャの医師ヒポクラテス(紀元前460~370年ごろ)は、4種類の気質のバランスがとれているのが理想的な人間だと考えました。「とはいえ、わたしたちの多くは、どれか1つの気質が強く出る傾向がある」と、著者は述べています。
本書は「憂うつ質」について書かれており、この気質を著者は「ビタースイート」と呼んでいます。「ビタースイート」な人は、「切なる望み」や「心のうずき」、「悲しみ」を抱きやすく、時が過ぎゆくのを鋭く感じ取るといいます。そして、世の中の美しいものに接すると、心に妙に突き刺さるような喜びを覚えるとして、著者は「『ビタースイート』な人は、『明』と『暗』、『誕生』と『死』、――つまり『ビター』と『スイート』――は永久に対をなすことに気づいてもいる。アラブ社会のことわざ『ある日ははちみつ、ある日はたまねぎ(甘くて幸せな気分になるときもあれば、辛くてつらいときもある)』も、そのことを表している。人生の『悲劇』は、人生の『栄華』と切っても切れない関係にあるのだ」と述べます。
人は文明を破壊して、一から築き直すこともできるかもしれませんが、結局は同じ「二元性」が生まれるだろう、と著者は言います。しかし、そうした二元性には「明」もあれば「暗」もあることを十分に受け入れることが、逆説的ではありますが、二元性を超越する(乗り越える)唯一の方法なのだといいます。そして二元性を超越することがとても大事だと告白し、著者は「『ビタースイート』な人には、『魂の交わり』を望む気持ちや、安心できる『心のふるさと(心のわが家)』にかえりたいという気持ちもある」と述べます。そして、「苦痛」を「創造力」や「超越する力」、「愛」に転換するという考え方が、この本の核になっていることを訴えるのでした。
「ビタースイート」な人は、最悪の状態のときには、「完全で美しい世界なんて、永久に手が届かない」と絶望します。しかし、最高の状態のときには、そういう世界を生み出そうとするといいます。「ビタースイート」な人は、月ロケットや、傑作や名作、恋物語の隠れた「生みの親」なのだと指摘し、著者は「私たちがベートーベンの『月光』を弾いたり、火星に向かうロケットをつくったりするのは、『切なる思い』があるからだ。ロミオがジュリエットを愛したのも、シェークスピアが彼らの物語を書いたのも、それから何世紀も経っているのに、いまだにその戯曲が上演されているのも、『切なる思い』があるからなのだ」と述べています。
第1部「『悲しみ』と『切なる思い』」の第1章「『悲しみ』は何の役に立つのか?」では、ピクサー・アニメーション・スタジオの有名なアニメ監督ピート・ドクターの「インサイド・ヘッド」(2015年)の製作に協力したことで知られる1人の研究者が紹介されます。カリフォルニア大学バークレー校の心理学教授であるダッチャー・ケルトナーです。「インサイド・ヘッド」は一般に不要であると思われている「悲しみ(カナシミ)」が人間にとって欠かせない大切な感情であることを示した映画ですが、それはケルトナーの研究結果に基づくものでした。ケルトナーの研究については、彼の著書『Born to Be Good(生まれながらのいい人)』にまとめられていますが、研究の土台となっているものの1つは彼が「compassionate instinct(思いやりの本能)」と呼んでいる考え方です。それは、「人間は、お互いが抱えている困難を、気にかけるようつくられている」というものです。人間の神経システムは、自分の苦痛(痛み)と他人の苦痛(痛み)をほとんど区別しないことがわかっています。どちらに対しても同じような反応をするというわけです。
ケルトナーの言う「思いやりの本能」は、「食べたいという欲求」や「呼吸の本能」と同じくらい人間の大切な一部なのだといいます。「思いやりの本能」は、人のサクセスストーリーの土台にもなるし、ビタースイートタイプの素晴らしい力の1つでもあります。「compassion(思いやり)」という言葉は、字義的には「ともに苦しむ」という意味で、ケルトナーはそれを、人間の再考の資質であり、最も贖罪的な(罪を償う)資質だとみなしています。著者は、「思いやる気持ちは『悲しみ』から生まれるが、『悲しみ』というのは、向社会的な(他人を思いやり、他人に利益をもたらす)感情であり、人と人を繋げる手段、愛情を生み出す手段にもなる。こうした『悲しみ』を、ミュージシャンのニック・ケイブ(1957年~)は『どこにでもある、1つにまとめる力』と呼んでいる。『悲しみ』と『涙』は、私たちの最も強力な『人と人を結びつける手段』なのだ」と述べています。
「悲しみ」と「人と人を結びつけること」との関係を明らかにしたのは、ケルトナーの実験だけではありません。たとえば、ハーバード大学の心理学者ジョシュア・グリーン(1974年~)とプリンストン大学の心理学者で神経科学者でもあるジョナサン・コーエン(1955年~)の実験もそうです。彼らの実験参加者が「暴力の被害者たちの苦しみを思いやってほしい」と頼まれたときに活性化する脳の領域は、お母さんたちが可愛くてたまらない赤ちゃんを見つめたときに活性化すると以前の研究でわかっている領域と同じだと気づきました。また、エモリー大学の神経科学者ジェームズ・リリングとグレゴリー・バーンズは、生活に困っている人々を手助けしたときに活性化する脳の領域は、賞を取ったり、とてもおいしい料理を食べたりしたときに活性化する領域と同じだと気づきました。落ち込んでいる人(や、以前に落ち込んでいた人)は、相手の視点から世界を眺めたり、相手を思いやる気持ちを抱いたりする可能性が高いことや、共感力の高い人はほかの人たちに比べて、悲しい曲を楽しんでいる可能性が高いこともわかっているといいます。
タフツ大学の精神医学教授ナシア・ガミー(1966年~)は、「人が落ち込んでいるときには、生来の共感力が高まって、だれかれと、その人から逃れることができないような相互依存関係を築くものだ。(中略)そうした関係を築くことは、個人的な現実であって、非現実的な願望ではない」と述べています。これらの研究結果は大きな意味を持っています。なにしろ、「他人の悲しみに対処したい」という欲求が存在する領域は、呼吸や食物の消化、生殖、赤ちゃんの保護などの必要性に応える領域でもあり、報酬(ほうび)を得たいという願望や人生の喜びを味わいたいという願望が存在する領域でもあると教えているからです。また、ケルトナーは「人間というものの中心をなすのは、『気づかうこと』です。『悲しみ』というのは、気づかうためのものです。そして悲しみは、『思いやり』から生まれるものなんです」と著者に教えてくれたそうです。
人間の赤ちゃんは、ケルトナーの言う通り、「地球上の動物の中で、最も弱く」、善意ある大人たちの手助けが無ければ、生きていけません。人間がこうした弱い状態で生まれるのは、人間の大きな「脳」に対応するためだと指摘する著者は、「もし赤ちゃんの脳が完全に発達しきっていたら、大きすぎて産道を通らないのだ。とはいえ、人間が成熟する前に生まれてくるというのは、結局は、人間という種についてのもっと希望をもっていい事実の1つと言えそうだ。何しろ、どうしようもないほど自立できない人間の赤ちゃんの世話をするために、この種は知性を高め、それにつれて、共感力も高めてきたのだから。私たち人間は、赤ちゃんのわけのわからない泣き声を聞き分ける必要があった。そして、赤ちゃんに食べ物を与え、愛情を注ぐ必要があったのだ」と述べます。
もし、「思いやる気持ち」がわが子だけに向けられていたなら、共感力を高めてきたことに、それほど大きな意味はないかもしれません。しかしケルトナーによれば、人間は小さくてか弱い赤ちゃん全般を思いやれるように準備してきたので、赤ちゃんのような家にじっとしている人であれ、見知らぬ人であれ、窮地に陥って困っている他者をおもいやる能力も伸ばしてきたといいます。哺乳類のなかには、人間以外にも、他者を思いやる動物がいるそうです。シャチは、子どもを亡くした母親の周りをぐるぐる泳ぎ回るといいます。ゾウは、花を仲間のゾウたちの顔にそっと当てて、お互いに慰め合うといいます。でも、ケルトナーによれば、人間の場合は「まったく新しいレベルの『思いやり』が備わっています。人間の、困っている人や貧しい人たちに対する『悲しみ』や『思いやり』といった資質ほど素晴らしいものはない」のです。
チャールズ・ダーウィンはキャリアの初期に、10歳だった最愛の娘アニーを「しょう紅熱」で亡くしました。小児に多い発疹性伝染病です。その出来事が、彼の世界観を形づくったのかもしれないとして、著者は「ダーウィンの伝記を書いたデボラ・ハイリグマン(1958年~)やアダム・ゴプニク(1956年~)は推測している。ダーウィンは悲しみに打ちひしがれるあまり、アニーの埋葬式には参列できなかったという。彼は日記に、『アニーは、母親にくっついているのが大好きな陽気な子どもで、何時間もかけて父親の髪を整えてくれた』と優しく綴っている。アニーは、母親と離れなければならなくなると、こう叫んだという。『ああ、ママ。もしママが死んでしまったら、あたしたち、どうしたらいいの』。ところが、そうした悲劇に耐えなければならなかったのは、彼女の母親と父親、エマ&チャールズ・ダーウィンのほうだった。彼はアニーを亡くしたあと、日記にこう記している。『私たちは家庭を築く楽しみと、老後の慰めを失った』」と紹介します。
ダーウィンは、他者の苦しみに本能的に藩王している例を、次から次に挙げました。あるイヌは、一緒に飼われている病気のネコのそばを通るたびに、そのネコを気にかけ、なめてあげる。牛たちは、目の見えない年上の連れ合いに、根気よく食べ物を与えた。あるサルは命の危険を冒して、大好きな飼育係を非友好的なヒヒから守った。そして、ダーウィンは「私たちは、他人の苦しみを和らげずにはいられない。それは、他人の苦しみを和らげることで、自分につらい気持ちも同時に和らぐことになるからだ」と記しています。ケルトナーと同じように、ダーウィンも、他人の苦しみを和らげるといった習性が、親が持つ「わが子を大事に思う本能」から進化したものだと、直感的にわかっていたのでしょう。彼は、「母親や父親と接触しない動物には、『思いやり』は期待できない」とも語っています。
ダーウィンは、思いやる気持ちは、相手が家族の場合に最も強く、自分が属さない集団に対してはそれほどと強くないことや、思いやる気持ちがまったくない動物もよく見られること、人間がほかの種を、思いやるに値する「仲間」とみなすのはむずかしいことにも気づいていました。そして、わたしたちが「思いやりの本能」を発揮する相手を、家族から人間全体に、さらには生きとし生けるものへと可能な限り広げることが、人間に可能な最も気高い功徳の1つだと考えていたとして、著者は「実際、チベット仏教の最高指導者ダライ・ラマが、ダーウィンのこの考え方を耳にし、チベット仏教の考え方に似ていることに驚いたという。(ダライ・ラマは「これからは自分をダーウィニアン(ダーウィン説支持者)と呼ぼう」と語ったそうだ)。ダーウィンも仏教も、『思いやり』は最高の徳であり、母親と赤ちゃんとの結びつきが『思いやり』の中核になっていると考えている」と述べています。
「思いやり」は「悲しみ」を共有することで生まれるという、ビタースイートな見方ができます。それなのに、わたしたちは、「思いやり」を感情リストの「ポジティブ」欄のほうにいれることが多いと指摘し、著者は「実際、ケルトナーがライフワークにしている研究は、人を幸福にする方法を研究する心理学の一分野『ポジティブ心理学』が土台となっている。『ポジティブ心理学』という言葉は、1954年に心理学者アブラハム・マズロー(1908年~70年)が考案したものだ。その後、心理学者マーティン・セリグマン(1942年~)がポジティブ心理学を支持し、広めた。彼は、マズローと同様に、当時の心理学は『精神的な強み』よりも『精神疾患』を重視しすぎていると感じていたので、ポジティブ心理学を通じてそうした状況を打開したいと考えたのだ。彼らは、人々の心を浮き浮きさせ、人生を充実したものにするような手法や考え方を見つけようとした。それについては、セリグマンが大きな成功を収めている」と述べます。
ポジティブ心理学は最近になって、「ビタースイート」の研究にも取り組み始めているそうです。カナダのトロントにある「ミーニング・センタード・カウンセリング・インスティチュート」の所長ポール・ウォン博士や、イースト・ロンドン大学の講師ティム・ローマスなどの心理学者が、ポジティブ心理学ムーブメントの「第二波」が到来したことを、自らの言葉で証明しているのです。たとえば、ローマスは、「『ウェルビーイング(幸福/肉体的にも精神的にも社会的にも、すべてが満たされた状態にあること)』には、実際には、ポジティブなできごととネガティブなできごとのあいだの、捉えにくい、弁証法的な相互作用も含まれることに気づきました」と述べています。
また、認知心理学者のスコット・バリー・カウフマンは、大きな影響を与えた著書『Trancend(トランセンド/超越する)』を通じて、ポジティブ心理学についてのマズロー当初の考え方であるビタースイートタイプを「トランセンダー(超越する人)」と呼び、その存在を認める考え方を復活させています。カウフマンは、「トランセンダー、(従来の意味での)健全な人たちほど、“幸せ”ではない。トランセレンダーが、彼ら以上に、心から喜びを感じ、恍惚感を覚え、かなり高レベルの幸福感を覚えることもあるが、そうした感情と同じくらい―あるいは、そうした感情よりも多くの—ある種の果てしない『悲しみ』を覚える傾向があるのだ」と語っています。
 『礼を求めて』(三五館)
『礼を求めて』(三五館)
ケルトナーや、彼が共同で設立した「グレーター・グッド・サイエンス・センター」は、わたしたちが「悲しみ」を尊重できるようになるのに役立ちそうな手法を、数多く開発しています。重要な第一歩は「謙虚さ」を養うことだといいます。「謙虚さ」を身につけるには、(とくに、あなたが「自分は社会的にも経済的にも比較的恵まれた立場にある」と思っている場合は)どうしたらいいか。それは、「おじぎをする(頭を下げる)」という簡単な動作だといいます。著者は、「日本の人々は日々の人づき合いの中で、お辞儀をしているし、神を信じるたくさんの人たちが、頭を垂れて神に祈っている。ケルトナーによれば、この動作によって、実際に迷走神経が活性化されるそうだ」と述べます。これは「おじぎの科学」とうべきもので、「礼」を追求するわたしは非常に興味深く感じました。
 おじぎを科学する!
おじぎを科学する!
「おじぎの科学」を研究するケルトナーは、2016年のシリコンバレー(サンフランシスコ)での講演で「人々は、こうした敬意を示す動作に、心と体をつなぐ働きがあるのではないかと考え始めています」と語っています。著者は、「もちろん、信仰を持たない人や、服従を表明するのを不快に感じる人、その両方である人もたくさんいる。でも、私たちは、この動作を『服従』ではなく、『献身』とみなすこともできる。実際、ヨガにはおじぎを含む動作がよくあるが、私たちの多くがヨガを行っている。また私たちは、畏敬の念を抱かせるような芸術作品や大自然を目にすると、本能的に頭を下げている」と述べるのでした。
第2章「私たちはなぜ『完全で無償の愛』を切望するのか?(そのことと、私たちが「悲しい歌」や「雨の日」、「神聖なもの」が大好きなこととは、どんな関係があるのか?)」では、「ソウルメイト」に言及しています。著者は、「言うまでもなく、自分たちには『失った半分』などいない。ソウルメイト(魂の伴侶)なんてものはいないのだ。1人の人間が、自分のニーズをすべて満たすことなどできない。境界がなく、努力を要しない、永遠の『満足感』を望んだところで、失望するだけだ。そもそも、そんなものを望むなんて、神経症っぽいし、子供じみている。大人になったら、そんな望みはあきらめるべきだ」と述べています。「ソウルメイト」は、気の合う人、魂のつながりを感じる人などを意味しますが、前世からの縁がある人を意味することもあります。「ソウルメイト」のアイデアはプラトンの球体人間論(かつて両性具有の球体の人間がいたが、引き裂かれて男と女になったという説)に由来すると考えられています。
しかし、別の考え方が何世紀にもわたって存在しています。それは、「私たちが“完全な”愛を切に望むのは、正常で望ましいことだ」、「心から愛する人と一体化したいというのは、人間の心も最も奥深くにある願望ある」、「切に思うことが、いるべき所に到達するための道になる」といった考え方です。そして、こうした考え方は、恋愛だけについてのものではないとして、著者は「私たちは、ベートーベンの『歓喜の歌』を耳にしたときや、アフリカにある世界最大級の『ヴィクトリアの滝』を目にしたとき、礼拝用の敷物にひざまずいたときにも、同じような『切なる思い』に見舞われる。したがって、人生が変わるほどのカメラマンとの『4日間の恋』を描いた『マディソン郡の橋』のような作品に対しては、感傷的なナンセンス小説だと片づけるのではなく、そうした恋がほんとうはどういうものなのか、『歓喜の歌』や『ヴィクトリアの滝』、『祈り』と何ら変わりなく、同様の価値があるのではないかと考えてみることが、適切なのではないだろうか。『切に望む』というのは、クリエイティブでスピリチュアルな状態なのだ」と述べます。
 『結魂論〜なぜ人は結婚するのか』(成甲書房)
『結魂論〜なぜ人は結婚するのか』(成甲書房)
とはいえ、「完全な愛」を求めるべきだというプラトンの考え方を否定する議論は、根強く残っています。ちなみに、わたしは筋金入りのロマンティストですので、プラトンの球体人間論を信じています。それについては、拙著『結魂論〜なぜ人は結婚するのか』(成甲書房)で詳しく書きました。2016年には、スイス生まれの哲学者で、博学、多作の作家でもあるアラン・ド・ボトンが「ニューヨーク・タイムズ」紙で「なぜあなたは結婚する相手を間違えるのか?」というタイトルの記事を発表しました。そしてその年の署名記事の中で、最も多くの読者を獲得したのです。ド・ボトンはその記事で「私たちは、そして私たちの結婚は『自分のニーズをすべて満たし、自分の望みをすべて叶えてくれる完ぺきな人が存在する』という現実離れした考えを捨てたほうが、うまくいくはずだ」と主張しています。
著者は、人々に愛されている音楽ジャンルに「切なる思い」や「もの悲しい気持ち」をうまく利用しているものが非常に多いことを指摘します。ポルトガルの「ファド」(哀愁を帯びた民謡でギターの伴奏で歌われる)、スペインの「フラメンコ」(歌、踊り、ギター伴奏を主体とする芸能)、アルジェリアの「ライ」(イスラム道徳の建前をかなぐり捨てて、人間としての本音、苦しみ、悲しみ、愛欲をナマの言葉で表現した歌)、アイルランドの「ラメント(哀歌)」、アメリカの「ブルース」(アメリカに移住した黒人奴隷によって歌われた、生活苦や故郷への郷愁を主題とするワークソング)・・・。ポップミュージック(ポピュラー音楽)までもが、しだいに短調(マイナーキー)で書かれるようになっているといいます。心理学教授E・グレン・シェレンベルクと社会学者クリスチャン・フォン・シェープの調査によれば、1960年代には、ポップミュージック全体の中で短調の曲はわずか15%だったのに対し、今日では60%にのぼるといいます。
著者は、わたしたちの中には、「悲劇」や「雨の日」、「涙を誘う映画」が大好きな人がたくさんいることを指摘します。そして、わたしたちは「桜の花」を愛でることに注目し、「桜の開花を祝って、祝宴まで開いている。同じくらいきれいな花はいくらでもあるのに、桜の花が大好きなのだ。それは、桜の花が『短命』だからだ(日本の人々は、とりわけ桜が大好きで、その理由を『もののあわれ』のせいだとしている。『もののあわれ』とは、『ものごとに対する哀愁』と『命のはかなさを感じやすいこと』によって生まれる『おだやかな悲しみ』という望ましい精神状態)」と述べています。
哲学者たちはこうした現象を「悲劇のパラドックス」と呼び、これについて何世紀にもわたって頭を悩ませてきました。わたしたちがときどき「悲しみ」を歓迎し、それ以外のときには、どんなことをしてでも「悲しみ」を避けようとするのは、なぜなのか? 著者は、「今では心理学者や神経科学者たちも、こうした疑問について考えるようになり、さまざまな説を打ち出している。たとえばこんな調子だ。『月光』の曲には、喪失感を抱いたり、うつ状態に陥ったりしている人を癒す力があるのではないか。この曲は、私たちがネガティブな感情を、無視したり押さえつけたりせずに受け入れるのを助けるのではないか。この曲は、「悲しいのはあなただけじゃない」とおしえているのではないか・・・」と述べます。
もう1つの理由は、アリストテレスの時代から、長年にわたって言われてきた「カタルシス(精神の浄化)」が得られることです。たぶん、古代ギリシャの人々は、アテネの舞台でオイディプス王が自分の目をえぐり取るのを見たことで、自分の感情のもつれを解き放てるようになったのではないだろうかとして、著者は「もっと最近の例を挙げよう。神経科学者のマシュー・サックスとアントニオ・ダマシオ、心理学者のアサル・ハビオは、『悲しい曲』についての研究文献全体を見直し、『切ないメロディー』は、人間故体がホメオスタシス(恒常性)――さまざまな感情や生理機能が最適な範囲内で働いている状態――を保つのに役立つのではないかと考えた。また、いくつかの調査によれば集中治療室に入院している赤ちゃんのうち、子守歌(たいていは悲しげな歌)を聞いた赤ちゃんたちは、別の種類の曲を聴いた赤ちゃんたちに比べて、呼吸や食事のとり方、心拍などが力強かったという!」と述べています。
実際のところ、私たちは「悲劇」そのものを歓迎しているわけではありません。わたしたちが好きなのは、悲しく、なおかつ美しいもの。つまり、ビターでありながらスイートなものなのだと指摘し、著者は「たとえば、私たちは『悲しい言葉』のリストとか、『悲しい顔』のスライドショーをみても感動しない。(こうしたことは、研究者たちによって実証済みだ)。私たちが好きなのは、哀愁に満ちた詩とか、霧に包まれた海辺の町、雲まで届きそうな尖塔といったものだ。言い換えれば、私たちは、『結びつくことへの切なる思い』や『もっと完全で美しい世界への切なる思い』が現れている芸術的な形態を好むのだ。私たちは、『月光』の曲が表現する『悲しみに』奇妙な感動を覚える。その時私たちがかんじているには、『愛への切なる想い』――壊れやすい愛、いつしか消える愛、つかの間の愛、枠を超越した愛への、切なる思い――ではないだろうか」と述べます。
「切なる思い」は、究極の「ミューズ(詩や音楽の女神)」にもなっています。シンガーソングライターで詩人でもあるニック・ケイヴは、「俺の芸術家人生の中心にあるのは、俺の骨で口笛を吹き、俺の血の中でハミングしている『喪失感』や『切なる思い』といった感情をはっきり表現したいという『願望』、もっと正確に言えば『ニーズ(欲求)』なんだ」と語っています。ジャズ歌手でピアニストのニーナ・シモンは、「ハイ・プリーステス・オブ・ソウル(魂の女性指導者)」と呼ばれています。「ハイ・プリーステス・オブ・ソウル(High priestess of Soul)」は彼女のアルバムのタイトルでもあります。それは彼女の曲が、正義や愛への「切ある思い」に満ちていたからだといいます。
スペインの人々はそれを「duende ドゥエンデ(小悪魔、妖精、抗しがたい魅力)」と呼んでいます。スペインのフラメンコダンスなど、かき立てられた心を表す芸術形態の中心にあるのは、燃え立つような「ドゥエンデ」なのです。また、ポルトガル語を話す人々には、「saudade サウダージ」という概念があります。これは、心を優しく突き刺すようなノスタルジア(懐古の情、懐かしむ気持ち)のことで、音楽では、とても大切にしていたのにとうの昔になくなってしまったもの、そもそも存在しなかったかもしれないものへのノスタルジアとして表現されることが多いです。ヒンドゥー教の世界では「viraha ヴィラハ」――別離(たいていは愛する人との別れ)のつらさ――が、詩や音楽を生み出す源だと言われています。
著者によれば、「短調の曲」というのは、わたしたちが「切に望んでいるもの(こと)」を表現したものの1つなのだといいます。では、「切に望んでいるもの(こと)」とは何でしょうか? わたしたちは「二分の一」と言ったり、「0.5」、「半分」と言ったりしますが、どれも同じものを表現しているといいます。では、「同じもの」とは何でしょうか? 著者は、「分数や小数、語句は、何らかの数学的概念の本質を表現し、その本質は、私たちが言葉で表現したあとも変わらない。私たちが花瓶に挿す花の1本1本、私たちが美術館に飾る絵画の一枚一枚、新たに掘られ、私たちが涙を見せる墓の1つ1つが、同じもの、言い表しにくいながらも驚くべきものを表現しているのではないだろうか」と述べます。
恋愛の最もわかりにくい側面はわかっています。それは、長続きする恋愛は、自分の「切なる望み」がやっと叶ったという確信からスタートするということです。スタート時点で、仕事はもう済んだ、夢が実現した、自分の恋愛対象の中に「完全で美しい世界」が体現されていると確信するのだとして、著者は「でもそれは、求愛の段階であり、理想化の段階であり、ある特定のすごくいい時期のあいだ、あの別世界に到達して、あなたとパートナーが一体化する段階なのだ。この段階では、精神的な愛と、性的な愛の区別がほとんどない。多くのポップ・ソングが初めて性的関係持ったときのことを歌っているのは、それが理由だ。とはいえ、そうした曲は、ただ性的な愛を歌ったとして聴くのではなく、超越したいという『切なる思い』を歌った曲として聴いたほうがいいだろう」と述べています。
あなたが「無神論者」や「不可知論者」なら、「神を愛する」といった話題には、抵抗を覚えたり、イライラしたりするのではないだろうかと問う著者は、「あなたが、『信心深い方』なら、『神を欲する』には、当たり前のことに思えるかもしれない。あるいは、あなたは両者の間のどこかにいるのかもしれない。C.S.ルイスは、つねに『ビタースイート』な存在が自分を呼ぶ声が聞こえ、30代のころには、キリスト教の熱心な信奉者となっていたが、最終的には、次のような結論に達している。—私たちが空腹を覚えるのは、食べ物を食べる必要があるからで、私たちがのどの渇きを覚えるのは、飲みものを飲む必要があるからだ。だから、もし私たちが、この世界で満たすことのできないような『慰めようもないほどの切なる思い』を覚えたなら、それは私たちがもう1つの神聖な世界の一員だからにちがいない」と述べるのでした。
第3章「『創造力』は『悲しみ』や『切なる思い』、『超越する力』と関係があるのか?」では、世界的に偶像視された、詩人にしてミュージシャンのレナード・コーエンが取り上げられます。1944年、彼は9歳のときに父親を亡くしました。彼は哀悼の詩を書き、父親のお気に入りの蝶ネクタイ切り開き、その中に詩を書いた紙を入れ、モントリオールある自宅の庭に埋めました。それが、彼の最初の「芸術的な表現行為」だったのです。その後、60年にわたるキャリア(のちにグラミー賞の特別功労賞「生涯業績賞」を受賞したキャリア)の中で、そうした表現行為を何度も繰り返し「心の痛み」や「切なる思い」、「恋」をうたった何百もの詩を書き残すことになるのでした。
「創造力」は、何らかの謎の力を通じて、「悲しみ」や「切なる思い」と関係しているのか? この問いは長いあいだ、「創造力」の研究者からも、ただの観察者からも提起されてきました。そしてデータは、その問いの答えが「イエス」であること(それに、アリストテレスの直感――芸術分野で「憂うつ質」の人が目立つのはなぜかという疑問を通じての直感――が正しかったこと)を示しています。心理学者マーゼン・アイゼンシュタット(1936年~)は、創造的な分野の第一人者573人を対象として行った初期の有名な調査では、「創造力がとても高い人々」の中で、コーエンのように、子どものころに親を亡くしている人の割合が驚くほど高かったそうです。25%の人が、10歳までに、親の少なくとも1人を亡くしていました。「15歳まで」となると、その割合は35%に達し、「20歳まで」となると、なんと45%に達しています。また、別のいくつかの調査で、創造力のある人々は、親がかなりの高齢になるまで存命していた場合でも、「悲しみ」を抱くことがかなり多いことがわかっています。
何世代か前のフロイト派の心理学者たちは、「oceanic feeling(海洋的感情)」(ヤーデンの言う「自己超越の体験」)を、神経症のサインとみなしていました。「oceanic feeling」というのはフランスの作家ロマン・ロラン(1866~1944年)がフロイトへの手紙の中で使った言葉で「永遠の感覚」や「自分がまわりの世界全体一体となっている」という感覚を表しています。しかしハイトとヤーデンは、実際には、フロイト派の見方とはまったく逆であることに気がついたといいます。「自己超越の体験」をした人たちは、他の人たちより、自尊心(自己肯定感)が高く、向社会的(社会性のある)行動をとり、「人生には意義がある」という意識が高く、落ち込んでいる人の割合が低く、人生満足度や幸福感が高く、死に対する恐怖心が少なく、全体的に「心」が健康であることがわかったといいます。ハイトとヤーデンは、「自己超越の体験」は、「人生の中でもとくにポジティブで有意義なひとときになる」と結論づけ、1世紀前にウィリアム・ジェイムスが推測した通り、その体験が「私たちの最高のやすらぎ」につながることを確認したのでした。
19世紀半ばに、「人間性心理学」を生み出した偉大な心理学者アブラハム・マズローは、心臓病で死に瀕していた時期に、強烈な「ピーク・エクスペリエンス」を得ることがそれまで以上に頻繁になったといいます。2017年には、ノースカロライナ大学の心理学者アメリア・ゴランソンをリーダーとする研究者グループが、調査の参加者たちに、死ぬときはどんな気持ちになるか、想像するように依頼したところ、ほとんどの参加者が「悲しみ」や「恐怖」、「不安」といった感情を想像したといいます。ところが、研究者グループが、末期の患者や死刑囚を調査したところ、そうした実際に死に直面している人々は、「人生の意義」、「人とのつながり」、「愛」について語る人のほうが多かったのでした。研究者たちが結論づけた通り、「死神との出会いは、傍から見るほど恐ろしくはない」のでした。
ヤーデンの調査結果は、人生の節目を「スピリチュアルな気づきや、創造力の目覚め」への入り口として大事にするという、数多くの社会の考え方と一致しています。エステル・フランケルが名著『Sacred Therapy(神聖な心理療法)』の中で検証している通り、そうした考え方をしているからこそ、たくさんの社会が、宗教的な背景のなかで、成人の儀式(「初聖体拝領式」や、「バル・ミツバ」など)を執り行い、そうしたセレモニーの多くが、子ども時代の「死」と大人時代の「誕生」に関係しているのだといいます。ちなみに、「初聖体拝領式」は、キリスト教徒の子どもが7歳ごろに行う正式なキリスト教徒となるための儀式です。「バル・ミツバ」は、ユダヤ教の男子が、13歳のときに行う成人式です。中には、子どもが一時的に土中に埋められ、大人として掘り出される式を行っている地域もあるといいます。
また、子どもがタトゥーを入れられたり、ひどい傷を負わされたり、それ以外の、子ども時代の終わりと、新たな大人の誕生を告げる印をつけられたりする地域もあるそうです。そうしたことが、物理的に切り離されたスペース、たとえば、儀式用の小屋や池、教会やシナゴーグなどで行われる地域もあります。そうした儀式の本質は、Xは必ずYに移行する必要があり、そのプロセスには「犠牲」と「再生(究極の創造)」が含まれていること、そしてそのプロセスは「精神的高揚」の場となることだと言えるでしょう。イエス・キリストの誕生、十字架上での犠牲、その後の再生(復活)という、キリスト教における一連のできごとも、同様のストーリーを示しています。(「sacrifice」の語源はラテン語の「sacer ficere」で、このラテン語は「(人を)神聖な状態にする」という意味だそうです。
第4章「愛を失ったときには、どうしたらいいのか?」では、ネバダ大学の臨床心理学者であるスティーブン・ヘイズと仲間たちが、喪失に対処するために「7つのスキル」にまとめたことが紹介されます。彼らは、35年にわたって1000回以上の実験を行う中で、この「7つのスキル」を備えることができるかどうかで、喪失に直面した人が「不安」や「うつ状態」、「トラウマ(心の傷)」、「薬物乱用」などに陥るかどうか、喪失に強いかどうかを予測できることに気づきました。最初の5つのスキルは、「ビターなものを受け入れること」に関係しています。
1つ目のスキルは、「喪失は事実である」と認めること。わたしたちはまずは、それを認める必要があるのです。2つ目は、喪失に伴う感情を受け入れること。わたしたちは「苦痛」をコントロールしようとしたり、食べものやお酒、仕事などで紛らわせようとしたりしないで、「心の傷」や「悲しみ」、「精神的打撃」、「怒り」などをただ感じる方がいいのです。3つ目は、自分の感情、考え、記憶をすべて受け入れること。たとえ予想外のことであっても、一見、不適切に見えるものであっても、すべて受け入れる必要があります。4つ目は、ときには、わたしたちが「自分はもういっぱいいっぱい」と感じることもあると予測しておくこと。そして5つ目は、役に立たない考えを抱かないよう気をつけること。たとえば、「わたしは、これを終わらせるべきだった」とか、「すべて、わたしのせいだ」、「世の中、不公平だ」といった考えには気をつけたほうがいいそうです。
しかしながら、わたしたちの目を「ビター」から「スイート」へ、「喪失」から「愛」へと移してくれるのは、「7つのスキル」の残りの2つ、すなわち、「大事なものにつながること」と「価値観にもとづいた行動を取ること」です。「大事なものとつながる」というのは、喪失の「苦痛」は、あなたが、自分にとって最も大事な人や最も大事な原則、あらには人生の意義に目を向けるのに役立つと気づいていることです。「価値観にもとづいた行動を取る」というのは、そうした「大事なもの」にもとづいて行動することです。ヘイズは、「あなたの喪失が、最も有意義なものに気づき、ひいては人生を価値あるものにする機会になることもあります」と記しています。
大事なものにつながったり、それにもとづいて行動したりするスキルは、さまざまな形で見られます。建築家でエンジニアのバックミンスター・フラー(1895~1983年)は、事業に失敗し、さらに1922年に4歳の娘が髄膜炎で亡くなったことで、ひどく落ち込み、自殺まで考えました。でも彼は、「もう生きていてもしかたない」という思いをひるがえし、「人生を価値あるものにするのは、いったい何だろう?人類に利益をもたらすために、ひとりの人間ができることは何だろう?」と考えました。そして、それは、たくさんあることがわかったのです。フラーは、ジオデシック・ドームをはじめ、さまざまなもののデザインを考案し、「20世紀のレオナルド・ダ・ビンチ」として知られるようになりました。
著者は、「慈愛の瞑想(loving-kindness meditation)」を紹介します。パーリ語では「metta(メッタ)」と呼ばれていますが、他人の幸福を祈る瞑想法です。「バーリ語」は、古代インドの言葉で釈迦が亡くなったのち、その教えをまとめるために用いられ、聖典用語として定着しました。「metta」は、生きとし生けるものに深い友愛の心、慈しみの心を持つことです。古くから仏教徒の修行に使われてきた「メッター」には、多くのメリット、例えば「畏敬」、「喜び」、「感謝」などの感情を高める、片頭痛や慢性的な痛み、心の傷などを和らげるといったメリットがあります。この瞑想は、心が「喪失感」に代わって「愛」で満たされるようにするための、昔から続いている方法でもあるといいます。著者は、「もしあなたが『大切な愛』を失った、あるいは、自分にとってとても大事なものは『愛』だと思っているなら、『メッター』を通じて―アクセプタンス&コミットメント・セラピーの言葉を借りるなら、『価値観にもとづいた行動を取ること』や、『大事なもの(こと)につながること』ができる」と述べます。
 『慈経 自由訳』(現代書林)
『慈経 自由訳』(現代書林)
慈愛の瞑想をパーリ語で「metta(メッタ)」と呼ぶと言いましたが、わたしが自由訳を試みた「慈経」(メッタ・スッタ)というお経があります。仏教の開祖であるブッダの本心が最もシンプルに、そしてダイレクトに語られている、最古にして最重要であるお経です。上座部仏教の根本経典であり、大乗仏教における「般若心経」にも比肩します。上座部仏教はかつて、「小乗仏教」などと蔑称された時期がありました。しかし、僧侶たちはブッダの教えを忠実に守り、厳しい修行に明け暮れてきました。「メッタ」は、怒りのない状態を示し、つまるところ「慈しみ」という意味になります。「スッタ」は、「たていと」「経」を表します。興味深いことに、ブッダは満月の夜に「慈経」を説いたと伝えられています。満月とは、満たされた心のシンボルにほかなりません。
じつは「慈経」そのものが月光のメッセージです。わたしは、ドビュッシーの「月の光」を聴きながら自由訳を試みました。わたしは、「慈悲の徳」を説く仏教の思想、つまりブッダの考え方が世界を救うと信じています。「ブッダの慈しみは、愛をも超える」と言った人がいましたが、仏教における「慈」の心は人間のみならず、あらゆる生きとし生けるものへと注がれます。生命のつながりを洞察したブッダは、人間が浄らかな高い心を得るために、すべての生命の安楽を念じる「慈しみ」の心を最重視しました。そして、すべての人にある「慈しみ」の心を育てるために「慈経」のメッセージを残しました。そこには、「すべての生きとし生けるものは、すこやかであり、危険がなく、心安らかに幸せでありますように」と念じるブッダの願いが満ちています。
フランツ・カフカ(1883~1924年)は、20世紀のヨーロッパの偉大な小説家の1人です。しかし彼には、小説家としてのものとは別の物語があるとして、著者は「それはカフカについての物語だが、彼が書いたものではなく、スペインの作家ジョルディ・シエラ・イ・ファブラ(1947年~)が書いたものだ。その物語は、カフカが死の直前にベルリンで一緒に暮らしたドーラ・ディアマントという女性の回想録にもとづいている。物語は次のようなものだ。カフカが公園を散歩していると、お気に入りの人形を失くしたばかりで、涙ぐんでいる少女に出会った」と紹介しています。
カフカは人形を探すのを手伝いましたが、見つかりませんでした。そこで、少女に「お人形さんはきっと、旅に出たんだよ。僕が、お人形さんの郵便配達人になって、お人形さんからの言葉をきみに届けよう」と言いました。その翌日、彼は少女に手紙を渡しました。手紙は前日の夜に、彼が書いたものでした。人形は手紙で、「悲しまないでくださいね。わたしは世界をみるために旅に出ています。わたしの冒険について、手紙に書きますね」と書かれていました。それ以後、カフカは「わたし(人形)は学校に入って、ワクワクするような人たちと出会っています。新しい生活を始めたので、帰ることは出来ませんが、あなた(少女)のことが大好きですし、これからもずっと大好きです」といった内容の手紙を少女に渡し続けました。
カフカは、少女と最後に会ったときに、人形を1つ手渡し、それに手紙も添えました。彼はその人形が、少女が失くしたものと同じに見えないことは百も承知だったので、手紙には「わたし、旅をしたことで、変わったんです」と書かれていました。少女はその贈り物を、その後ずっと大事にしました。そして数十年後、その代用の人形に、見落としていた割れ目があり、その中に、もう1つの手紙が詰め込まれていることに気づきました。その手紙には、「きみは、いずれは大好きなものをすべて失うことになるでしょう。でもね、結局のところ、『大好きなもの』は別の形になって戻ってくるんです」と書かれていました。
第5章「多大な『悲嘆』の上に成り立った国家が、どうやって『笑顔』が当たり前の文化を築いたのか?」では、わたしが唱える「リメンバー・フェス」を連想させる記述があります。著者は、アメリカの文化的な祝祭、たとえば7月4日の独立記念日、ニューイヤーズイブ(大みそか)、各人の誕生祝いなどは、誕生を祝うもので、わたしたちが「命のはかなさ」や「悲しみ」とともに生きるのに役立つものではないといいます。メキシコの人々は「死者の日」に、この世を去った先祖を讃えますが、アメリカ人はそういうことはしません。チベット僧は、夜になると自分の水のみコップを伏せます。それは、自分は朝に死んでいる可能性があるのだと覚えておくためだそうですが、わたしたちアメリカ人はそういうことはしません。日本の人々は稲荷山(伏見稲荷大社がある)で、自分の願いを板に書き込み、それを風雨に晒しておきますが、アメリカ人はそういうことはしません。
また、アメリカのナホバ族の人々は「不完全さ」をラグに織り込み、日本の人々はそれを陶器に焼きこんで「わび・さび」を表現しますが、アメリカ人はそういうことはしません。心理学者のバーギット・クープマン=ホルムと、ジーン・ツァイの調査によれば、アメリカ人は「お悔み状」の中でさえ、深く悲しむ権利を否定するといいます。ドイツ人が「お悔み状」を送るときには、黒のモノトーンで描かれたカードを使い、「深い悲しみの中で~」、「どんな言葉も、重い心を軽くすることはないでしょうが~」といった言葉を書きますが、それとは対照的に、アメリカ人はカラフルなカードを使い、「愛は生き続ける」、「思い出がやすらぎをもたらすことになるでしょう」といった、幸せな気分にさせる言葉を並べるといいます。そして、著者は「キリストは十字架上で死んだのに、私たちアメリカ人は、キリストの誕生と復活に目を向ける」と書くのでした。
アメリカに「“ポジティブ”という絶対権力」が生まれたのは、1つには、アメリカの歴史的ルーツが正しく認識されなかったからだろうと推測し、著者は「最初のメジャーなアメリカ文化は、ニューイングランド地方に到着した白人入植者によって築かれ、『カルヴァン主義』を反映したものだった」と述べます。カルヴァン主義は、宗教改革の指導者ジャン・カルヴァン(1509~64年)の主張にもとづく、キリスト教プロテスタントの教義です。カルヴァンは禁欲や「予定説」を説いた他、蓄財を認めて商工業者の心をつかみました。カルヴァン主義では、「天国」は存在しますが、そこに行けると運命づけられた人のためだけに存在すると考えます。「地獄」はゾッとするような場所とされ。「地獄」を描写する文章がたくさんあります。そうした文章のせいで、子どもたちはしょっちゅう悪夢を見るようになったといいます。
第6章「職場などで『ポジティブ』を強要されるのを乗り越えるには、どうしたらいいのか?」では、スーザン・デイビットという女性が紹介されます。国際連合、グーグル、アーンスト・アンド・ヤングといったクライエントたちに、「エモーショナル・アジリティ(感情の敏捷性)」について教えている人物です。「エモーショナル・アジリティ」というのは、彼女の定義によれば、「つらい感情に見舞われたりいやな思いをしたりしても、ゆったり構え、そうした感情や思いに勇気と思いやりを持って向き合ってから、そうした感情や思いを断ち切って、人生を改善できるようにする」というプロセスのことだそうです。
組織心理学者のピーター・フロストは、「もし仏陀が語ったとされている通り、『“苦しみ”は自由に選択でいるものだが、人間であるためには避けられないもの』だとしたら、“苦しみ”は、組織の中でやっていくうえで重要なものだと気づくべきだ。我々は、そのことを何らかの形で理論に反映させるべきだろう」と語っています。こうした考え方に触発された何人かの組織心理学者が、フロストと、ミシガン大学の組織心理学者ジェーン・ダットンをリーダーに据え、「組織を『思いやり』を表現するための場所と捉える新しい視点」を発展させることに専門的に取り組む研究グループを設立しました。彼らはこのグループを「CompassionLab(コンパッションラボ)」と名付けました。
コンパッションラボは、今ではミシガン大学の研究者モニカ・ウォーリンによって運営されています。ウォーリンは、ダットンとの共著で、職場での思いやりについての貴重な本も書いています。経営学教授のジェイソン・カノフとローラ・マッデンというコンパッションラボの2人のメンバーが、カノフが以前に「周囲からの孤立」についての研究用に行った労働者への聞き取り調査の報告書を綿密にチェックしました。その結果、2つのことがわかりました。1つ目は、報告書には、パニック発作に見舞われたとか、人間関係がうまくいかない、自分は低く評価されていると感じているといった、職場での「苦痛や苦しみ」の物語が多く記されていたこと。2つ目は、調査に参加した労働者たちは、自分の物語を伝えるのに「苦痛」とか「苦しみ」といった言葉はほとんど使わなかったことです。
リーダーがどんな感情を見せるかが、リーダーがどのくらいパワフルに見えるかに影響することに、研究者たちはだいぶ前から気づいていました。困った状況に陥ったときに、怒っているように振る舞うリーダーは、たいていの場合、悲しげに振る舞うリーダーよりもパワフルだとみなされるとして、著者は「実際、私が『ビタースイート』タイプの有名なリーダーを探してみたところ、クリエイティブな世界の大物なら簡単に見つかったが、ビジネス界のリーダーはなかなか見つからなかった。それは、『憂うつ質』のリーダーがあまりいないからでなく、『憂うつ質』のリーダーは自分が『憂うつ質』であることを公に認めていないからではないだろうか。とはいえ、経営学教授のホアン・マデラとD・ブレント・スミスが2009年に行った実験で、リーダーは『怒り』よりも『悲しみ』を見せたほうが、いい結果――たとえば、部下たちとの関係を強化できた、有能であるという評価が高まった、など――につながることがわかっている」と述べています。
憂うつ質のリーダーは特殊な力を備えている可能性があるといいます。場合によっては、リーダーが怒りを見せたほうがうまくいくときもあるだろうとして、著者は「たとえば、外部からの脅威に直面するという緊急事態が発生したときだ。だが、製品をリコールしたことで、顧客に迷惑をかけたときなど、『ビタースイート』な振る舞いのほうが適切な場合もあるだろう。(実際、マデラとスミスが2009年に、そうした状況で実験したところ、「怒り」と「悲しみ」が入り混じったリーダーが、最もいい結果をだすことが判明した)。シュヴァルツミュラーは、メディア企業Ozy社のデジタル雑誌でこう語っている。『部下たちが大事なプロジェクトを駄目にしてしまったときは、「こんなことになって私は怒っている」と言うのではなく、「こんなことになって私は悲しい」といったほうがいいでしょう。あなたが「個人の力」を発揮することで、部下たちは、「自分はあなたのことが好きだから、あなたと共有する目標を達成するために、あなたの役に立ちたい」という気になるのです』」と紹介しています。
はたして、「“ポジティブ”という絶対権力」を暗黙のうちに乗り越えられる職場文化など、築けるものか? わたしたちは職場文化に、「人間にとって、悲しみは避けられないもの」という考え方を織り込み、悲しみを抱えている人に「思いやりを持って対応することが大事だ」という考え方を植えつけられるものか? 2011年に、コンパッションラボの何人かの研究者たちが、1つの素晴らしい組織(ミシガン州ジャクソンの貧しい地区にある地域住民無化の病院の「治療費請求課」)についての研究論文を発表しています。この部署で働く職員たちは、病人たちから未払いの治療費を取り立てるという憂うつな仕事を抱えていました。
「この仕事以上にやる気の出ない仕事は、なかなか思いつかない」といった仕事なので、この職種は、離職率が高いという問題も抱えていました。ところが「ミッドウエスト・ビリング」の名で知られている課は、個人的な悩みを抱えることは、すべての職員にとって当たり前のことだと考える文化を築いていたのです。個人的な悩みを抱えることは、職員の「自分には価値がある」という意識に悪影響を及ぼすどころか、課の職員たちがお互いに思いやりを示すいい機会になっていました。職員の誰かが母親を亡くしたときや、離婚したとき、家庭内暴力を受けたときなどは、いつも周りの職員たちがその職員を思いやりました。職員の誰かが風邪をひいたときでさえ、ミッドウエスト・ビリング課の職員たちは互いに助け合ったのです。
悩みや苦しみを分かち合うことは、精神面での健康にいいだけではなく、ビジネス面にも役立つといいます。ミッドウエスト・ビリング課は、研究の対象となった年までの5年間で、治療費を取り立てる速さがそれ以前の5倍になり、その速さは業界標準を上回っていたといいます。離職率もわずか2%で、ミッドウエストの医療機関の離職率の平均「25%」や、治療費請求業界の非常に高い離職率に比べたら、かなり低く抑えられています。スーザン・デイビッドは著者に「企業は、たいていの場合、安全で、革新的、協調的、開放的な組織になろうとするでしょ。でも、『安全』は『恐怖』と背中合わせだし、『イノベーション(革新)』は『失敗』と背中合わせ、『協調』は『対立』と背中合わせなの。そういう企業の業績は、ビタースイートな人たちをどのくらい受け入れるかできまると思うわ」と語ったそうです。わが社は「コンパッショナリー・カンパニー」を目指しているのですが、そのヒントを与えられました。
第3部「『人の死』と『命のはかなさ』、『死別の悲しみ』」では、「私たちは『死別の悲しみ』や『命のはかなさ』を吹っ切ろうとすべきなのか?」では、小林一茶の「露の世は 露の世ながら さりながら」という俳句を取り上げて、著者は「私たちは、自分も愛している人たちも、みんな死ぬと知りながら、どのように生きていけばいいのだろうか? 私には、一茶は、彼独自のビタースイートな答えを提供しているように思える。彼はこの詩を通じて、『「命のはかなさ」を受け入れる必要はありません』と私たちに伝えているのではないだろうか。『「命ははかない」とわかっていて、それによる、刺すような痛みを感じているなら、それで十分です』と伝えているのではないだろうか。そして結局のところ、その『痛み』が私たちみんなを結びつけるのではないだろうか」と述べています。わたしの唱える「悲縁」に通じる考えであると思いました。

『愛する人を亡くした人へ』
(現代書林)
そして、死別の悲嘆について、著者は「みなさんは、愛する人を亡くすと、長いことつらい思いをし、そのあと、苦労しながらゆっくりと回復するのが、残された人がたどる一般的な道だと思っているのではないでしょうか。ですが実際のところは、それほど単純ではありません。人は娘を亡くした次の日に、ジョークを聞いて笑うこともあれば、50年後に、娘のことを思い出してむせび泣くこともあるのです」と述べるのでした。大切な人を亡くした直後は、強烈な幸福感と強烈な悲しみのあいだをいったり来たりすることがよくあるというのです。この発言は、グリーフケアの研究と実践に励んでいるわたしにとって、大きなヒントを与えてくれました。本書は、訳文が硬すぎる(どちらかというと、これは下訳ですね)という欠点に目をつぶれば、「悲しみ」という感情について深く考察した素晴らしい本でした。これから、何度も読み返したいです。
2023年12月9日 一条真也拝




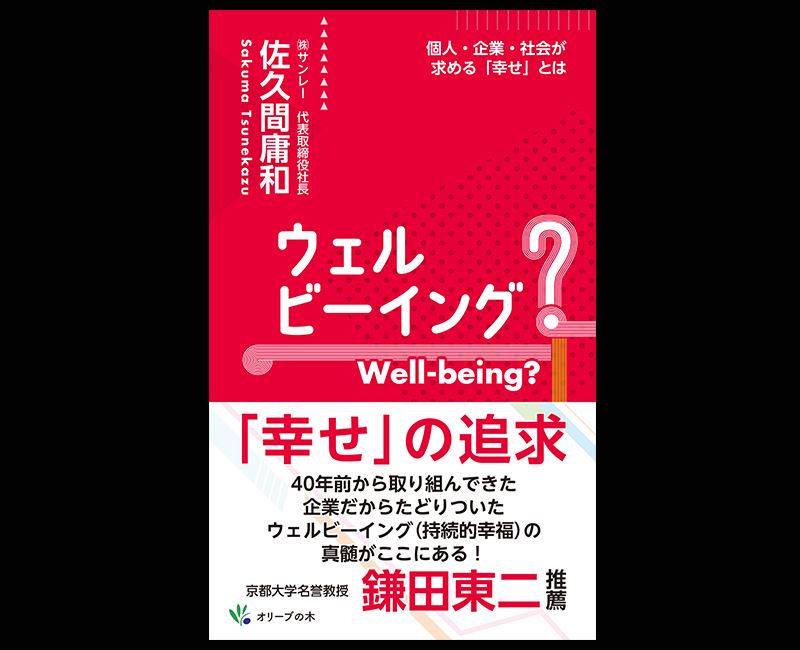 『
『

 『
『