
一条真也です。
「嵐」の櫻井翔と相葉雅紀が、それぞれ一般人女性との入籍を電撃発表しました。国民的グループの5人のメンバーのうち2人が揃って結婚をファンに報告するという、日本アイドル史上例を見ないビッグニュースです。
『ニッポン男性アイドル史』太田省一著(青弓社)を紹介します。「一九六〇-二〇一〇年代」のサブタイトルがついています。著者は1960年生まれ。社会学者、文筆家。東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得満期退学。テレビと戦後日本の関係が研究および著述のメインテーマ。それを踏まえ、現在はテレビ番組の歴史、お笑い、アイドル、ネット動画などメディアと文化に関わる諸事象について執筆活動を続けています。著書にブログ『SMAPと平成ニッポン』で紹介した本をはじめ、『中居正広という生き方』(青弓社)、『木村拓哉という生き方』(青弓社)、 『紅白歌合戦と日本人』(筑摩書房)など。

本書のカバー表紙の下部
本書のカバー表紙には、日本芸能史を飾って来た男性アイドルたちのイラストとともに、「男性アイドルとして存在感を放つジャニーズを軸に、歌手だけでなく、俳優、バンド、ダンスグループのアイドル的な側面にも光を当てる。未完成の存在であるがゆえの成長する魅力で私たちを引き付けてやまない男性アイドルの歴史を、戦後の日本社会やメディア文化との関係から描き出す」と書かれています。
アマゾンの「内容紹介」には、「1960年代のグループサウンズとジャニーズのライバル関係に始まり、70年代の新御三家、学園ドラマの俳優、80年代のたのきんトリオ、チェッカーズなど、多岐にわたる男性アイドルの足跡を、『王子様』『不良』『普通の男の子』というキーワードをもとにたどる。さらに、アイドルの定義を変えたSMAP、国民的アイドルになった嵐、その一方で独自のスタイルを構築したDA PUMPやEXILE、菅田将暉ら特撮ドラマ出身の俳優、K-POPアーティストなど90年代から現在に至る多彩な男性アイドルの魅力と特質を明らかにする。またテレビ、映画、舞台、SNSや『YouTube』などアイドルの多メディア展開も射程に収め、未完成の存在であるがゆえの成長する魅力で私たちを引き付けてやまない男性アイドルの歴史を、日本社会やメディア文化との関係から描き出す」と書かれています。
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
序章 男性アイドルは、どのように変わって来たか
第1章 GSとジャニーズ
――1960年代、男性アイドルの幕開け
第2章 「新御三家」の時代
――1970年代の本格的な拡大
第3章 学園ドラマと「ロック御三家」
――1970年代の多様化
第4章 ジャニーズの復活とロックィドルの人気
――1980年代の全盛期
第5章 SMAPとダンスアイドルの台頭
――1990年代の新たな男性アイドル像
第6章 嵐の登場と「ジャニーズ1強時代」の意味
――2000年代以降の「国民的アイドル」のかたち
第7章 ジャニーズのネット進出、
菅田将暉とBTSが示すもの
――2010年代という新たな変革期
終章 男性アイドルとはどのような存在なのか
「あとがき」
序章「男性アイドルは、どのように変わって来たか」の1「男性アイドルの二大タイプ、『王子様』と『不良』」では、憧れをかき立てるやさしい「王子様」タイプとギラギラした野性味あふれる「不良」タイプ。この二つのタイプが競い合うことで、男性アイドルの世界は展開してきたと主張されています。たとえば、1960年代の初代ジャニーズとGS(グループサウンズ)、さらに70年代の郷ひろみと西城秀樹などは、それぞれ「王子様」と「不良」のタイプを担いながら時代をかたちづくった存在だったと指摘しています。これは、わたしも気づいていました。
続けて、著者は「ここでひとつ気づくのは、『王子様』タイプを担ったのがいずれもジャニーズアイドルだったこと、そして『不良』タイプを担ったのがそれ以外のアイドルだったことである。言い換えれば、ジャニーズアイドルの原点は『不良』ではなく『王子様』であり、それは1970年代まで変わらなかった。たとえば、70年代後半にロックミュージシャンがアイドル化した『ロック御三家』(Char、原田真二、世良公則&ツイスト)の人気などは、『不良』タイプのアイドルがジャニーズ以外の領分だったことを物語るものだろう」と述べています。
大きく状況が変わるのは、1980年代からでした。70年代後半、勢いを失っていたジャニーズは、たのきんトリオ(田原俊彦、近藤真彦、野村義男)のブレークによって息を吹き返すのです。著者は、「学園ドラマ『3年B組金八先生』(TBS系、1979年放送開始)の生徒役から人気者になった3人には、それまでの男性アイドルにはない『普通の男の子』の魅力があった」と述べています。
また、著者は以下のようにも述べています。
「しかしそのなかでも、田原俊彦はジャニーズの伝統を受け継ぐ『王子様』タイプ、近藤真彦はやんちゃなイメージの『不良』タイプと従来の構図は引き継がれていた。このとき以来、『王子様』の系譜では少年隊、『不良』の系譜では男闘呼組といったように、ジャニーズが双方のタイプを一手に引き受ける時代が始まった」
ジャニーズが男性アイドル全般をカバーし、「男性アイドル=ジャニーズ」になる流れの大本は、ここにあるとして、著者は「1980年代後半に社会現象的ブームを巻き起こした光GENJIにしても、基本は『王子様』タイプでありながら、そこにやんちゃなタイプのメンバーもいるなど『不良』要素が絶妙のさじ加減でミックスされていた」と述べます。光GENJIの後には、SMAPが登場。
2「『普通』を男性アイドルの常識にしたSMAP、そして嵐」では、「普通」という魅力は、たのきんトリオにもあったものでしたが、著者は「SMAPは、それを『男の子』と呼ばれるような年齢に限定されないアイドルの魅力として認めさせたところが、決定的に新しかった。そしてSMAPのアイドル史に残る圧倒的成功は、必然的に『普通』を男性アイドルのスタンダードにした」と述べます。
そこには平成の日本社会に特有の時代背景もあったと指摘する著者は、「平成は、バブル崩壊に始まり、阪神・淡路大震災、地下鉄サリン事件、東日本大震災、さらに格差の拡大などによって漠然とした不安が社会全体に広まった時代、裏返して言えば当たり前に普段どおりの生活を送れることの価値が再認識された時代だった。だからこそ、そうした状況のもとでアイドルが『普通』を全うする姿は、より輝きを増した。実際、SMAPは、阪神・淡路大震災や東日本大震災の際など、社会との接点を積極的にもとうとした点でも新しいアイドルだった」と述べています。
SMAPの「普通」の魅力を引き継いだのが、1999年にデビューしたジャニーズ事務所の後輩、嵐でした。著者は、「SMAPが切り開いた男性アイドルの生きる道筋は、その後デビューしたほかの多くのジャニーズグループにとってのお手本になった。そのなかでも嵐は、より普通らしい『普通』の魅力を備えたグループとして、2000年代以降のジャニーズグループの象徴的存在になった」と述べています。第1章以降は、グループサウンズ(GS)前夜からの日本のアイドル史を振り返っていきます。
第1章「GSとジャニーズ」の「エレキブームからGSブームへ」では、1960年代に大ブームとなったベンチャーズとビートルズの音楽性を比較しながら、著者は「ベンチャーズの音楽はインストゥルメンタル、つまり演奏だけでボーカルがないものだった。それに対し、ビートルズは演奏しながら歌うスタイル。エレキギターと歌の組み合わせは当時の日本人にとっては新鮮で、ビートルズの来日をきっかけに、今度はそのスタイルを模倣するバンドが続々誕生した。それが、GSブームの土台になっていく」と述べています。
GS最初のレコードは、1965年5月発売のザ・スパイダース「フリフリ」。著者は、「フリフリ」について、「ビートルズの来日よりも前だが、この曲の作詞・作曲者でもあるメンバーのかまやつひろしは、海外の最新音楽動向に詳しかった。そのために、日本ではベンチャーズスタイルが全盛のなかでいち早く歌入りの楽曲をリリースしたのである。そこには、スパイダースが所属していた芸能事務所ホリプロダクションの思惑もあった」と述べます。
意気込んで作ったものの洋楽色が強い「フリフリ」は、歌謡曲全盛の時代にはヒットするまでに至りませんでした。ホリプロダクションの創業者である堀威夫は、マネジメントする立場としてまずヒット曲を出すことにこだわったといいます。そこで堀からスパイダースに提案したのが、歌謡曲のヒットメーカー浜口庫之助が作った「夕陽が泣いている」(1966年9月)でした。著者は、「夕焼けを太陽が泣いている様子に見立てた詞がいかにもセンチメンタルなバラード曲だが、曲調はやはり歌謡曲的でスパイダースは難色を示した。しかし発売してみるとこれが100万枚を超える大ヒットになり、スパイダースは一躍人気グループとなる」と述べます。
その機をとらえた堀は、事前にスカウトして準備を進めていたほかのGSグループを一斉にデビューさせました。「亜麻色の髪の乙女」のヴィレッジ・シンガーズ、「小さなスナック」のパープル・シャドウズ、「ガール・フレンド」のオックス、「朝まで待てない」のザ・モップスなどで、これらはいずれもホリプロダクションの所属でした。そこにザ・タイガースやザ・ワイルド・ワンズの渡辺プロダクション勢、さらにジャッキー吉川とブルー・コメッツやザ・テンプターズなども加わり、一気にGSブームが到来するのでした。
2「『不良』だったGS、『夢』を追ったジャニーズ」では、GS出身者からアイドル的な存在も生まれたことが紹介されます。代表は、タイガースの沢田研二、テンプターズの萩原健一、スパイダースの堺正章などです。著者は、「あらためて言うまでもないが、沢田はソロ歌手、萩原は俳優、そして堺はコメディアンとして再出発し、それぞれ一世を風靡した。そして分野も芸風も異なるとはいえ、そこにはやはり前述したようなGS的不良性が感じられる」と述べています。
3「『王子様』フォーリーブスとジャニー喜多川の哲学」の「GSとジャニーズ、その基本路線の対立」では、GSを魅力的なものに見せていたのは不良性だったとして、著者は「それは、この時代特有の反体制気分も含んでいたものの、最終的には政治色が薄いエンタメ限定のものとして発展した」と述べます。「ツッパリ」「ヤンキー」「やんちゃ」といったその後の男性アイドル史に登場するキャラクターは、ここで定まった「不良」イメージのバリエーションでもあるのです。
「テレビを味方につけた『王子様』フォーリーブス」では、ジャニーズ事務所の創業者であるジャニー喜多川は、GSと徹底的に差別化するためにジャニーズのタレントを健全なアイドル、その理想形としての「王子様」として打ち出す戦略をとりました。その戦略を体現したのが、初代ジャニーズの弟分にあたるフォーリーブスでした。フォーリーブスは、仕事よりも学業を優先する方針を打ち出し、舞台上でもGSとの違いを意識した演出がなされました。そして、初代ジャニーズの教訓に基づくフォーリーブスの戦略的独自性はテレビの重視にありました。フォーリーブスは、音楽番組(NHK「紅白歌合戦」は1970年から7回連続出場)だけでなく、バラエティ番組にも積極的に出演したのです。
2章「『新御三家』の時代」では、1970年代に人気を集めた西城秀樹・野口五郎・郷ひろみの「新御三家」が取り上げられます。御三家という括り方について、著者は「日本特有のことなのかどうかはわからないが、『三』という数字でその分野を代表させるパターンは少なくない。芸能の分野もそうだ。女性歌手だと、『三人娘』(美空ひばり、江利チエミ、雪村いづみ)や『新三人娘』(小柳ルミ子、南沙織、天地真理)がすぐに思い浮かぶ。そして男性歌手では、1960年代前半に登場した橋幸夫、舟木一夫、西郷輝彦の『御三家』がいた。3人全員がデビュー年にレコード大賞新人賞受賞と『NHK紅白歌合戦』初出場を果たし、その後も長く活躍した」と述べています。
2「野口五郎と西城秀樹――対照的だった二人のアイドル」の「ロックとアイドルを共存させた『不良』西城秀樹」では、西城秀樹が一貫して追求したのは歌謡曲と洋楽、特にロックの要素を融合した良質の「歌謡ロック」だったと言えるとして、著者は「同じ方向性を共有していた沢田研二と同様、当時としては珍しく自前のロックバンドを従えて歌ったのは、その表れである。また『傷だらけのローラ』のようなバラード曲にしても、本人が言うように『洋楽と日本のメロがうまく融合したようなオリジナリティのあるメロディ』のものだった」と述べます。
西城秀樹の最も興味深い点は、根っからのロック志向でありながらも、同時に現在のアイドル文化にも影響を与えるスタイルの開拓者になりえたところであると指摘する著者は、「ファンのコールや振り付けはその一端だ。また、現在ではアイドルの現場に必須のペンライト(サイリウム)による応援のパイオニアであるともされる。またスタジアムコンサートを開催し、ゴンドラやクレーンを使った演出など現在のアイドル文化に残した影響は小さくない」
「西城秀樹は、GSからの系譜を受け継いだという意味で、男性アイドルの『不良』タイプの正統的な後継者のポジションにあった。当時の人気劇画を映画化した『愛と誠』(監督:山根成之、1974年)で不良の主人公・大賀誠を演じたのも、その点で必然であった」と述べるのでした。『愛と誠』は、梶原一騎の原作、ながやす巧の作画で、「週刊少年マガジン」(講談社)にて1973年3・4合併号から1976年39号まで連載された日本漫画史に燦然と輝く名作で、1975年には講談社出版文化賞児童まんが部門を受賞しています。
3「郷ひろみ、そして『新御三家』のアイドル史的意味」の「『王子様』の系譜を継ぐジャニーズアイドル、郷ひろみ」では、西城秀樹が男性アイドルの「不良」の継承者だったとすれば、もうひとつの系譜である「王子様」のポジションにいたのが郷ひろみだったとして、著者は「それは、郷ひろみが『王子様』的アイドルの原点であるジャニーズのタレントだったという意味でも自然な流れだった」と述べています。郷ひろみは、もともと本名の「原武裕美」としてフォーリーブスの弟分でしたが、ファンから絶大な支持を受け、初めてテレビ番組のステージに立ったとき、会場の女性たちから一斉に「ゴーゴーゴーゴー レッツゴーヒロミ」というコールを浴びせられ、これに驚きと感激を味わった彼が、この「ゴー」につなんで芸名を「郷ひろみ」に決めたといいます。
デビュー曲「男の子女の子」のレコーディングディレクターだった酒井政利によれば、デビュー当時の郷ひろみは、「幾分ふっくらとした幼さの残る男の子ではあったが、目だけは決して子供のそれではなかった。ひと言で言えば、茫洋とした目、何を考えているのだろうかと思わせるような目・・・・・・であった。そして無口で、愛想笑いなど一切しない少年であった」と述べ、その魅力を「不気味」と表現しています。著者は、「それはおそらく、『郷ひろみ』という『王子様』的アイドルが、男性か女性か、子どもか大人かというような性別や年齢についての固定観念を第超えたところにいることを酒井なりに表現したものだろう」と述べています。
そこには、既存の性別を超えたところにあるエンターテインメントという点で、宝塚歌劇にも通じるものが感じられるとして、著者は「実際、『男の子女の子』の詞を担当したのは、越路吹雪との盟友関係で知られ、宝塚歌劇団出版部にいた経歴をもつ作詞家・岩谷時子だった。その後も岩谷は、『裸のビーナス』(1973年)、『花とみつばち』(1974年)など郷ひろみの初期ヒット曲の多くを手掛けることになる。そうした積み重ねのなかで、(これは岩谷の詞ではないが)『よろしく哀愁』(1974年)が郷自身、そしてジャニーズにとっても初のオリコン週間シングルチャート1位を獲得するに至るのである」と述べるのでした。
第3章「学園ドラマと『ロック御三家』」では、1970年代の男性アイドルの多様化について書かれています。1「森田健作と学園ドラマのアイドル化」の「思わぬ成功だった『青春とはなんだ』」では、学園ドラマの分野を大きく開拓したのは日本テレビだったとして、「記念すべき第1作は、石原慎太郎の同名小説が原作の『青春とはなんだ』(1965-66年)である。主演は当時東宝のスターだった夏木陽介。夏木が演じたのは、アメリカ帰りの新任教師・野々村健介。彼が赴任するのは田舎の小さな町の高校である。その町にはいまも昔からのしきたりが残り、人びとは閉鎖的だ。野々村はそんな古い慣習や価値観に反発し、アメリカ仕込みの果敢な行動力で生徒が抱える悩みや問題を解決していく。封建的な人びとに立ち向かう民主主義的な熱血教師。そんな学園ドラマの基本構図が当初から明確だったことがうかがえる。夏木演じる教師がアメリカ帰りで、しかも都会ではなく田舎の学校に赴任するという設定も、その対比を強調している」とあります。
「生徒が主役になった森田健作『おれは男だ!』」では、1970年代に入って登場した作品が、再び学園ドラマを活性化したことが紹介されます。森田健作主演の『おれは男だ!』(日本テレビ系、1971-72年)がそれです。最大の変更ポイントは、教師ではなく生徒が主人公になったことでした。著者は、「従来の学園ドラマの教師が完全無欠のヒーローだったとすれば、この『おれは男だ!』で森田健作が演じる生徒は、迷い悩みながらもライバルとの切磋琢磨のなかで成長していく、いわばアイドル的なキャラクターだった。学園ドラマでも1970年代になって、アイドルの時代が本格的に到来したのである。学園ドラマ出演の若手人気俳優は、『新御三家』とともに男性アイドル界の一角を担う存在になっていく」と述べています。
著者は、『おれは男だ!』に“歌謡ドラマ”の趣があった(初回にはフォーリーブスが本人役で出演し、歌った)ことに注目し、アイドル化の一端であると見ます。また、森田健作は自ら主題歌「さらば涙と言おう」を歌い、これがヒットしました。劇中で森田が挿入歌「友達よ泣くんじゃない」を歌うミュージックビデオ風の場面もありました。また不良生徒役で当時人気を集めた石橋正次も日本テレビ系『飛び出せ!青春』の挿入歌「夜明けの停車場」(1972年)をヒットさせ、『NHK紅白歌合戦』にも出場したほどでした。
2「中村雅俊の登場と‟終わらない青春”」の「「中村雅俊が体現したモラトリアム」では、村野武範主演の『飛び出せ!青春』(1972年~73年)の世界をそのまま引き継いだ続編『われら青春!』(1974年)で新人ながら主演を務めた中村雅俊の魅力は、繊細さとラフさが同居しているところにあるとして、著者は「中村は、歌手としても多くのヒット曲を出した。そのきっかけになったのが、『われら青春!』の挿入歌『ふれあい』(1974年)である。このデビュー曲は、オリコン週間チャートでなんと10週連続1位を記録し、レコード売り上げも100万枚を超える大ヒットになった」と紹介します。
大ヒット曲「ふれあい」では、悲しみや空しさに襲われるとき、「あの人」にそばにいてもらいたいという内容の歌詞を、当時中村雅俊はアコースティックギターの弾き語りで切々と歌いました。これは野口五郎の「私鉄沿線」などと同じく、フォークがもつ繊細さを歌謡曲に取り込んで成功したケースと言えるとしながら、著者は「ただそうした一方で、中村雅俊には昔懐かしい『バンカラ』を思い起こさせるラフな魅力があった。そのイメージを決定づけたのが、1975年から76年にかけて放送された日本テレビ『俺たちの旅』である」と述べます。
「‟終わらない青春”というメッセージ」では、1970年代の終わり、「学校は社会の縮図」という発想に基づいた新しい学園ドラマの波が起こったことが紹介されます。その代表が、1979年に始まりシリーズ化された『3年B組金八先生』(TBS系)でした。著者は、「このドラマでは中学生の性や校内暴力、さらには性同一性障害やドラッグ問題まで実にさまざまな社会的テーマが扱われ、新しいリアルな学園ドラマとして高く評価された。ただし興味深いことに、そのようなシリアスな内容にもかかわらず、この『3年B組金八先生』からは従来の学園ドラマと同様に多くのアイドルも生まれた。その先鞭をつけたのが、第1シリーズに生徒役で出演して爆発的ブームを巻き起こした田原俊彦、近藤真彦、野村義男のたのきんトリオである。1970年代後半停滞していたジャニーズは、これをきっかけに80年代以降大きく息を吹き返すことになる。その意味では、男性アイドル史のターニングポイントになった作品でもあった」と述べます。
第4章「ジャニーズの復活とロックアイドルの人気」では、1980年代の男性アイドル全盛期について書かれています。「田原俊彦が変えた歴史――『寝たい男』になったジャニーズ」では、女性誌「an・an」(マガジンハウス)の企画で毎年発表される「好きな男」ランキングで、1987年のアンケートの結果、田原俊彦が1位になりました。この「好きな男」とは「寝たい男」のことであり、同誌の主な読者層が20代から30代の働く女性だったことを考えると、これは画期的なことでした。ちなみに、85年の1位は山崎努で、86年の1位は岩城滉一でした。その劇的な変化は明らかであり、それまでトップを渋い年上の俳優が占めていたのが、いきなりジャニーズアイドルになったわけです。
「『不良』から『やんちゃ』へ――近堂正彦が体現したもの」では、田原俊彦がバックダンサーを従えて華やかに歌い踊ったとすれば、近藤真彦はロックバンドを従えてシャウトするのが二人の個性のコントラストでもあっとして、著者は「その意味では、田原の郷ひろみに対し、近藤は同じ『新御三家』でも西城秀樹に近いと言える。やはり男性アイドルの『不良』の系譜である。本人にとってもジャニーズ事務所にとっても初となった日本レコード大賞の受賞曲『愚か者』(1987年)が荻原健一との競作だったのも、その意味でうなずける」と述べています。
また、著者は「田原俊彦がファンにとって身近な『王子様』だったように、近藤真彦も身近な「不良」だった。そのあたりは、同じロック路線のアイドルだった吉川晃司(1984年に「モニカ」でデビュー)と比べても明白だろう吉川が最終的に本格的なロックミュージシャンの道を選んだのに対し、近藤真彦はあくまでジャニーズアイドルとしての道を進んだ」と書いています。ちなみに、わたしが1番好きな男性アイドルは田原俊彦で、2番目が吉川晃司でした。2人の共通点は足が高く上がることで、若い頃は、カラオケを歌うときによく真似して右足を高く上げてみたものでした。それで転んだこともあります。(笑)
5「シブがき隊、少年隊、そして光GENJIブーム」では、たのきんトリオに続いてデビューし、人気を集めたのが、同じ3人組のシブがき隊であるとして紹介されます。著者は、「デビューの経緯も似ていた。シブがき隊は、『3年B組金八先生』と同じ枠で放送された学園ドラマ『2年B組仙八先生』への生徒役出演をきっかけに結成された。不良タイプの薬丸裕英、王子様タイプの本木雅弘、優しい感じの布川敏和という3人のバランスも、たのきんトリオを思わせる」と述べています。
シブがき隊の同期には小泉今日子や中森明菜、松本伊代、堀ちえみ、早見優、石川秀美ら人気アイドル歌手も多く、「花の82年組」と呼ばれました。彼らの活躍の背景には、ジャニーズの躍進以外にそうしたアイドル全盛期の到来があったとして、著者は「それらアイドル歌手たちの人気を支えていたのが、『夜のヒットスタジオ』や『ザ・ベストテン』などのテレビの音楽番組である。たのきんトリオや松田聖子から始まって、1980年代前半はテレビとアイドルの関係が一心同体と言えるほど密接になった時期だった。当然、『花の82年組』の活動の主舞台もテレビだった」と述べています。
「‟光GENJI現象”が意味するもの」では、著者は「たのきんトリオは『3年B組金八先生』というテレビドラマが生んだアイドルだった。つまり、1960年代以来のジャニーズの原点が舞台であるとすれば、活動の場としてそれに加えてテレビの比重がぐっと増したのが80年代だった。シブがき隊と少年隊の路線の違いは、そんな歴史的変化の反映でもあった。そこに彗星のように登場したのが、光GENJIである。彼らは、ジャニーズにとどまらず男性アイドル史上でもあまり類をみないような爆発的ブームを巻き起こした」とも述べています。光GENJIのデビュー曲「STAR LIGHT」(1988年)はオリコン週間シングルチャートで初登場1位を獲得、年間ランキングでも4位を記録しました。
それだけでも人気のほどがうかがえますが、翌1988年度のオリコン年間ランキングでは、「パラダイス銀河」「ガラスの十代」「Diamondハリケーン」がトップ3を独占するという快挙を達成。さらに「パラダイス銀河」でデビュー2年目にして日本レコード大賞を受賞するなど、光GENJI旋風が吹き荒れました。その人気の一因に、代名詞とも言えるローラースケートでの派手なパフォーマンスがあったと指摘し、著者は「曲のあいだメンバーは縦横無尽にローラースケートで駆け回り、バク転やバク宙まで披露した。その華麗さと疾走感は、彼らのアイドル性をいっそう際立たせた。なぜ、ローラースケートなのか。そこにはジャニーズらしく、ミュージカルが関係していた。当時、世界的に人気を集めていた『スターライトエクスプレス』というロンドン発のミュージカルがあった」と述べています。
「伝統的男性アイドル像の終わり?――SMAPへ」では、“光GENJI現象”は、1970年代以来続いてきた伝統的男性アイドルの最後の輝きだったのではないだろうかとして、著者は「光GENJIが登場したのは80年代後半、つまりちょうど昭和の終わりごろである。したがってそれ以降の平成の男性アイドルは、まったく新しいタイプのアイドル像の確立を求められた。そのパイオニアとしての役割を担うことになったのが、光GENJIのバックで踊っていた6人の少年たちである。光GENJIのバックダンサーだったJr.のなかに、『スケートボーイズ』という10人あまりのグループがあった。そしてそのメンバーのなかから6人が選ばれ、新たにグループが結成される。彼らは『SMAP』と名付けられた」と述べます。
第5章「SMAPとダンスアイドルの台頭――1990年代の新たな男性アイドル像」の1「SMAPの登場、そのブレークへの道のり」では、昭和から平成になった頃、つまり1990年の前後に『夜のヒットスタジオ』や『ザ・ベストテン』、『歌のトップテン』(日本テレビ系、1986~90年)など当時を代表する長寿音楽番組が続々と終了したことを紹介し、著者は「それは、60年代からテレビとともに発展してきた歌謡曲全体の衰退と軌を一にするものだった。その結果、テレビの音楽番組で新曲を聴いた視聴者がレコードやCDを買ってヒットにつながるという従来の構図が崩れた。SMAPは、ちょうどそのタイミングでデビューしたことになる。その意味では、本人たちの努力だけではどうしようもない部分も小さくなかった」と述べています。
2「SMAPはアイドルの定義を変えた」の「『SMAP×SMAP』のアイドル史的意味」では、1996年4月15日、SMAPの冠バラエティ番組『SMAP×SMAP』(以下、『スマスマ』と表記)が始まりました。フジテレビ系の月曜夜10時。「月9」に続く時間帯ですが、実はその日は、メンバーの木村拓哉が主演して社会現象的な人気を博することになる『ロングバケーション』の初回放送日でもあった。『スマスマ』の冒頭に生放送でそのことを話題にする場面もあり、グループとソロの両立を図るSMAPの活動を凝縮したような番組編成でもあったとして、著者は「『スマスマ』はまさにバラエティの王道をいくものだった。旬のゲストを招いて料理を振る舞いながらトークを楽しむ『BISTRO SMAP』、『マー坊』『古畑拓三郎』『カツケン』など多くの人気キャラクターを生んだオリジナルコント、そしてマドンナやマイケル・ジャクソンなど海外の大物を含む人気アーティストとのコラボによる『S-Live』。この基本構成は、番組が続いた約20年間ほとんど変わらなかった」と述べます。
男性アイドル史のなかでSMAPは「普通の男の子」の系譜を受け継いでいたという著者は、「ときにはかっこわるい部分をさらすこともいとわない。だが、そのために私たちも共感し、応援できる。そんな『王子様』でも『不良』でもない『普通の男の子』という第3の道を、SMAPは大きく発展させた」と述べ、さらには「SMAPの登場とともに、男性アイドルは『普通の男の子』から脱皮し、『普通のひと』、言い換えればあらゆる人にとって『普通』であることの価値を体現してくれる存在になったのである。違う言い方をすれば、ここでSMAPは、アイドルグループでありながらどのような人びとをも包み込む一種のコミュニティのようなものになっていた。東日本大震災があった2011年末の『NHK紅白歌合戦』で『オリジナル スマイル』を大トリで歌い、15年に被災地での『NHKのど自慢』に出演した姿は、その証しだった」と述べるのでした。
第6章「嵐の登場と『ジャニーズ1強時代』の意味」の2「ジャニーズJr.黄金期」の歴史的意味、そして嵐のデビュー」では、1999年10月にジャニーズJrが最初の東京ドームでコンサートを開いたとき、ファンの前でお披露目されたのが、すでにデビューが決まっていた嵐でした。相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔(当初は「桜井」表記)の5人からなる嵐。リーダーの大野が1980年生まれで、あとの4人はみな82年から83年生まれ。比較的年齢が近いメンバーが集まっていました。
3「国民的アイドルになった嵐、そのジャニーズ史的意味」の「嵐が示した“より普通らしい『普通』”」では、櫻井翔のキャスターとしての活動などが典型的ですが、嵐全体に言えることは、いわゆる芸能界の匂いがあまり前面に出てこないことであり、そのことが「普通」であるという嵐の魅力につながっているとして、著者は「嵐はジャニーズアイドルが『普通』であることがすでに当たり前になった時代に誕生した。その意味で、嵐が体現したのは“より普通らしい「普通」”であった。全員がそうだというわけではないが、嵐のメンバーたちは、ある意味ジャニーズであることへのこだわりが薄かった。
大野智は、元時代に「芸能界はもういいかな」と思い、一度はジャニーズ事務所を辞めようと考え、その意向を伝えてもいました。絵の関係の仕事に就きたいと思っていたのです。二宮和也も、嵐のデビュー直前に事務所を辞めてアメリカで映画製作の勉強をする決意を固めていました。櫻井翔は、Jr.時代には学業優先で生活していました。試験のひと月前からは仕事を休んだ。そのため仕事が減ったこともあったが、「それはそういうもんだ」と受け止め、「高校卒業したらジャニーズはやめようかな」と思っていたといいます。そして、彼らは2020年をもって活動休止することを発表しました。
第7章「ジャニーズのネット進出、菅田将暉とBTSが示すもの」の2「新しいソロアイドル、菅田将暉ら若手俳優の台頭」では、「福山雅治、星野源、北村匠海・・・・・・、“演技する歌手”の時代」として、著者は「『アイドル=歌手』という常識は、1980年代まで根強いものがあった。ただ前に書いたように、学園ドラマの出演をきっかけにアイドル的な人気を集める中村雅俊のような俳優もいた。森田健作や石橋正次などもそうだったが、彼らは俳優を本業とする一方で歌も歌ってヒットを飛ばし、歌手としても存在感を発揮した。それはさかのぼれば石原裕次郎や小林旭などにも共通するが、いずれにせよ彼らは“歌う俳優”として活躍した。1990年代に入り、同じ兼業でも逆のタイプの存在が頭角を現す。つまり“演技する歌手”である。彼らは、いま挙げたような俳優と比べれば、明白に音楽により多くの比重を割いた活動を展開した」と述べています。その先駆的存在は福山雅治であり、同じことは星野源にも当てはまり、この系譜を継ぐ直近の存在としては北村匠海がいます。
一方、最近の若手俳優の登竜門になっているのが、ライダーもの(「仮面ライダーシリーズ」[テレビ朝日系ほか、1971年-)や戦隊もの(「スーパー戦隊シリーズ」[テレビ朝日系ほか、1975年-])などの特撮ドラマです。2000年代後半から10年代に時期を絞ってみても、特撮ドラマ出身で現在活躍する俳優は枚挙にいとまがありません。主だったところだけでも、ライダーものでは佐藤健、瀬戸康史、菅田将暉、福士蒼汰、吉沢亮、竹内涼真、磯村勇斗、戦隊ものでは松坂桃李、千葉雄大、山田裕貴、竜星涼、志尊淳、横浜流星など、錚々たる顔ぶれが並んでいます。本当に、みんな大活躍ですね!
錚々たる仮面ライダー俳優たちの中でも、「平成仮面ライダーシリーズ」のひとつ、『仮面ライダーW』(テレビ朝日系、2009-10年)に主演した菅田将暉の存在感が際立ちます。1993年生まれの彼は、放送開始時16歳。ライダーものの主役としては史上最年少でした。ブログ「アルキメデスの対戦」、ブログ「糸」、ブログ「花束みたいな恋をした」、ブログ「キャラクター」などにも書いたように、わたしは俳優としての彼を非常に高く評価しています。また、歌手としても紅白出場を果たすなど、マルチな才能の持ち主です。本人によれば、自分自身の俳優としての強みは「身長176cm、A型、長男、右利き、顔は濃くも薄くもなく、眉を隠すことで印象を変えられる」とデータ的に全てにおいて「普通」なので、どんな役にも寄せやすいのかもしれないと分析しています。ということで、SMAPや嵐を経て、いま最も「普通」を体現している男性アイドルが菅田将暉なのかもしれません。
2021年9月29日 一条真也拝
 「ムーンライト・シャドウ」
「ムーンライト・シャドウ」
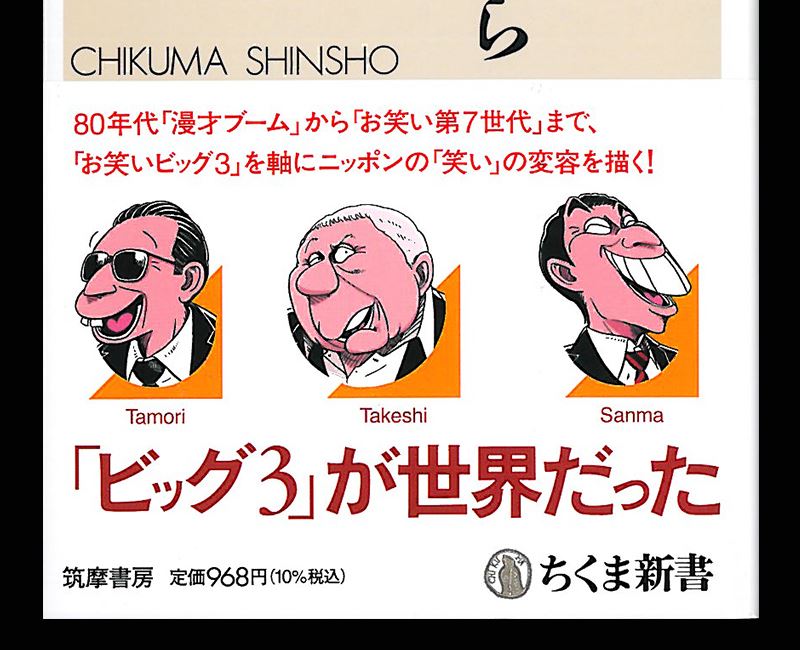










 「
「
 「
「

 「フューネラルビジネス」2021年10月号
「フューネラルビジネス」2021年10月号 「フューネラルビジネス」2021年10月号
「フューネラルビジネス」2021年10月号

