
一条真也です。
19日から東京に出張します。
『コロナ後に生き残る会社 食える仕事 稼げる働き方』遠藤功著(東洋経済新報社)を読みました。これまで「コロナ後」に関するさまざまな本を読んできましたが、本書はとても具体的にコロナ後の社会やビジネスを在り方を示し、コロナ後に日本人を襲う「会社・仕事・働き方の大変化」をわかりやすく解説しています。著者の代表作に『見える化ーー強い企業をつくる「見える」仕組み』(東洋経済新報社)という好著がありますが、本書はまさしくコロナ後の世界を「見える化」してくれました。
著者は、株式会社シナ・コーポレーション代表取締役。早稲田大学商学部卒業。米国ボストンカレッジ経営学修士(MBA)。三菱電機、複数の外資系戦略コンサルティング会社を経て、現職。2005年から2016年まで早稲田大学ビジネススクール教授を務めた。2020年6月末にローランド・ベルガー日本法人会長を退任。7月より「無所属」の独立コンサルタントとして活動している。多くの企業のアドバイザー、経営顧問を務め、次世代リーダー育成の企業研修にも携わっている。株式会社良品計画社外取締役。SOMPOホールディングス株式会社社外取締役。株式会社ドリーム・アーツ社外取締役。株式会社マザーハウス社外取締役。株式会社NTTデータアドバイザリーボードメンバー。

本書の帯
本書の帯には「緊急出版」として、「【会社】弱肉強食が加速!――世界的『コロナ大恐慌』の衝撃」「*『3つの蒸発』+『牽引役』不在で長期化」「【仕事】あなたの仕事は消失or残る?」「米国では5人に1人が失業」「*『プロ』しか食えない時代に」「【働き方】レスの時代!」「『通勤レス』『対面レス』『出張レス』がいっきに加速」「*『生産性×創造性』を最大化する秘訣」と書かれています。

本書の帯の裏
帯の裏には、以下のように書かれています。
あなたの会社・業種も消えるのか?
――経済と企業の見通し
*1000兆円の所得が消え、
日本でも15兆円の消費が喪失
*リーマンショックを超える景気悪化はこれから
*「移動蒸発、需要蒸発」がもたらす、
深刻な「雇用蒸発」の衝撃
――中国では2億人が職を失い、
日本でも222万人が失職する試算も
*日本企業がとるべき4つの経営戦略
――「SPGH戦略」
仕事はどう変わる?
――どこでも食える「プロ人材」になれ!
*トヨタは5割を中途採用に
「無用な人」と「引く手あまたの人」の二極化へ
*終身雇用は消滅するのか?
衰退する職業で「生き残る人」の共通点は?
*プロとして勝ち残る5つのパラダイムシフト、
8つの成功ポイント
働き方はどこまで変わる?
――「レスの時代」の仕事術
*フェイスブックが掲げる
「リモートワークが可能な人の4条件」
*「70%ルール」で時間を捻出し、
「新たな変化・価値を生む仕事」に挑む
*「チームワーク」「育成」「自己管理」のコツ、
社内コミュニケーションの4原則
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
はじめに――「コロナ・ショック」を「コロナ・チャンス」に変える
第1章 コロナがもたらす「本質的変化」とは何か
1 「移動蒸発→需要蒸発→雇用蒸発」という
コロナ・ショックのインパクトを理解する
2 「弱肉強食の時代」に突入する
3 「低成長×不安定」の時代に、
生き残る覚悟をもつ
第2章 コロナ後に、日本企業は何を、
どう変えるべきなのか
1 日本企業が再生のためにとるべき戦略
2 ポストコロナのサバイバル戦略
3 ポストコロナの生産性戦略
4 ポストコロナの成長戦略
5 ポストコロナの人材戦略
第3章 コロナ後に、
「仕事」はどのように変わるのか
1 「食える仕事」「食えない仕事」とは何か
2 「プロフェッショナルの時代」がやってくる
3 「プロ化するビジネス社会」で
生き残るための処方箋
4 「プロ」として成功するための8つのポイント
第4章 コロナ後に、
「働き方」はどのように変わるのか
1 「レスの時代」の幕開け
2 どうすれば「生産性の高い働き方」ができるのか
3 リモート時代における
社内コミュニケーションの4原則
4 働き方の自由度を高め、真の豊かさを享受する
5 どうすれば「創造性の高い働き方」ができるのか
6 コロナ後の人材評価の4つのポイント
おわりに――元に戻るな、大きく前に進め!
「はじめに――『コロナ・ショック』を『コロナ・チャンス』に変える」の「『まさかこんなことに・・・・・・』という時代を生きる」では、近年、大企業の経営者たちがよく使う「VUCA」という言葉が紹介されます。「VUCA」とは「Volatility」(不安定性)、「Uncertainty」(不確実性)、「Complexity」(複雑性)、「Ambiguity」(曖昧模糊)という4つの単語の頭文字からとった略語であり、「先がまったく読めない不安定、不透明な環境」を意味します。
この「VUCA」について、著者はこう述べます。
「私たちは『VUCA』という新たな混迷する環境を頭では理解し、備えていたつもりだった。しかし私たちの認識は、とんでもなく甘かったと認めざるをえない。『VUCA』とは『まさかこんなことに・・・・・・』という事態が起きることなのだと思い知らされた。中国に端を発する新型コロナウイルスは、わずか半年ほどで世界を震撼させ、経済活動や社会活動をいっきに停滞させ、世界中の人々の生活をどん底に陥れようとしている。『つながる』ことや『ひとつになる』ことの恩恵ばかりを享受していた私たちは、その裏で広がっていた『感染』というリスクの怖さを、日々身をもって体験している」
また、「世界的な『コロナ大恐慌』の可能性は高まっている――インパクトはとてつもなく大きく、長くなる」では、たとえ今回のコロナが収束しても、シベリアの永久凍土が溶け出し、新たな感染症が懸念されるなど、ウイルスによるリスクは間違いなく高まっていると指摘し、著者は「パンデミック(感染爆発)のインパクトはとてつもなく大きく、長くなることを私たちは覚悟しなければならない。経済の低迷は、企業の倒産、失業者の急増、自殺者の増大、食糧問題の深刻化など社会不安を高め、世界は混迷を深めている」と述べています。
米国では白人警官が黒人男性の首を圧迫して死亡させた事件をきっかけとした抗議活動が全米に広がり、その一部が暴徒化、放火や略奪まで起きていますが、その背景について、著者は「黒人らマイノリティのコロナによる死亡率の高さや大量失業などによる不安や不満の蓄積があると指摘されている。人種差別を糾弾するデモは世界中に広がっている。ドミノ倒しのようにさまざまな問題が連鎖し、世界的な『コロナ大恐慌』になる可能性は高まっている」と述べます。
「『緩慢なる衰退』から脱却する千載一遇のチャンスでもある――コロナ後に確実に起きる変化は、ある程度読み解ける」では、コロナ後の変化を先取りし、先手先手を打たなければ、コロナの大渦に呑み込まれてしまうだろうとして、著者は「世界経済は大きく縮む。当面はコロナ前と比較して『30%エコノミー』『50%エコノミー』を想定せざるをえない。その先においても、『70%エコノミー』が妥当な予測だろう。それぞれの会社は、まずは『縮んだ経済』に合わせて、身を縮めるしかない。生き残るためには、痛みを伴う施策を断行せざるをえない会社も出てくるだろう」と述べています。
しかし、コロナ・ショックは日本にとって必ずしもマイナスばかりではないとして、著者は「むしろ、平成の『失われた30年』という『緩慢なる衰退』から脱却し、力強い再生へとシフトする千載一遇のチャンスである。中途半端に沈んだまま、もがきつづけるより、どん底まで沈んだほうが反転力は強くなると私は期待したい。それだけの回復力、潜在力が、この国にはあるはずだ」と述べます。
「『プロの時代』『レスの時代』の幕開けになる」では、経済的な側面よりも、日本人の価値観や働き方を大きく変え、日本という国が真に豊かで、幸せな国になるための好機であるとして、著者は「コロナ・ショックは、ビジネス社会における『プロの時代』の幕開けになる。滅私奉公的なサラリーマンは淘汰され、高度専門性と市場性を兼ね備えた『プロ』が活躍する時代へと突入する。競争は厳しくなるが、『個』の活性化なしに、この国の再生はありえない。そして、働き方においては『レスの時代』の幕開けとなるだろう。『ペーパーレス』『ハンコレス』にとどまらず、『通勤レス』『出張レス』『残業レス』『対面レス』、さらには『転勤レス』といった新たな働き方がこれから広がっていく」と述べます。
そして、著者は「こうした新たな動きによって、無用なストレスは軽減され、私たちは人間らしさを取り戻していく。その結果、経済的な豊かさだけでなく、精神的な豊かさも手に入れることができるはずだ。コロナという『目に見えない黒船』は、この国を再生させる大きなきっかけになりえる。私たちは『コロナ・ショック』を、自らの手で『コロナ・チャンス』へと変えなければならない」と述べるのでした。
第1章「コロナがもたらす『本質的変化』とは何か」の1「『移動蒸発→需要蒸発→雇用蒸発』というコロナ・ショックのインパクトを理解する」では、「1000兆円の所得が消える」として、コロナ不況は2008年のリーマンショックを超え、ウォール街の株価暴落に端を発した1930年代の大恐慌に匹敵すると言われていることが紹介されます。
著者は、「コロナの影響を免れる国や産業などない。一部の限られた業界を除けば、ほぼすべての業界が、すでに大きな打撃を受けている。現在は航空、鉄道、タクシーなどの交通関係、ホテル、旅館などの観光業界、飲食業、娯楽産業などを直撃しているが、これからは製造業や不動産業など、きわめて広範囲な産業に甚大な影響を及ぼすのは必至だ」と述べています。「移動蒸発→需要蒸発→雇用蒸発」という「蒸発のドミノ倒し」。わたしたちは「出口の見えないトンネル」に入り込んでしまったというのです。
2「『弱肉強食の時代』に突入する」では、「『真面目な茹でガエル』は死滅する」として、著者は「コロナをきっかけに日本企業は大きく生まれ変わろうとするだろう。変わらなければ生き延びていけないのだから、経営者たちは本気だし、必死だ。問題は社員たちだ。会社が生まれ変わろうとしているのに、社員たちの意識や行動が変わらなければ、その社員は間違いなく『お払い箱』になる。いまの日本企業に、それを躊躇している余裕などない」と述べます。コロナによって、わたしたちは「低成長×不安定」という、どん底局面へと追い込まれています。わたしたちは「先の見えないトンネル」の中にいるのではなく、「出口のないトンネル」に追い詰められているのです。
「危機的な異常事態は『新たな様式』を生み出す」として、日本の生産性の低さが取り上げられます。ここ何十年も、日本の生産性の低さが指摘され、議論され、対策も講じられてきましたが、著者は「私たちは本気で生産性を高めようとはしてこなかった。しかし、コロナ・ショックですべての活動が止まり、日本のみならず世界経済がいっきに悪化するなかで、私たちはほぼ強制的に変わらざるをえない状況に追い込まれている」と述べます。
変革には大きな損失や痛みを伴いますし、抵抗勢力の反発も大きいです。しかし、長い目で見れば、「緩慢なる衰退」が続くよりもはるかにいいとして、著者は「危機的な異常事態は、『新たな仕組み』や『新たな様式』を生み出すトリガーにもなることは歴史が証明している。実際、1929年に始まった世界大恐慌がきっかけとなって、週40時間労働や最低賃金、児童労働禁止、ワークシェアリングなどの現代に続く労働慣行は生まれている」と述べています。
そして、「『出口のないトンネル』から脱出する策をさぐる」として、著者は「『出口のないトンネル』から脱出する方法はひとつしかない。それは、自分たちで「出口を掘る」ことである。逆にいえば、いま覚醒できなければ、この国は間違いなく終わるだろう。一流国どころか、三流国へと転落し、消えていく。私たちはそうした歴史的大転換点に立たされているのである。奈落への転落を防ぎ、いま一度輝く国へと再生するために、私たちはどうしたらいいのか」と述べるのでした。
第2章「コロナ後に、日本企業は何を、どう変えるべきなのか」の2「ポストコロナのサバイバル戦略」の方策1「人員の適正化(ダウンサイジング)を断行する」では、「本社で働く3割はいらない」として、著者は「90年代のバブル崩壊後、日本企業は『3つの過剰』に苦しめられた。『設備の過剰』『雇用の過剰』『債務の過剰』である。多くの日本企業は、1990年代から2000年代はじめにかけて厳しいリストラを断行し、『3つの過剰』を解消する努力を行った」と述べています。
また、コロナ禍が起きる前のことですが、著者がある大企業の経営者と会食をした際、彼は「本社で働く3割はいらない」と語っていたとして、著者は「実際、ここ数年、『働かないおじさん』は社会問題化していた。出勤しているのに、仕事をせずにぷらぷらしている中高年層の社員たちのことだ。人手不足が叫ばれていたにもかかわらず、仕事がない、仕事をしない人たちが一定比率、存在していた。しかも、『働かないおじさん』の給与水準は高い。働かないにもかかわらず、若い人たちよりもはるかに高い報酬が支払われる。若い人たちのモチベーションは下がり、職場の雰囲気も悪くなるのは必然である」
方策2「コストの『変動費化』を進める」では、「『身軽』にするのが最大のリスクヘッジ」として、著者は「コロナの影響が最も深刻な業界は、固定費の高いビジネスである。重厚長大な大規模設備投資型の産業や、人を多く抱える労働集約的な産業は、経済活動がストップし、稼働率がいっきに下がると、持ちこたえることができない。航空、鉄道、鉄鋼などは、きわめて厳しい状況に追い込まれている。今回のコロナが収束しても、同様のウイルスがまた世界で猛威をふるうことは間違いなく起こりうる。『需要蒸発』というリスクは、高固定費ビジネスのあり方を根本から変えてしまう可能性がある」
3「ポストコロナの生産性戦略」では、「会社は『不要不急』なものだらけだったことが露呈した――止まったからこそ、いろいろなものが見えてきた」として、ひとことでいえば、会社は「不要不急」なものだらけだったことが明かされます。著者は、「行く必要のない『不要な通勤』、結論の出ない『不要な会議』、ただ飲み食いするだけの『不要な出張』、意味や価値のない『不要な業務』、だらだらとオフィスにいつづけるだけの『不要な残業』・・・・・・。すべてが止まったからこそ、会社という組織がいかに『不要不急』なものに汚染されているかという『不都合な真実』があからさまになった」と述べています。
また、「コロナによって『必要な人』と『不要な人』が顕在化した」として、いざ会社が本格的に再始動するときに、「本当に必要な人は誰なのか」「本当に役に立つ人は誰なのか」が明白になることが指摘されます。逆にいえば、「不要な人」「役に立たない人」、つまり「いらない人は誰なのか」が白日の下にさらされてしまうのです。著者は、「世界経済や日本経済が堅調であれば、『不要な人』を救う手だてはあるかもしれない。しかし、サバイバル戦略において述べたように、中長期的な経済の低迷が予測されるなか、企業が『いらない人』を抱えている余裕などない」と述べています。まったく同感ですね。
ポストコロナの生産性戦略のポイント1「オンライン化、リモートワークを『デフォルト』にする」では、「私たちは『新たな選択肢』を手に入れた」として、著者は「好むと好まざるとにかかわらず、オンライン化やリモートワークに移行せざるをえない状況に追い込まれたのは、この国にとって不幸中の幸いと言える。実際にやってみることによって、オンライン化やリモートワークのメリットやデメリットを実体験することができた」と述べています。
また、慣れないために、生産性が落ちたり、業務品質が下がったり、ミスコミュニケーションが起きるなどの弊害はもちろん発生すると指摘しながらも、「しかし、経験を積めば、使い勝手は必ず改善するし、技術も日進月歩で進化するだろう。また、対面だとなかなか自己主張できなかった人が、オンラインだと堂々と自分の意見を述べることができるなどのオンラインならではのメリットも確認されている。なにより大事なことは、業務を行ううえでの「新たな選択肢」を私たちは手に入れたことである。これは劇的な変化であり、この幸運を私たちは最大限に活かさなくてはならない」と、著者は述べます。
ポストコロナの生産性戦略のポイント3「生産性と『幸せ』を両立する『スマートワーク』を実現する」では、「働く人たちが『幸せ』にならなければ意味がない」として、著者は「生産性というと、どうしても経済合理性や効率性の話に終始しがちだが、より重要なのは、働く人たちが『幸せ』かどうかである」と述べます。まったく同感ですが、続けて著者は、「毎朝、通勤ラッシュに痛めつけられ、長時間労働を強いられる。さらに、パワハラやセクハラが横行し、残業後に無理やり飲み会に付き合わされたりしたのでは、とても『幸せな職場』とは言えない。コロナ以前から、多くの企業でメンタルに問題を抱える社員が増えていた」とも述べています。
4「ポストコロナの成長戦略」では、「新たな『インキュベーション・プラットフォーム』を確立する」として、近年、多くの経営者が「両利きの経営」という言葉を打ち出していることが紹介されます。これは、「既存事業の深耕」と「新規事業の探索」の両軸を同時並行的に進めるという戦略です。著者は、「多くの日本企業は『既存事業の深耕』には熱心だったが、『新規事業の探索』をうまく進めてきた企業は稀である。その理由のひとつとして、野中郁次郎先生(一橋大学名誉教授)が指摘する『オーバーアナリシス』『オーバープランニング』『オーバーコンプライアンス』があげられる。『過剰な分析』『過剰な計画づくり』『過剰な法律的縛り』という『3つの過剰』が、起業家精神を減退させ、過度にリスクを回避する動きにつながってしまっている」と述べています。
5「ポストコロナの人材戦略」では、「不透明な時代に必要なのは『個の突破力』」として、コロナ後の経営戦略において最も重要な柱は人材戦略であることを指摘し、著者は「日本企業は昭和、平成と続いた『人材についての考え方』を根本から変えなくてはならない。日本企業の高度成長を支えた終身雇用や年功序列、新卒一括採用といった考え方は、もはや通用しないばかりか、会社の競争力を削ぐものになってしまっている。コロナ後に日本企業が再生できるかどうかは、すべて人材にかかっている。有能な人材を確保し、活用できる会社だけが生き残る」と述べます。
ポストコロナの人材戦略のポイント2「『ミッションありき、結果志向』へシフトする」では、「『ミッション』で組織を動かす」として、著者は「ポストコロナの組織運営においてなにより大事なのは、1人ひとりの社員に与える『ミッション』(使命)を明確にすることである。会社が苦境を乗り越え、新たな成長を実現するためには、どのような『ミッション』を遂行しなければならないのかを、社員全員が自覚し、実践しなければならない」と述べています。
わが社も、かつての苦境時に社長に就任したばかりのわたしが新たなミッションを掲げて全社一丸となって業績回復に取り組んだ経験があるので、著者の意見に大賛成です。「ミッション」について、著者は「平時のときは、『ミッション』など意識しなくても、会社はなんとか回る。自分に与えられた目の前の『タスク』(任務)だけをやっていれば、それなりにやっていける。しかし、有事はそういうわけにはいかない。組織の上から下までが、自分に与えられた『ミッション』を自覚し、日々実践に努めなければならない」と述べます。
ポストコロナの人材戦略のポイント3「現場力を支える『ナレッジワーカー』の評価を高める」では、「現場力の重要性はますます高まる――『ナレッジワーカー』は代替性の低い、会社の財産」として、著者は「平時においては、並の現場力でも、なんとか持ちこたえられる。しかし、有事においては、現場力の高い会社でなければ生き残ることは難しい。現場力を支えるのは、『ナレッジワーカー』(知識労働者)である。現場での仕事に従事しながらも、知恵を出し、創意工夫しながら、粘り強く改善に取り組む」と述べています。
こうした泥臭い取り組みがあるからこそ、コストダウンや品質、サービスの改善が実現されるとして、著者は「日本企業の競争力の源泉が現場力であることは、ポストコロナにおいても変わることはない。一方、決められたことしかできない『マニュアルワーカー』の価値は、さらに小さくなるだろう。その多くは、今後ロボットやAIなどによって代替されていく。『ナレッジワーカー』は代替性の低い、会社の財産である。ロボットやAIが代替することができない『ナレッジワーカー』に対する評価を高め、報酬を高めていくことが不可欠である」と述べます。
第3章「コロナ後に、『仕事』はどのように変わるのか」の1「『食える仕事』『食えない仕事』とは何か」では、「『食える人』と『食えない人』の差は何か――『代替可能性』と『付加価値の大きさ』の二軸で分類できる」として、著者は、コロナ後において「食える人」と「食えない人」の差を読み解くには、「テクノロジーによる職業の代替可能性」と「人が生み出す付加価値の大きさ」(プロVSアマ)の二軸で整理するとわかりやすいだろうとして、ポストコロナの人材を次の4つに分類しています。
(1)「代替可能性」が低い職業で
「付加価値」が高い(プロ)人材
→ スター
(2)「代替可能性」が高い職業で
「付加価値」が高い(プロ)人材
→ サバイバー
(3)「代替可能性」が低い職業で
「付加価値」が低い(アマ)人材
→ コモディティ
(4)「代替可能性」が高い職業で
「付加価値」が低い(アマ)人材
→ ユースレス
2「『プロフェッショナルの時代』がやってくる」では、「『人が生み出す価値には歴然とした差がある』という現実を認める」として、ポストコロナの大変革に必要なのは、「新たな価値の創造」(Innovation)と「効率性の飛躍的向上」(Efficiency)の両輪であることを指摘し、著者は過去の延長線上にない不連続の『新たな価値の創造』と『効率性の飛躍的向上』の両方を早期に実現できなければ、日本企業はコロナとともに沈むだけである。『プロフェッショナル』とは、新たなレールを敷き、新たな車両を造る人たちのことである。そうした野心とエネルギーと高度専門性をもつ人たちこそが、いま求められているのである。『プロ化するビジネス社会』とは、『人が生み出す価値には歴然とした差がある』という現実を認める社会のことである」と述べています。
3「『プロ化するビジネス社会』で生き残るための処方箋」では、「あなたはいったい何の『プロ』なのか?」として、著者は「日本の大企業では、数年ごとに部署を異動し、ひととおりの経験を積む『ジェネラリスト』指向が強かった。こうしたローテーション人事は、いろいろな経験は積むものの、何のスペシャリティもない『中途半端なジェネラリスト』を大量に生み出したきわめて同質的な『中途半端なジェネラリスト』の大集団から、才能と運に恵まれたごく一部の人間が役員として登用された。それが、昭和の時代につくられた典型的な日本の経営モデルだった。しかし、コロナ後の大変革時に、『中途半端なジェネラリスト』が山ほどいても、会社にとっては何の役にも立たない」と述べています。
また、「『プロフェッショナル』の定義」として、著者は「自分が得意な分野、自分が興味ある分野、自分が経験を積んできた分野においては、ほかの人たちを凌駕する卓越した知見、スキル、実績をもつ人材こそが『プロフェッショナル』である。これからの経営においては、さまざまな分野、領域で『プロ』が求められる。『戦略のプロ』『マーケティングのプロ』『ITのプロ』『AIのプロ』『デジタルのプロ』『M&Aのプロ』『法務のプロ』『監査のプロ』など、高度専門性を磨かなければ、会社の中で力を発揮し、認められることはない」と述べます。
「プロ」として成功するポイント1「『会社』ではなく、『機会』で判断する」では、「『未成熟』『未完成』なものほど、プロにとっては魅力的」として、著者は「ビジネスの世界における『プロ』にとって大事なのは、『どの会社に勤めるか』ではない。『どの機会を選択するか』である。『プロ』は『機会』(opportunity)を求めて動く。自分の力が思う存分発揮でき、貢献できる『機会』こそが、最大のインセンティブなのである。だから、『プロ』は著名な会社、安定した大きな会社を好まない傾向が強い」と述べています。
「有名企業だから」「給与がいいから」などの一般的な尺度だけで、自分が身を置く場所を選ぶことはしないとして、著者は「もちろん、新規事業開発や海外展開など新たな分野への挑戦であれば、大企業であっても『機会』にはなりえるが、一般的にいえば、『出来上がった』大きな会社は、『機会』に乏しく魅力に欠ける。逆に、『出来上がっていない』発展途上の会社や事業は、『機会』の宝庫である。『未成熟』『未完成』なものほど、『プロ』にとっては魅力的だ」と述べます。
第4章「コロナ後に、『働き方』はどのように変わるのか」の1「『レスの時代』の幕開け」では、「『通勤レス』『出張レス』『残業レス』『対面レス』――私たちは『新たな選択肢』を手に入れた」として、コロナ・ショックは「レスの時代」の幕開けであると指摘し、著者は「デジタル化、オンライン化によって、さまざまな不要なものを『レス』(なくす、減らす)することができる。『ペーパーレス』『ハンコレス』は言うに及ばず、『通勤レス』(会社に行かない)、『出張レス』(意味のない出張はしない)、『残業レス』(不要な残業はしない)、『対面レス』(非対面で仕事をすます)など、『レス』できるものが多いことに私たちは気づいた」と述べています。
さらには、ビジネスパーソンにはつきものだった「転勤」のあり方もこれからは変わっていくだろうとして、著者は「これまでは辞令1枚で転勤を強要されるのがサラリーマンにとっては常識だったが、これからは社員が転勤の可否を選択する時代になっていく。そうなれば『転勤レス』も私たちは手に入れることができる。これからは『複数の選択肢』を賢く使い分けていく時代になる。それが『スマートワーク』である」と述べます。
2「どうすれば『生産性の高い働き方』ができるのか」では、「リモートワークに向いている人、向いていない人がいる――問題は、『業務』ではなく『人』」として、著者は、「リモートワークに向いている業務、向かない業務」の議論よりも、「リモートワークに向いている人、向かない人」をしっかりと見定めることが重要だと述べます。問題は「業務」ではなく「人」であり、しっかりと自己管理ができ、スーパーバイズ(監督・指導)なしに、自己完結的に業務を進めることができる技量と経験をもつ人であれば、リモートワークの効果はきわめて大きいですが、「自己管理力」が不十分で、スーパーバイズが必要な人は、リモートワークによってかえって生産性が下がるだろうと言います。
3「リモート時代における社内コミュニケーションの4原則」では、「『過剰管理』でもなく、『野放し』でもなく――部下が『自己管理』できるように上司が導く」として、著者は「『過剰管理』は部下のモチベーションを下げ、『野放し』は業務品質を著しく低下させるリスクを増大させる。リモートワークが大きな成果を生み出すために大切なのは、管理を強化することではなく、部下が『自己管理』できるように上司が正しく導き、適切な指導を行うことだ。上司が部下を管理するのではなく、部下が自らを『自己管理』できるように仕向ける。部下の『自立』を手助けするのが、ポストコロナにおける有能な管理者である」と述べています。
社内コミュニケーション術の原則2「経験値の高い人と低い人を『ペア』で組ませ、アドバイスする『メンタリング』がより重要になる」では、著者は「経験値の高い人と低い人を『ペア』で組ませ、必要に応じてタイムリーにアドバイスできる仕組みが不可欠である。アドバイスはオンライン上でも十分に可能だ。逆に、対面よりも本音を言いやすく、気楽に相談できるというメリットもある。一方、リモートワークを開始した企業の多くで、新たな課題も生まれている」と述べています。
オン・オフの切り替えができず、働きすぎに陥る社員や問題を抱え込んだまま孤立する社員が増えているとして、著者は「年次の近い先輩社員が、在宅勤務のちょっとしたコツや働き方のヒントをタイムリーに伝授することができれば、リモートワークのストレスを軽減できるはずだ。大事なのは、『誰が誰の面倒をみるのか』を明確にすることである。管理者である上司ではなく、気楽に話ができる身近な『メンター』の存在があれば、心強い。リモートワークという分散的な働き方を機能させ、組織全体の生産性を高めるためには、人と人とのつながりをしっかりと確保することが生命線である」と述べます。
社内コミュニケーション術の原則3「『ムダ話』や『雑談』をするための、インフォーマル・コミュニケーションの『場』をつくる」では、リモートワークによって失われてしまうものもあるとして、著者は「それはオフィスにおけるインフォーマル・コミュニケーションである。オフィスでの何気ない『雑談』、廊下ですれ違いざまの『立ち話』、タバコ部屋での『噂話』など、ちょっとした情報のやりとりがビジネスのヒントとなったり、人と人との垣根を取っ払う役割を担ってもいる」と述べます。まったく同感ですね。
そこで大事なのが、オンラインを活用した、「ムダ話」や「雑談」をするためのインフォーマル・コミュニケーションの「場」づくりであるといいます。著者は、「通常の業務上のやりとりではなく、『ムダ話』や『雑談』をするためだけの『場』をオンラインで設けることによって、人と人とのつながりが濃くなっていく。『オンラインランチ』や『オンラインおやつタイム』など、気楽に参加できるハードルの低いインフォーマル・コミュニケーションの『場』を意図的につくることが必要である」と述べています。
社内コミュニケーション術の原則4「定期的にオフライン(対面)で会うから、日常のオンラインが機能する」では、オンラインやリモートでは、人間の「機微情報」というものが見えないし、伝わらないとして、著者は「だから、最低でも月に一度はオンラインでの個人面談の機会を設けるべきだ。これは『自己管理力』の有無とは関係ない。むしろ、『自己管理力』の高い人材ほど、表面的にはうまくいっているように見えても、自分ひとりで問題を抱え込み、悶々とするケースは多い。オフライン(対面)でのやりとりがあるからこそ、日常のオンライン(非対面)は機能すると肝に銘じなければならない」と述べています。これも、まったく同感です。
4「働き方の自由度を高め、真の豊かさを享受する」では、「真の豊かさとは『経済的な豊かさ×精神的な豊かさ』――個を尊重し、人間らしく生きる社会に変える」として、著者は「会社にはさまざまなストレスが存在する。とりわけ『通勤』『残業』『人間関係』は、どの会社にも共通する3大ストレスである。ポストコロナの社会においては、これらを解消もしくは大きく軽減できる可能性がある。『デジタル化 → オンライン化 → リモートワーク』の流れが浸透、定着すれば、『通勤レス』『残業レス』『対面レス』は十分に実現可能だ。ポストコロナをきっかけに、私たちは個を尊重し、人間らしく生きる社会に変えなくてはならない」と述べています。
いくら会社が利益を上げ、内部留保を貯め込んでも、そこで働く人たちが疲弊し、暗い顔をしていたのでは、とてもいい会社とは言えないとして、著者は「平成の30年は、そんな会社が増えていった時代だった。私たちはコロナ・ショックを機に、その流れに終止符を打たなければならない。真の豊かさとは、『経済的な豊かさ』と『精神的な豊かさ』が共存するものだ。コロナがきっかけとなってこれから起きてくるだろうさまざまな働き方の変革は、私たちの『精神的な豊かさ』を高めてくれる可能性がある。『資本の論理』『会社の論理』ばかりがまかり通った時代から、『人間の論理』『個の論理』が通用する社会に変えていかなければならない」と述べています。このあたりは、拙著『心ゆたかな社会』(現代書林)の内容に大いに通用しています。
5「どうすれば『創造性の高い働き方』ができるのか」では、「デジタルの時代だからこそ、リアリズムが大事――大事なのは『誰と会うか』」として、著者は「デジタルの時代だからこそ、リアリズムが大事になる。人と対面で会うからこそわかること、現場に自ら行くからこそ見えることも多い。オンライン化やリモートワークの最大のリスクは、『つながっているつもり』『見えているつもり』『わかっているつもり』に陥ってしまうことである。いくら便利でも、やはり現場に行かなければ感じられないもの、人と対面で会わなければ見えてこないものは確実にある。『三現主義』(現地・現物・現実)など時代遅れと切り捨ててはいけない。五感で感じるリアリズムは、デジタルで代替することはできない」と述べています。
コロナ後の人材評価のポイント4「会社に『しがみつかない』人が評価される」では、どんな会社だって潰れる可能性があり、どんな仕事だって突然なくなる可能性があるとして、著者は「正社員だから安泰なんて言っていられない。国だっていつ破綻するかわからない。それが『VUCA』という時代である。本当に力がある人間は、会社にしがみつかない。だから会社も、しがみつかない人を評価し、登用する。会社にしがみついて、人生を棒に振ることが最も不幸なことである。コロナをきっかけに、私たちは会社に縛られない『脱会社』のマインドをもたなければならないのだ」と述べるのでした。
「おわりに――元に戻るな、大きく前に進め!」では、「歴史は70~80年サイクルで繰り返す――『コロナ革命』という大変革の真っただ中にいる」として、著者は「『歴史は70~80年サイクルで繰り返す』と多くの歴史学者が指摘する。日本の歴史をさかのぼれば、江戸時代の1787年に『天明の打ちこわし』が起きた。天明の大飢饉に端を発した民衆暴動が、江戸、大坂など主要都市で勃発し、国内は混乱を極めた。その81年後の1868年に、明治新政府が樹立され、日本は開国へと大きく舵を切った。さらにその77年後の1945年、第2次世界大戦は終結し、日本は終戦を迎えた。そして、終戦から75年たった2020年、私たちを襲ったのは未知のウイルスだった」と述べています。
この「目に見えない黒船」は、日本という国、日本企業、そして日本人が覚醒するまたとないチャンスでもあるとして、著者は「80年後には『コロナ革命』と呼ばれているかもしれない大変革の真っただ中に、私たちはいるのだ」と述べます。また、「日本人が陥っていた悪弊を一掃するチャンス」として、著者は「コロナ後に、私たちは元に戻ってはいけない」と訴えます。個人の幸せよりも組織が優先される「集団主義」。やってもやらなくても差がつかない「悪平等主義」。常に横と比較する「横並び主義」。責任を明確にしない「総合無責任体質」・・・・・・こうした悪弊を一掃することができず、わたしたちは「緩慢なる衰退」に陥っていたというのです。
著者は、「目に見えない黒船」が来襲したにもかかわらず、旧来の意識や常識、価値観を払拭することができなければ、この国が浮上することはないだろうと推測し、「私たちは元に戻るのではなく、大きく前に進まなければならないのだ」と強く訴えます。そして、著者は「『目に見えない黒船』は私たちに『もっと豊かになれ。もっと幸せになれ』いう問いかけをしてくれているように私には思えてならない。すべてが止まったからこそ見えてきたものを、私たちは大切にしなければならない」と述べるのでした。豊富なデータを示し、合理的な思考に貫かれながらも、本書には「ミッション」とか「幸せ」とか「精神的な豊かさ」などのキーワードが多々見られ、著者が人間尊重の経営に価値を置いていることがよくわかりました。もちろん、わたしも同じです。
2020年10月19日 一条真也拝


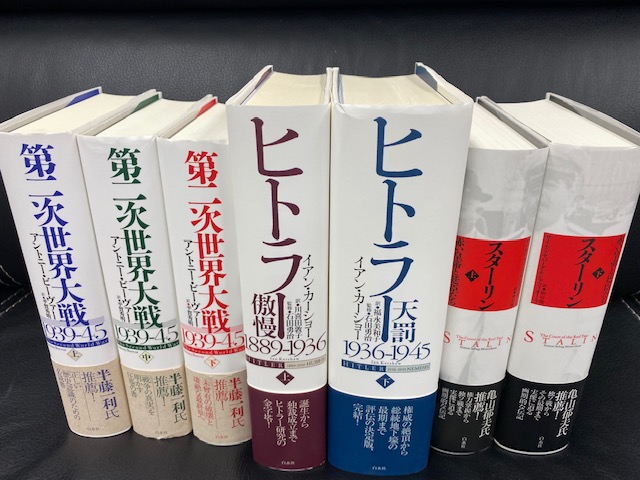









 カラオケ・スナックDANの前で
カラオケ・スナックDANの前で
























 『
『





