一条真也です。
『仕事と人生に効く 教養としての映画』伊藤弘了著(PHP研究所)を読みました。「日本一わかりやすい」映画講師として紹介されている著者は、1988年生まれ。愛知県出身。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程研究指導認定退学。現在は関西大学、同志社大学、甲南大学で非常勤講師を務めています。また、東映太秦映画村・映画図書室にて資料整理の仕事を行なっています。「國民的アイドルの創生――AKB48にみるファシスト美学の今日的あらわれ」(『neoneo』6号)で「映画評論大賞2015」を受賞。本書が初の単著です。

本書の帯
本書の帯には「こう見ればよかったのか!」「『東京物語』(1953)から『パラサイト』(2019)まで超戦略的シネマ鑑賞法」「佐藤優氏 楠木健氏 激賞」と書かれています。

本書の帯の裏
帯の裏には、「映画を通じて他人の人生を疑似体験できる。仕事と人生の幅を広げるための最良のツールが映画だ。」(作家・元外務省主任分析官 佐藤優)、「ほんと映画は教養の両輪。優れた読書論は多いが、優れた映画鑑賞論は希少だ。映画から教養を獲得するための待望の一冊。」(一橋ビジネススクール教授 楠木健)「仕事がデキるあの人も、映画を見ている。」と書かれています。
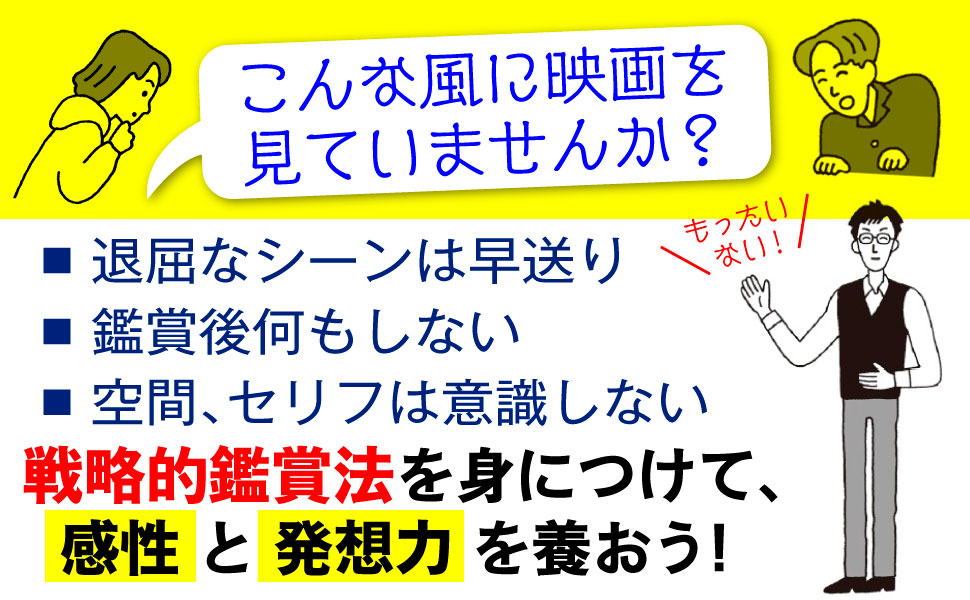
本書のカバー前そでには、「あの作品の知られざるエピソード&豆知識が満載!」「ヨーロッパでは溝口健二、ハリウッドでは黒澤明が愛される理由」「映画史に残るエジソンの功績と挫折」「『カメラを止めるな!』はなぜヒットしたかetc」と書かれています。

本書のカバー後そでには、「絶対にもう一度見返したくなる作品批評」「ヒッチコック『裏窓』に隠されたトリック」「『万引き家族』お風呂シーンの意図」「『ボヘミアン・ラプソディ』はフィクションだった!?」「小津安二郎の隠れた傑作『オナラ映画』etc」とあります。
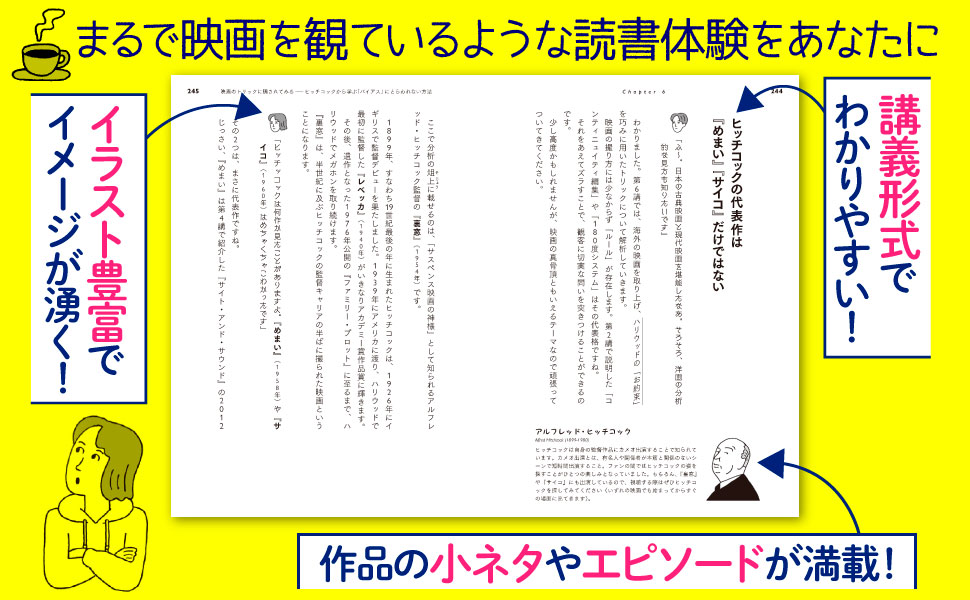
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
プロローグ 「トイ・ストーリー」は難しい?
第1講 映画を見たらどんないいことがあるか
――人生が劇的に変わる5大効用
●映画の効用1
感情の起伏を経験し、内省を深めることができる
●映画の効用2
他人の人生を疑似体験できる
◎INTERMISSION
『トイ・ストーリー』の大ヒットと
スティーブ・ジョブズの復活劇
●映画の効用3
異文化に触れることができる
●映画の効用4
知識を身につけるきっかけになる
●映画の効用5
人間としての魅力が増す
コメンタリー「ベラルーシ映画旅行記」
第2講 映画史を知ればビジネスの基本がわかる
――イノベーションと産業の歴史
コメンタリー「なぜ映画の日は『1日』なのか」
第3講 「日本の古典映画はなぜ世界で評価されるのか
――黒澤・溝口のすごい仕事術
コメンタリー「三船敏郎のデビュー秘話」
コメンタリー「ヌーヴェル・ヴァーグってなんだ?」
コメンタリー「隠れた名作『近松物語』」
第4講 絵画のように映画を見る
――人間の真実を描いた小津の『東京物語』
コメンタリー「小津映画に反映された『絵画性』」
◎INTERMISSION
小津安二郎の「グルメ手帖」
第5講 「映画で考える「家族のあり方」
――是枝裕和『海街diary』の視線劇
◎INTERMISSION
是枝映画の入浴シーン
第6講 映画のトリックに騙されてみる
――ヒッチコックから学ぶ
「バイアス」にとらわれない方
コメンタリー「眠る人を撮り続けた反映画」
◎INTERMISSION
映画の著作権保護期間
――『東京物語』の著作権は有効?無効?
第7講 映画の「噓」を知る
――人の心を動かす映像戦略
コメンタリー「高まる『応援上映』」
◎INTERMISSION
映画資料の保存と活用
最終講 あなたの感想が世界を変える
――情報を整理し、表現する力
コメンタリー「映画の引用について」
コメンタリー「『映画を見る会』を開こう」
◎INTERMISSION
そのアウトプットは誰のためのもの?
「あとがき」
「参考・引用文献」
付録 必見!!
世界と日本の名作映画111選/映画鑑賞ノート
プロローグ「『トイ・ストーリー』は難しい?」では、著者は「映画研究者=批評家としての立場から、私は『映画を意識的に見ることは、人間としての能力の底上げや人生の向上につながる』という確信を抱いています」と述べています。第1講「映画を見たらどんないいことがあるか――人生が劇的に変わる5大効用」の「映画は『オワコン』ではない」では、2020年はコロナ禍の影響もあって観客数、興行収入ともに2019年の55%弱に落ち込んでしまいましたが、そのような状況のなかでブログ「劇場版「鬼滅の刃」無限列車編」で紹介したアニメ映画が歴代最高の興行収入を記録したことは注目に値するとして、著者は「人々には依然として映画に対する強い欲求があり、機会があれば困難な状況下でも映画館に足を運ぶということが証明されたからです」と述べます。
映画鑑賞について、著者は「『映画館で見たい映画を見ること』は、実は依然として都市部に暮らす人間にのみ許された贅沢です(地方には近くに映画館のない地域がいくらでもあります)。しかし、映画ソフトのレンタルや動画配信サービスの充実によって、現代の日本に生きる私たちは、人類の歴史上もっとも映画にアクセスしやすい環境にあるのです(その一方で、戦前の作品を中心に、オリジナル・フィルムの消失によって二度と見ることのできない映画が大量に存在していることは銘記しておかなければなりません)」と述べています。
「映画館だからヒットした『カメラを止めるな!』」では、途中で離席されることをそれほど恐れなくてもいいというのが映画製作上の強みとなると指摘した上で、 ブログ「カメラを止めるな!」で紹介した2018年に日本中を席巻した上田慎一郎監督作品は、そうした強みを存分に利用した快作でした。著者は、「この作品は前半40分弱が後半のための伏線になっていて、その部分だけを見るとむしろ退屈なつくりになっています。ですが、映画館で本作を見た観客の多くは、その退屈な時間に耐えることができました。そして、映画を最後まで見ると退屈に思われた前半部分がいかに重要であったかが理解され、大きな満足(カタルシス)を得られる仕掛けになっているのです」と述べます。
「映画鑑賞の5大メリット」の映画の映画の効用1は、「感情の起伏を経験し、内省を深めることができる」です。 ブログ「君の名は。」で紹介したで紹介した新海誠監督のアニメ映画を例にしながら、著者は「人は、基本的に感情を揺さぶられることに快を覚える動物です。この場合の感情の揺らぎには、『楽しい』『興奮する』といったポジティブなものだけでなく、『怖い』『悲しい』といった一見するとネガティブなものも含まれます。人間は、涙を流すために進んでメロドラマ映画を見に行き、恐怖を感じるためにホラー映画を見に行く倒錯した生き物なのです。
また、著者は「映画という擬似現実を通して感情の起伏を経験できること。映画の特別な楽しみは、このようにも言うことができるでしょう。魂が揺さぶられるような大きな感情の変化の積み重ねは、あなたの人生をより彩り豊かなものにしてくれるはずです。誰しも、自分の実生活のなかで過度の恐怖や悲しみは感じたくないものです。ですが、映画というフィクションを通してであれば、リスクを負うことなくそうしたネガティブな感情に浸ることができます(感情の起伏それ自体がしんどいので映画自体『あるいは特定のジャンルの映画』を見るのが苦手だという人の存在は承知しています)」とも述べています。
「“スマホ疲れ”にも効果的」では、映画を見ることは、ある種のデジタルデトックスになると説明します。集中して映画を見ている間は、デジタル機器からの刺激をシャットアウトできるからです。著者は、「映画を見ている時間とは、自分の心の動きを見つめる時間にほかなりません。映画を通して感情の起伏を積み重ねていくと、自分の感情の振れ幅がわかるようになります。自分はどういう状況に喜びを見出したり、怒りを覚えたり、悲しみを感じたりするのか。つまりは、自分はどういう人間なのかを知ることにつながります。自らの感情の動きを知り、内省を深めてそれをコントロールできるようになること。このようにして磨かれていくのが『感性』と呼ばれるものの核心ではないかと私は考えています」と述べています。
「『一生』を2時間に凝縮」では、映画の効用2として、「他人の人生を疑似体験できる」が紹介されます。観客は一定の時間をかけて映画の登場人物たちに感情移入していき、彼らの人生を擬似的に生きながら感情の変化を味わえます。しかも、わたしたちは、複数の映画を見ることでいくつもの人生を擬似的に生きることができるといいます。映画のこの特質については、大の映画通としても知られた時代小説家の池波正太郎も著書『映画を見ると得をする』(新潮文庫)で、「すぐれた映画とか、すぐれた文学とか、すぐれた芝居とかというのを観るのは、つまり自分が知らない人生というものをいくつも見るということだ。もっと違った、もっと多くのさまざまな人生を知りたい・・・・・・そういう本能的な欲求が人間にはある」と書いています。池波はここで文学や芝居にも言及していますが、同時に「やっぱり映画には映画ならではというところがある」とも言っています。映画の特権として、「2時間かそこら」の「ごく短い時間で」、「まるで自分の隣の人がやっているように見せる」ことのできる点を挙げているのです。
また、文章から情景を想像するのが小説の醍醐味だとすれば、登場人物や街並みをすべて映像で見られるのが映画の特色であるとして、著者は「『罪と罰』は19世紀のサンクトペテルブルク(帝政ロシアの当時の首都)が舞台となっています。21世紀の日本に生きる私たちが、文章のみを手掛かりにして異国の過去の都市の情景を想像するのは困難ですが、すぐれた映画はきちんとした時代考証に基づいてそれを正確に再現してくれるのです。他の人の人生を2時間ほどの短時間で疑似体験できること。これが『なぜ映画を見るのか?』という問いへの池波正太郎なりの回答です」と述べます。
さらに、映画の真骨頂は、疑似体験した複数の人生を現実の自分の人生に持ち込むことができる点にあると指摘し、著者は「映画ではしばしば危機的な状況や困難な状況が描かれます。そうした状況を打開するために登場人物たちが見せる知恵や勇気、決断力は、分野を超えて私たちに多くのことを教えてくれます。切羽詰まった状況下では、冷静な主人公たちを際立たせるために、自己中心的な人物や愚かな行動に走る人物が描かれるものです。そうした振る舞いを反面教師とすることもできるでしょう。たくさんの人生を知っている人は、それだけ他者への想像力を働かせることができ、広い視野から物事を眺められるようになるのです」と述べています。
「お金がなくても海外に行ける」では、池波による映画の効用3として「異文化に触れることができる」が紹介されます。池波正太郎が、外国映画を見ることでそれぞれの国の国民性や文化、あるいは都市の構造に自ずと通じていくことができると述べたことを紹介し、著者は「池波の実体験として、曲がりなりにも40年間フランス映画を見続けていたおかげで、初めてパリを訪れた際にもまったくまごつくことなく、よさそうなお店や場所が感覚的にわかったという話を紹介しています。彼はフランス語がわからないにもかかわらずです。海外旅行の際に、初めて訪れる場所でスムーズに行動できて、より深く現地を堪能できるとなれば、たしかにお得ですよね」と述べます。
加えて、その国の映画を知っていることはそれ自体が「武器」になるとして、著者は「どの国にもかつて大ヒットした映画、国民の誰もが知っている有名な映画や俳優が存在するものです。そうした話題を提供することができれば、相手との心理的距離を一挙に詰めることができるでしょう。日本にきた外国人がジブリ作品のことを嬉しそうに話してくれたら、聴いているこちらも嬉しくなるのと同じことです」と述べるのでした。
「無知を知る」では、池波による映画の効用4として「知識を身につけるきっかけになる」が紹介されます。ウイルス感染の脅威、アポロ計画の実態、原発事故の現場、リーマン・ショックの背景など、映画は実に多彩な題材を取り上げることを指摘し、著者は「こうしたテーマを書籍や文献で学ぶのはもちろん重要なことですが、いきなり専門的な書籍に当たるのはハードルが高いですよね。その点、映画は視覚的なイメージから入ることができます。しかも多くの映画は一般的な観客の理解力をシビアに計算してわかりやすく作られていますので、無理なくその分野に馴染むことができます。非常にコスト・パフォーマンスがよいのです」と述べます。最後に池波による映画の効用5は「人間としての魅力が増す」です。映画を意識的に見続けると、池波は「粋な人間になって行く」「人間の『質』が違ってくる」などと表現しています。
第2講「映画史を知ればビジネスの基本がわかる――イノベーションと産業の歴史」の「ハリウッド誕生の背景」では、撮影された映画は当時どこで上映されていたのかという疑問について、著者は「最初期の映画は遊園地や地方巡業の見世物の1つとして上映されていましたが、その後の映画館文化への接続という点で重要なのは、ヴォードヴィル劇場と呼ばれる見世物小屋です。ヴォードヴィルは17世紀末にパリの大市に出現した演劇形式です。アメリカのヴォードヴィル劇場では、歌や踊り、手品やコントといった雑多なショーが上演されていました。ここに映画の上映がくわえられ、人気を得るようになります」と述べます。
映画の人気は、ヴォードヴィル劇場で従来行なわれていた各種パフォーマンスを凌ぐようになり、やがて映画の上映のみでプログラムを組む劇場があらわれます。こうして、1905年ごろに映画の常設館が生まれたのです。著者は、「アメリカに登場した初期の常設映画館は、入場料の5セント硬貨がニッケルであったことにちなみ、ニッケルオデオンと呼ばれます。入場料金の安価さからもわかるように、ニッケルオデオンは庶民のための娯楽場でした」と説明しています。
ここで、リュミエール兄弟ともに映画の発明者の1人とされるトーマス・エジソンが登場します。映画から得られる利益を独占しようと目論んだエジソンは、映画会社に対して特許をめぐる裁判を連発。1908年には、相次ぐ裁判で消耗した大手映画会社を抱き込み、モーション・ピクチャー・パテント・カンパニー(MPPC)という映画(カメラ)の特許を管理するトラストを結成します。本書には、「ニッケルオデオンの成功によって財を成していた経営者たちは、このエジソンの強権的な支配に反発します。高額な特許料の支払いから逃れるために、彼らが築いた新天地こそがハリウッドでした」と書かれています。
ハリウッドは映画製作に最適の場所でした。ニューヨークから遠く離れ、いざとなれば国境を越えてメキシコに避難することもできたこの土地は、くわえて気候にも恵まれており、映画撮影のための絶好の条件を備えていたのです。著者は、「アメリカ映画といえば真っ先に西部劇を連想する方も多いでしょうが、最初期につくられた西部劇はじっさいの撮影をアメリカ東部で行なっていました。ロサンゼルスに拠点を移したことで、本物の西部の景観を思う存分撮影することができるようになり、数々の名作が生み出されることになったのです」と述べています。
「ユダヤ系経営者に支えられたビジネス・モデル」では、初期のハリウッドを支えたのはユダヤ系の経営者たちであったとして、著者は「彼らによって1910~20年代にかけて設立された会社が、のちにハリウッドを支配する大会社へと成長していきます。パラマウント、20世紀フォックス、ワーナー・ブラザーズ、RKO、メトロ・ゴールドウィン・メイヤー(MGM)といったメジャー映画会社は、いずれもこの時期に設立されました。(前身となった会社を含みます)」と説明しています。
「『見せる』映画から『物語を語る』映画へ」では、初期の映画は異国の物珍しい風景や各種のパフォーマンス、好奇心を煽るような衝撃的な出来事など、それ自体が魅力を持つ対象を「見せる」ことに重点を置いていたことが紹介されます。映画研究者のトム・ガニングは、1906年ごろまでに製作された初期映画の特徴を「ショックや驚きのような直接的な刺激を強調」している点に求め、それらの映画を「アトラクションの映画」と名付けました。しかし、「見せる」ことを重視していた映画は、やがて「物語を語る」ことへとシフトしていきます。この時期に活躍した映画監督D・W・グリフィス(1875~1948)は、物語を効果的に語るための各種技法を洗練させ、映画を芸術の域に高めたと見なされています。物語映画の様式は、1910年代終盤までにほぼ確立していたと考えられています。今日の映画にまでつながる基礎的な技法は、すでにこの時代に編み出されていたということです。
映画研究者のデイヴィッド・ボードウェルは、1917年から60年までにハリウッドで製作された映画に特定のスタイルがあることを明らかにし、この時代の映画を「古典的ハリウッド映画」と呼びました。「効率的な語りとは」では、古典的ハリウッド映画の最大の特徴は、何よりもまず「物語を優先する」点にあることを指摘し、著者は「各種の技法は、効率的な語り(語りの経済性)を実現させるために動員されています。これによって観客を映画のなかに引き込み、我を忘れて物語に熱中する『夢の時間』を作り出すのです。登場人物の動機や物語の因果律(原因と結果)を明白に示し、ハッピー・エンドで締めくくること(あるいはあいまいさの残らない完結したエンディングにすること)も特徴の1つです」と延べます。
また、古典的ハリウッド映画の製作方法について、本書には以下のように書かれています。
「プロデューサー主導のもと、映画製作の各プロセスは徹底的に分業化され、スターやジャンルを最大限に活用した画一的な映画が量産されました。スタジオ・システム下における映画の大量生産の仕組みは、しばしばT型フォードの流れ作業(ライン生産方式)になぞらえられます。映画の文脈に経済性を求めるのは違和感があるかもしれませんが、観客は、経済的な語りのおかげで映画を楽しく見ることができるのです」
「歴史を学んだら『地図』を描く」では、映画史に限らず、歴史を知るということは、自分の現在の立ち位置を確かめることにつながると指摘されます。歴史家のE・H・カーは、「歴史とは現在と過去との間の尽きることを知らぬ対話」であると述べました。著者は、「過去の出来事を通して現在を知り、また未来を見通すことができるのです。それは、よりよく生きるための指針ともなるでしょう。私は、歴史は地図に似たところがあると考えています。自分がどこから来て、どこに向かっているかを教えてくれるのが地図であるとすれば、やはり歴史にも同じような機能を見出すことができるのではないでしょうか」と述べています。
◎INTERMISSION「『トイ・ストーリー』の大ヒットとスティーブ・ジョブズの復活劇」では、「ピクサーの躍進とジョブズの凱旋」として、著者は「ピクサーでの華々しい成功を手に、ジョブズは業績不振に陥っていたアップルに復帰し、暫定CEOに就任して辣腕を振るうことになります。その後、iPodやMacBook、iPhone、iPadといったヒット商品を世に送り出したのはみなさんもご存知のとおりです。ハードウェアの販売という当初の思惑は外れてしまったものの、ジョブズがピクサーのアニメーション制作技術を信じて赤字時代を支え続けていなければ、その後の復活やそれに続くヒット商品の連発も起こらなかったかもしれません。『トイ・ストーリー』の成功は、文字通り世界を変えたのです」と書いています。
第3講「日本の古典映画はなぜ世界で評価されるのか――黒澤・溝口のすごい仕事術」の「よく見ることは、よりよく生きること」では、小津安二郎の『お早よう』(1959年)の中のシーンが「大人たちの形式的なあいさつや紋切型の世間話を無駄だと切り捨てる子どもたちを前にして、彼らに英語を教えている男性登場人物(佐田啓二、中井貴一のお父さんです)は次のように言うのです。『でも、そんなこと、案外余計なことじゃないんじゃないかな。それ言わなかったら、世の中、味も素ッ気もなくなっちゃうんじゃないですかねぇ。僕ァそう思うなァ』」というふうに紹介されます。「無駄があるからいいんじゃないかなァ、世の中――」「僕ァそう思うなァ」というこのシーンを見返すたびに著者は言いようのない感動に襲われるそうで、「人間社会の真実を鋭く言い当てた名場面」と述べています。
 「一条真也の映画館」TOPページ
「一条真也の映画館」TOPページ
わたしは、日々、多くの映画を観て、その感想をブログに書き、さらには「一条真也の映画館」にレビュー記事を掲載しています。なぜ、映画について人は文章を書かずにいられないのか。著者の大学院修士課程時代の指導教員である映画研究者=批評家の加藤幹朗は、ある研究書の「あとがき」に、「映画について書く暇があれば、映画を見に行ったほうがよいというひとがいるかもしれない。しかしわたしは映画をもう一度見るために書く。書くことは、よりよく見ることだからである」と書いています。著者はこの考え方に全面的に同意し、「もっと言えば、『書くこと』『よりよく見ること』は、『よりよく生きる』ことと地続きではないかと思います。私はおそらく、映画をよく見てそれについて書くことが、よりよく生きることにつながると信じているのです。そうして書かれたものが、読んでくれた誰かにほんの少しでも気づきを与えて、その人の人生を豊かにすることができたとしたら、これに勝る喜びはありません」と述べています。わたしも、著者とまったく同じ気持ちです。
「小津と黒沢の意外な関係」では、黒澤の自伝『蝦蟇の油 自伝のようなもの』(岩波書店)の内容が紹介されます。同書には、検閲官たちからいかに的外れな批判を浴びせられ、それに対して黒澤がどれほど腹を立てたかが克明に記述されています。黒澤が自身のデビュー作である『姿三四郎』(1943年)の検閲試験に業を煮やして席を立とうとしたとき、小津が立ち上がって「百点満点として『姿三四郎』は、120点だ! 黒澤君、おめでとう!」と言って合格が決まったそうです。著者は、「小津は50年代の黒澤作品について批判的な言葉を口にするようになりますが、黒澤はのちのちまでこのときの小津への感謝を忘れなかったようです。小津の『一声』がなければ、黒澤映画は日の目を浴びなかったかもしれません。日本映画の『黄金世代』はこうした巨匠たちの切磋琢磨とリスペクトのなかで醸成されたとも言えます」と述べています。
「ヨーロッパは溝口、ハリウッドは黒澤がお好き」では、総じて溝口健二がヨーロッパ、とくにフランスのシネフィル(熱心な映画愛好家)に受け入れられる傾向にあり、それに対して黒澤明はハリウッドで高い評価を得たことを指摘し、著者は「これにはヌーヴェル・バーグが掲げていた『作家主義』という戦略も大いに関わってきます。溝口のような独創的なスタイルを持った映画は彼らの理念に合致していたと言えるでしょう。一方、西部劇の神様ジョン・フォードを尊敬していた黒澤の映画には、ハリウッド映画的な要素が色濃く組み込まれていました。このことは、当のハリウッドの映画人たちに親しみを抱かせたと考えられます。あるいは、一見して娯楽性の高い黒澤作品に映画の本流を見たのかもしれません」と述べます。
第4講「絵画のように映画を見る――人間の真実を描いた小津の『東京物語』」では、一生をかけて付き合い続けることのできる映画との出会いはそうそうあるものではありませんが、そうした作品と出会えた人は幸福であるとして、著者は「そんな映画と出会うと、それまでとは世界の見え方が変わってきます。心の拠り所となるような作品の存在は、その人を強くしてもくれます。私の場合は、それが小津映画でした。ぜひみなさんにも『運命の1本』と出会い、その映画について考え続ける幸福な人生を経験してほしいと思います」と述べています。小津映画といえば、似たようなテーマが繰り返し描かれるのも特徴で、『晩春』『麦秋』『秋日和』『彼岸花』『秋刀魚の味』はいずれも「娘の結婚」をめぐる話であることが紹介されます。
「小津映画が描く普遍的な人間の姿」では、ゆるやかに崩壊へと向かう家族の日常を描いた小津の映画は、人間の普遍的な姿を映していたのかもしれないとして、著者は「1950年代当時、黒澤や溝口の時代劇が海外で脚光を浴びるなか、あまりに日本的な生活を描いていた小津のホームドラマが国際映画祭に出品されることはほとんどありませんでした。しかし、サムライやニンジャには興味を惹かれないという外国人であっても、その人生において「家族」と無縁であることはまずありません」と述べています。小津に私淑しているドイツのヴィム・ヴェンダース監督は、『東京画』(1985年)というドキュメンタリー映画の冒頭で「小津の作品はもっとも日本的だが国境を越え理解される。私は彼の映画に世界中のすべての家族を見る。私の父を、母を、弟を、私自身を見る。・・・・・・小津の映像は20世紀の人間の真実を伝える。われわれはそこに自分自身の姿を見、自分について多くのことを知る」と語りました。
第5講「映画で考える『家族のあり方』――是枝裕和『海街diary』の視線劇」の「批判的思考力を磨く」では、「批判」はたんに悪口を言うことではないことが訴えられます。この言葉の第一義的な意味は「物事に検討を加えて、評価・判定すること」であり、そこには良い点を見つけることも含まれます。「批評」もこれとほぼ同じ意味をもつ言葉です。著者は、「映画は私たちの生きる同時代の社会を反映する鏡です。映画の流行を追うことは、時代の潮目を見極める能力を鍛えることにつながるでしょう。話題の新作映画を見ることで世の中の流行にキャッチアップしつつ、批判的思考力を磨いていけば、刻々と移り変わっていく社会情勢のなかで確固とした存在感を発揮できるようになるはずです」と述べています。
「是枝作品が問いかけるテーマ」では、ブログ「海街diary」で紹介した日本映画が取り上げられ、「『海街diary』では、母親の違う四女(父親は3人の姉たち家族を捨てて四女の母である女性と家を出た人物です)がそのことに負い目を感じつつ、三姉妹と正真正銘の家族になっていく過程が描かれていくのですが、この映画に見られる「家族にとって大事なのは血のつながりなのか、それともともに過ごした時間や思い出なのか」という問いは、是枝作品にしばしば登場する重要なテーマです。赤ん坊の取り違えを描いた『そして父になる』(2013年)は、このテーマに正面から切り込んだ作品でした。『万引き家族』はまさに血のつながりのない家族の物語でしたし、代表作の1つである『誰も知らない』(2004年)は全員父親の違う兄弟姉妹たちの話でした。また、『歩いても 歩いても』(2008年)をはじめとして再婚相手の連れ子という設定もよく見られます」と書かれています。
「是枝裕和と小津安二郎の共通点」では、是枝裕和はしばしば小津の影響を指摘される監督であるとして、著者は「是枝自身は家族をテーマにしている作品が多いからといって、それだけで安易に小津と比較されることにうんざりしているようです。ただ、私が見る限りでは、登場人物の視線を一致させたりずらしたりすることによってその関係性を描き出す点は2人の監督に共通しているように思います」と述べます。また、「フラッシュバック(回想シーン)を用いない点も両者に共通しています。小津も是枝も、登場人物の思い出はすべて会話のなかで処理していきます。一般的な映画であればそこから回想シーンが始まりそうな場面であっても、2人の映画ではフラッシュバックの使用が厳に禁じられているのです。2人の監督は、記憶というものは客観的な映像によって安易に提示できるようなものではないと考えているのでしょう」と述べます。
ブログ「小津安二郎展」にも書きましたが、わたしは小津安二郎の映画が昔から大好きで、ほぼ全作品を観ています。小津の作品には、必ずと言ってよいほど結婚式か葬儀のシーンが出てきました。小津ほど「家族」を描き続けた監督はいないと世界中から評価されていますが、彼はきっと、冠婚葬祭こそが「家族」の姿をくっきりと浮かび上がらせる最高の舞台だと知っていたのでしょう。小津の後継者と見られている是枝監督の「海街diary」には葬式のシーンが登場します。著者は、「葬式とは、参列者の視線がいっせいに遺影へと注がれる儀式にほかなりません。序盤に登場した三姉妹の写真に四女の居場所はありませんでしたが、直接関わりのあった二ノ宮の遺影には彼女なりに思うところがあったはずです」と述べています。
第7講「映画の『噓』を知る――人の心を動かす映像戦略」の「『ボヘミアン・ラプソディ』はフィクション?」では、 ブログ「ボヘミアン・ラプソディ」で紹介した音楽映画が取り上げられます。クイーンのフレディ・マーキュリーの人生を描いた実話映画と思われているこの作品にじつは多くのフィクションが混ざっていることを指摘し、著者は「映画というのは、ときに嘘によって真実以上に真実らしさを描き出すことのできるメディアであると指摘し、著者は「『嘘』という言葉は、一般的にはネガティブな印象を与えるかもしれません。ですが、私たちの文化は嘘と真実が曖昧に混じり合って成立しています。また、だからこそこれほどの豊かさを獲得しているのです。嘘を嘘であると知りながら、それでもなおその嘘と軽やかに戯れるすべを知っている人は、成熟した精神の持ち主ではないかと思います」と述べています。
最終講「あなたの感想が世界を変える――情報を整理し、表現する力」では、小津の「彼岸花」(1958年)に関する著者のツイートがバズったことを紹介。この映画では、お嫁に行く娘(有馬稲子)とそれを送り出す母(田中絹代)が茶の間で語り合うシーンがあるのですが、母は結婚指輪をしていますが、未婚の娘はしていません。また、画面に写っているグラスの中の液体や皿は女優の手と同じ高さに調整されていることを指摘し、著者は「この場面に見られるグラスや皿の高さの統一は、女優の手のための空間を用意し、指輪の有無を際立たせる働きをしているのではないかというのが私の解釈です。つまり、小道具の高さを利用して観客の視線を自然に女優の手元へと誘導しているわけですね。その手元の対比を通して、最終的には映画のテーマである親世代と子ども世代との価値観(結婚観)の対立にまで議論を展開していきました」と述べています。
さらに「彼岸花」について、著者は「映画の公開当時はちょうど見合い結婚と恋愛結婚の比率が逆転する直前に当たっており、自分たちと同じように娘も親の認めた相手と見合い結婚をして当然だと思っている父親と、自分の結婚相手くらい自分で見つけて何が悪いと考える娘の価値観が衝突しているのです」と述べるのでした。この見方には、心底感服しました。本書から、わたしは多くを学びました。何よりも、著者の映画に対する深い愛情に感銘を受けました。もうすぐ上梓する拙著『心ゆたかな映画』(現代書林)を書く上で非常に参考になったことを告白するとともに、最高の映画入門として広くオススメいたします!
2022年8月11日 一条真也拝




