一条真也です。
『戦国武家の死生観』フレデリック・クレインス著(幻冬舎新書)を読みました。「なぜ切腹するのか」というサブタイトルが付いています。著者は1970年、ベルギー生まれ。国際日本文化研究センター教授。専門は戦国文化史、日欧交流史。著書に『オランダ商館長が見た 江戸の災害』(講談社現代新書)、『ウィリアム・アダムス 家康に愛された男・三浦按針』(ちくま新書)、『戦乱と民衆』(共著、講談社現代新書)、『明智光秀と細川ガラシャ 戦国を生きた父娘の虚像と実像』(共著、筑摩選書)などがあります。

本書のカバー表紙には、日本の城の前に立つ著者の写真が使われ、「エミー賞『SHOGUN 将軍』時代考証家・衝撃の一冊」「破天荒な、戦国日本人のリアル」と書かれています。
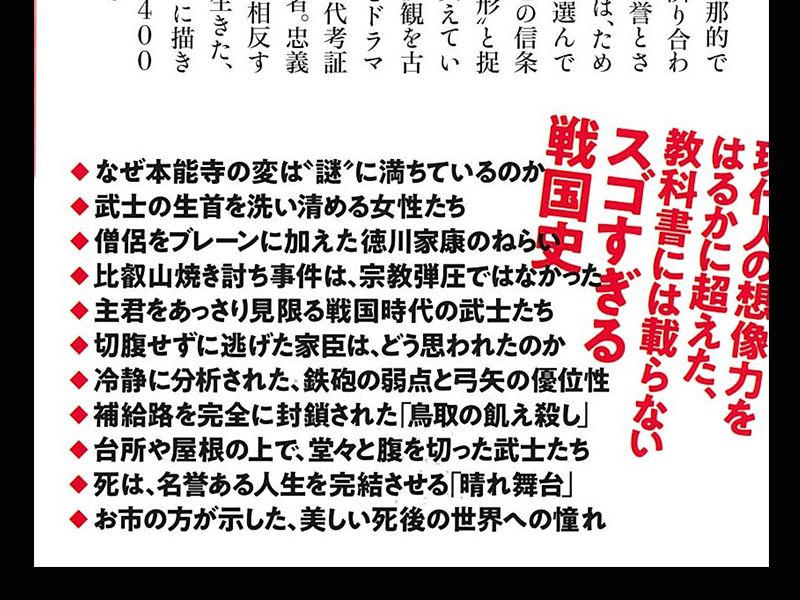
また、帯の裏には「現代人の想像力をはるかに超えた、教科書には載らないスゴすぎる戦国史」として、以下の目次抜粋が並んでいます。
◆ なぜ本能寺の変は謎に満ちているのか
◆ 武士の生首を洗い清める女性たち
◆ 僧侶をブレーンに加えた徳川家康のねらい
◆ 比叡山焼き討ち事件は、宗教弾圧ではなかった
◆ 主君をあっさり見限る戦国時代の武士たち
◆ 切腹せずに逃げた家臣は、どう思われたのか
◆ 冷静に分析された、鉄砲の弱点と弓矢の優位性
◆ 補給路を完全に封鎖された「鳥取の飢え殺し」
◆ 台所や屋根の上で、堂々と腹を切った武士たち
◆ 死は、名誉ある人生を完結させる「晴れ舞台」
◆ お市の方が示した、美しい死後の世界への憧れ
カバー裏表紙には、以下の内容紹介があります。
「戦国時代の武士たちは、刹那的で激しく、常に死と隣り合わせで生きていた。合戦での討死は名誉とされ、主君の死や敗戦の際には、ためらうことなく自ら切腹を選んでいる。命より家の将来や社会的立場を重んじ、死を〝生の完成形〟と捉える死生観が、その覚悟を支えていたのだ。こうした戦国独特の価値観を古文書から読み解き、その知見をドラマ『SHOGUN 将軍』の時代考証に存分に活かした歴史学者が、戦国武士の生きざまを徹底検証。忠義と裏切り、芸術と暴力――相反する価値観の狭間で気高く生きた兵たちの精神世界を、鮮烈に描き出す一冊」
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「はじめに」
序章 なぜ本能寺の変は“謎”に満ちているのか
第一章 アナーキーな社会を生きた人々と戦国の思想
第二章 武将たちの激しい信仰と宗教戦争
第三章 不安定な主従関係と戦国の忠義
第四章 足軽と鉄砲が変えた戦国の合戦
第五章 戦国時代の切腹と武士の名言
「おわりに」
序章「なぜ本能寺の変は“謎”に満ちているのか」の「戦国の気風から読み解く本能寺の真相」では、戦国の武将たちは、江戸時代の武士と多くの点で異なっていたことが指摘されます。たとえば、主従関係です。戦国時代は社会構造そのものが流動的であったため、江戸時代に比べて主従関係も不安定でした。江戸時代のように、主家や主君との関係性が倫理観や規範意識によって維持されていたのではなく、主君に対する個人的な情愛や信頼感が重視されていたとして、著者は「本能寺の変の一報が届いたとき、藤孝が信長から受けた恩を理由に出家を決意したのは、戦国時代の武将らしい判断といえます」と述べています。また、各地で武力衝突が頻発していた戦国時代の人々にとって、死は決して他人事ではなく、日常の一部であったことも見逃すことができないといいます。
武将たちは信仰心が篤く、刹那的でもあり、感情に忠実でした。打算的かと思えば、惚れ込んだ相手には命まで捧げてしまうほど純粋な一面も見られ、そうした本能的な多面性が戦国の気風の本質であったと考えられます。本能寺の変は、まさに戦国の激しい世相ゆえに起きた事件と見るべきであるとして、著者は「したがって本能寺の変とは、野心に突き動かされた光秀による突発的な事件ととらえるべきではないかと、私は考えます。政治的な背景はなく、信長が見せた一瞬の隙を見逃さなかった光秀による下剋上と理解するのが、自然な解釈ではないでしょうか。事件に計画性がなかったことは、ほかならぬ光秀自身が書状のなかで吐露しています」と述べるのでした。
第一章「アナーキーな社会を生きた人々と戦国の思想」の「男女とも胡坐か立膝で座る」では、戦国時代はよく江戸時代と混同されることが指摘されます。テレビや映画などの時代劇の舞台が圧倒的に江戸時代に集中していることが理由と考えられます。それらの視聴者の多くが江戸時代の武士像に慣れ親しんでいるからこそ、時代区分としては直前、戦国時代の武家についての誤解や錯覚が、ほかのどの時代よりも多く見られるのではないかとして、著者は「たとえば、戦国時代の人々の作法です。日本人の座り方は、古来、正座が定番であったと思われがちですが、正座が広く社会に広まったのは江戸時代以降です。正座という言葉も、一般化されたのは明治期であったという見解が定説となっています」と述べています。
とはいえ、戦国時代にも正座に近い座り方は存在していました。その場合、膝と足指の先を床面につけて尻は踵に乗る「跪座」が一般的でしたが、時折、足の甲を床面につける記述も史料に見られます。戦国時代、武士の日常的な座り方は胡座が一般的でした。また、いざというときに素早く立ち上がることができるように、立膝や片膝立ても好まれました。著者は、「武士たちが跪座や正座のような座り方にあらためるのは、主君との対面の際など、貴人に対する儀礼が求められる場面くらいでした。また、同格の武家との対面では、客と主人が最初は互いに跪座で礼を示した後、共に姿勢を崩すのが通例でした。換言すれば、地位の高い人物が正座にあらためなければならない場面はかぎられており、家臣との謁見の場で正座をする主君という構図は、基本的にはあり得ない状況と考えてよいでしょう」と述べます。
「武芸だけでなく、文化的教養も求められた戦国の武将たち」では、「歌連歌乱舞茶の湯を嫌ふ人 そだちのほどを知られこそすれ」という和歌が紹介されます。和歌、連歌、能楽、茶の湯といった芸道に優れていなければ、武士として失格であるという意味です。茶の湯は基本的に、戦国武士の人間関係と密接に関わっていました。迎える側と訪問者がいて初めて茶の湯が成立します。戦国武士はよく仲間を訪問し、そのおもてなしとして茶の湯が発展したと考えられます。また、能楽も武将たちの間で大人気でした。ただ観るだけでなく、自分で舞うことが重視されました。細川幽斎・忠興父子が能を演じた記録は、数え切れないほど残されています。秀吉も能にのめり込み、自分が主人公として描かれる演目を複数作らせました。これらは「太閤能」と呼ばれています。
「武将たちが最も愛した和歌の世界」では、武将たちにとって最も特別な文芸は和歌であったことが指摘されます。和歌は、この世の儚さを表現するのにぴったりの媒体だったとして、著者は「武士たちは熱心に和歌を詠みました。仲間との歌合や連歌会もあれば、1人でも創作しました。出陣する前にも、そして死ぬ直前にも歌を詠みました。当時の史料を見ると、必ずといってよいほど和歌が登場します」と述べます。戦国史研究の第一人者である静岡大学教授の小和田哲男氏によれば、和歌や連歌は戦国武将たちの教養として欠くべからざるものであったといいます。加藤清正などは、武士があまりに和歌・連歌に熱中してしまうと、本業である「武」の方がおろそかになってしまうことを警戒していたぐらいでした。北条早雲などは、「歌道を心得ていれば、常の出言に慎みがある」と述べています。歌は五・七・五・七・七の三十一文字、連歌は五・七・五の上の句と、七・七の下の句の連続で、いずれにしても、きわめて短い言葉で自分の思いを表現しなければなりません。早雲は、そうした鍛錬が、日常、何気ない言葉にもあらわれるとみていました。
歌心のあるなしで、その人の品格のあるなしがわかり、また、情のあるなしもそこに反映されるという考え方は昔からありました。徳川家康は何人かの家臣たちと雑談していて、話が源義経のことにおよんだとき、「源義経は生まれつきの大将ではあるが、歌学のなかったことが大きな失敗だった」と言い出しました。家臣たちは、「義経に歌道がなかったというのは聞いておりません」と家康に言うと、家康は、「義経は、“雲はみなはらひ果たる秋風を松に残して月を見るかな”という古歌の心を知らなかった。そのために身を滅ぼした。平家を少しは残すべきだったのだ」と答えたといいます。家康は自分で詩作をするのは苦手だったようですが、よく勉強はしていたと思われます。そして、古歌をただ教養として学んでいたのではなく、自身の生活態度、さらに政治・軍事にも応用していたことがわかります。家康にとって歌学は、生きた学問だったわけです。また、連歌の場合はもう一つの意味があり、「出陣連歌」といって、合戦の前に連歌会を開き、詠んだ歌を神社に奉納し、戦勝祈願をするためにも必要でした。「連歌を奉納して出陣すれば、その戦いに勝つことができる」との信仰があったのです。
その家康が徳川幕府の思想的支柱としたのが儒教でした。「武士の役割を再定義した江戸時代の儒教」では、著者は以下のように述べています。
「江戸時代に受容された儒教を注意深く検証すると、次の点で巧みにアレンジが加えられていることを指摘することができます。まず、『忠』と『孝』については、中国では親への孝が重視されていたのに対し、武家社会では主君への絶対的な忠節を優先させ、忠を重んじる思想へと変容しています。また、『五倫』(君臣・父子・夫婦・長幼・朋友)の解釈においても君臣関係を最上位に置き、血縁関係よりも優先することで、大名と家臣の関係を正当化し、家臣団内部の階層秩序を維持する理論的基盤としました」
さらに著者は、「『修己治人』(修養に励んで徳を積み、その徳によって人々を感化して世を治める)という思想は、武士が行政官として実務能力の向上に取り組む根拠となり、家臣に対する教育や指導の道徳的指針としても機能しました。『礼』の概念は武家社会における儀礼や作法として具体化され、登城の際の公式な場面での振る舞いや日常的な礼儀作法の規範化に活用されました」と述べます。その表れの一例として正座が正式な座り方として一般化を遂げたのです。これらの儒教思想は武士の日常生活にも浸透し、質素倹約の奨励や学問修養の重視といった具体的な行動指針として機能し、武士に道徳的模範としての自覚を促しました。
第二章「武将たちの激しい信仰と宗教戦争」の「武将たちは本当に神仏を利用したのか」では、これまで、儒教的な武士像の延長線上に描かれてきた戦国武将の姿には合理主義者としての色合いが強く、信仰心が政治的な行動や判断におよぼした影響については見過ごされがちだったことが指摘されます。むしろ近年は、武将たちが勢力拡大のために宗教を利用していたとする解釈も見られる指摘しながら、著者は「しかし、その当時の人々にとって、神仏は『利用』できるものだったのでしょうか。じつは、そうした見方そのものが、宗教に対して一定の距離感を保つようになった現代的な発想ではないかと私は考えます。戦国武将にとって、信仰とは日常の一部であり、特別な行為ではありませんでした」と述べます。
たとえば、無神論者であったといわれる織田信長ですら、永禄3(1560)年の桶狭間の戦いの際には熱田神宮で戦勝を祈願してから出撃しています。豊臣秀吉は京都に日本最大の大仏を造立し、徳川家康は「厭離穢土 欣求浄土」という浄土宗の言葉を自身の旗印に採用していました。著者は、「武将たちの多くは寺社の有力な庇護者であり、合戦の際には護符や小さな仏像を身につけて戦場に臨むのがつねだったのです。現代を生きる私たちが空気の存在を疑わないように、彼らは神仏の存在を疑わなかったはずです。戦国時代の世界観において、神仏は日常にあまねく存在しており、合戦の勝敗はもちろん、政治や文化、私生活においても、彼らはあらゆる場面に神仏の意思を感じ、その導きを求めていたと考えられます」と述べます。
「修行僧のように求道的な上杉謙信の日常」では、戦国武将の中でも、最も熱心な宗教実践者の1だった越後の上杉謙信が取り上げられます。有名な僧形の肖像画からもわかるように、彼は武家の当主でありながら信仰心の篤い求道者でもありました。謙信の宗教的実践は多岐にわたりました。彼は宗派にこだわることなく、さまざまな仏や神々を信仰し、日常的に祈りを捧げていました。元亀元(1570)年12月に認めた「看経の次第」には、阿弥陀如来、千手観音、摩利支天、日天などへの看経を詳細に記し、それぞれに真言の唱和や経典読誦の回数まで定めていたとされています。
特筆すべきは、謙信が禅宗と真言宗の両方に深く親しんでいた点です。幼少期から林泉寺の天室光育や後の住持益翁宗謙といった禅僧たちと親交を深める一方で、永禄元(1558)年ごろからは高野山無量光院の清胤を師と仰ぎ、真言の奥義を学んでいました。晩年の天正2(1574)年12月19日には剃髪して法体(出家姿)となり、清胤を師として仏法灌頂の儀を行い、僧侶の最高の位である法印大和尚となりました。著者は、山田邦明著『上杉謙信』を参照しながら、「謙信は春日山城内の大乗寺で日々看経に励み、戦に臨む際にも祈りを欠かしませんでした。同時に、領内の寺院(宝幢寺・至徳寺・林泉寺・転輪寺・広泰寺など)の僧侶たちにも戦勝祈願を命じ、特に頸城郡の「能化衆」と呼ばれる高位の僧侶6人には摩利支天法という護摩を執行させるなど、信仰を通じた戦勝への祈りを重視していました」と説明します。
「自分と生き写しの不動明王像をつくらせた武田信玄」では、謙信のライバルであった信玄も熱心な宗教者であったことが紹介れます。大永元(1521)年、甲斐守護武田信虎の嫡子として誕生した信玄は、天文10(1541)年、重臣たちとともに父を駿河へ追放し、家督を継ぎました。その後、信濃や北関東に勢力を拡大し、永禄2(1559)年に出家しています。著者、「信玄は、武田家の菩提寺であった臨済宗妙心寺派の恵林寺を手厚く保護し、お抱えの祈願所として重視しました。そのことは、信玄が同寺に安置した不動明王像が強く示唆しています。その不動明王像は俗に『武田不動尊』と呼ばれ、信玄がみずからを模して等身大でつくらせたと伝わります」と説明しています。
信玄は武田家の氏神である諏訪大社を崇敬し、社殿の造営や社領の寄進を行いました。武田軍といえば、『孫子』軍争篇から受容されたいわゆる「風林火山」(其疾如風 其徐如林 侵掠如火 不動如山)の軍旗がよく知られていますが、信玄は軍の先頭に「南無諏方南宮法性上下大明神」という諏訪神号旗を掲げさせていました。そして自身の兜には、小さな諏訪明神像を飾りつけています。神仏の加護を得るため、彼が懸命に手を尽くしていた様子が浮かび上がってきます。そうした信玄の信仰心に関して、興味深いことに、イエズス会士のルイス・フロイスが1573年4月30日付の書状の中で「信玄は剃髪して坊主となり、つねに坊主の服と数珠を身につけていた。1日に3回、偶像を祀るために、戦場には600人の坊主を同伴させている」と書いています。
「僧侶をブレーンに加えた徳川家康のねらい」では、徳川家康に言及します。元亀3(1573)年、三方ヶ原の戦いで信玄に大敗北を喫しながら、その後は信玄を尊敬していたといわれる家康も、篤い信仰心を持っていました。戦国武将たちの多くが禅宗に傾倒する中、浄土宗に帰依していた家康は少数派といえます。彼は旗印に「厭離穢土 欣求浄土」という浄土宗の言葉を掲げて合戦に臨みました。これは「穢れたこの世を離れ、来世は美しい仏の世に生まれたい」という意味の言葉で、源信の『往生要集』に由来します。著者は、「家康の宗教観は、彼が生涯、僧侶たちとの多彩な親交を重ねたことからもうかがうことができます。とりわけ、晩年の家康が天海と以心崇伝をブレーンとして登用していたことは注目に値します」と述べています。
家康は戦国武将のなかでもっとも朱子学に傾倒していましたが、晩年においては仏教の宗論にのめり込むようになりました。この時期、数多くの僧を召し、法門を聞く機会が著しく増加します。確認できる限りでは、晩年の3、4年のうちにじつに30回を超える聴聞の機会を設けています。またこの時期の家康は、戦国に生まれ、多くの人を殺した罪滅ぼしとして、日課に6万遍もの念仏を唱えていたといいます。これは第2代将軍秀忠の妻お江に宛てた慶長17年2月25日付の書状に記されています。
「傅役の供養のために寺院を建立した織田信長」では、織田信長の宗教観が紹介されます。後世、信長を無神論者と見なす意見が一定の説得力をもって広まるほど、彼は反仏教的な武将として知られます。たしかに、元亀2(1571)年の比叡山焼き討ち事件は仏法に対する前代未聞の敵対行為とされ、それ以降、長い間、天台宗では信長を仏敵と見なしてきました。また、元亀元年から天正8(1580)年にかけて行われた石山合戦では、本願寺を中心とする浄土真宗(一向宗)と真正面から対峙し、伊勢長島や越前では「根切り」といわれる殲滅戦に踏み切っています。著者は「こうした徹底的な戦いぶりは、信長が同時代の武将たちとは異なる特殊な宗教観をもっていたのではないかとの疑念を生じさせます」と述べています。しかし、一方で信長は形式的には浄土宗に帰依しており、意外なことに、当初は本願寺とも友好的な関係を築いていました。
また、信長は親交の深かった臨済宗の僧・沢彦宗恩が考察した「天下布武」という言葉を印判に採用しています。この事実は、信長が仏教界の知識人との交流を重視していたことを示しています。「比叡山焼き討ち事件は宗教弾圧ではなかった」では、著者は「よく知られるように、永禄11(1568)年に足利義昭を奉じて上洛して以来、畿内に覇権を確立しようとしていた信長に対して、本願寺や越前の朝倉氏、近江の浅井氏、紀伊の雑賀衆といった勢力の連携が成立しました。いわゆる信長包囲網です。この包囲網に延暦寺も参加しており、元亀元(1570)年の志賀の陣では浅井・朝倉連合軍を比叡山に招き入れて織田軍と対峙し、延暦寺は信長への敵対姿勢を鮮明にしました。延暦寺は当時、武装した数千人もの僧兵を擁しており、伝教大師最澄以来の聖地としての権威を誇りながら、その実態は武装集団の拠点として機能していたのです」と述べます。
延暦寺の武装化の歴史は古く、すでに平安時代末期には白河法皇が「天下の三不如意」の1つとして挙げていたように、延暦寺の僧兵は「山法師」と呼ばれて強力な軍事力を恐れられていました。事件当時の僧侶たちは仏道修行や宗教儀式をないがしろにしており、武芸の鍛錬に励んでいたといいます。さらに、彼らが多くの「美女」や「稚児」を寺院内に引き入れていたことも記録に残されています。当時の延暦寺は、宗教施設の立場を利用しながら社会秩序に悪影響をおよぼし、俗世の政治権力にも介入する武装集団であったのです。著者は、「したがって、信長の意図は仏教の弾圧にあったのではなく、仏教を隠れ蓑とする武装集団に対する制裁が目的であったと考えられます。比叡山焼き討ち事件とは、一見、反仏教的な虐殺行為のようですが、その本質はむしろ仏教に聖性を求めていた信長によって実行された、破戒集団に対する懲罰行為であったといえるでしょう」と述べるのでした。
「徳川家臣団を分断した宗教一揆の真相」では、これまで日本では、多神教を基盤とする文化的な土壌が宗教間の対立を緩和してきたため、一神教の国々が経験してきたような深刻な宗教戦争は起きなかったといわれてきたとしながらも、著者は「しかしながら実は、戦国時代には激しい信仰心に起因する宗教的な色彩の強い合戦がいくつか見られます。かつては、日本でも宗教戦争が起きていたのです。その典型的な事例の1つが、三河一向一揆です。三河一向一揆は、永禄6(1563)年から翌年にかけて、当時、松平元康と名乗っていた家康が治める西三河全域で、ほぼ半年間にわたって続いた浄土真宗の信者(門徒)たちによる武装蜂起です」と説明しています。
「主君を捨てた本多正信の篤い信仰心」では、三河一向一揆がきわめて深刻であったのは、家康の家臣団のおよそ半数が一揆側に走ってしまったことだと指摘します。このことは、当時の武士たちが主君に対する忠誠と信仰との間に深い葛藤を抱えていた実態を示しているとして、著者は「現実と信仰との間で激しく懊悩した武士のなかには、後年、家康の参謀役として江戸幕府の成立に貢献した本多正信もいました。半年間にわたる戦いの末に一揆を鎮圧した家康は、いったんは自身のもとを去った家臣たちの罪を問うことなく、その大半に帰参を許しました。結果として、この寛大な処置は家康と家臣団との結びつきを強めることになります」と述べます。
「葬式仏教へと変質する江戸時代の仏教」では、戦国時代の宗教は武将たちの日常と深くかかわっており、彼らは当然のように信仰を精神的なよりどころとしていたことが指摘されます。現代的な感覚とは異なり、彼らの多くが直情的で、荒々しい信仰心をもっていたことがわかるとして、著者は「そうした宗教観が成り立っていた背景要因として、つねに死と直面しなければならなかった当時の社会状況を指摘することができます。戦国の武士たちは、信仰を心の支えとして、無常観にもとづく死の覚悟を内面化していたのです。さらに、多くの武将たちが臨済宗をはじめとする禅宗に傾倒していた事実も見逃すことはできません。彼らは、座禅などの修養を日常生活に取り入れることで、平常心を養い、精神統一に努めていました。澄み切った境地に生じる『禅機』を得て、判断力を磨いていたのです」と述べています。
江戸時代に入ると、儒教を中心とする思想的な武士像が形づくられていくなかで、彼らの信仰心は理性的なものへと変化します。幕府による管理のもと、全国の寺社が統治機構に組み込まれて檀家制度が機能しはじめるとともに、いわゆる葬式仏教としての性格が強まり、仏教には儒教の補完的な役割が求められるようになりました。著者は、「祖先崇拝が制度化され、社会秩序を維持するための要素の1つとして位置づけられる一方、儒教的な道徳観との調和がはかられるなかで文化的な教養としての仏教理解が進み、学問的な研究対象として見られるようになるのです。武将たちの精神的な支柱としての切実な役割が期待された戦国時代と比べれば、江戸時代の仏教の実践的な意味合いは低下したと考えられます。結果として、現代を生きる私たちが思い描く武士像からは宗教的な要素が失われてしまいました」と述べるのでした。
第三章「不安定な主従関係と戦国の忠義」の「戦国武士なら考えられぬ赤穂の無血開城」では、元和偃武から90年近い年月が経っていた当時、赤穂事件をめぐっては、武士から町人にいたるまで、人々の間でさまざまな議論が交わされたことが紹介されます。このことは、戦国時代の気風が儒教的な価値観によって塗り替えられつつあった当時の武家社会の困惑を示唆しているとして、著者は「人々は、かつての伝統的な武士の価値観とは異なる、新たな時代の「合戦」をどのように評価すればよいのか、大いに迷っていたのです。戦国時代の価値観に照らし合わせたとき、赤穂事件の異質性が最も特徴的に表れているのは、次の2点です。その第1は、浅野家があっさりと幕府に城を明け渡してしまったことです」と述べています。
戦国時代の価値観をあてはめれば、浅野家による無血開城は全面降伏の意思表示であり、厳しい見方をすれば、武士としての意思表示の機会すら放棄する行為だったともいえます。こうした論理は、当時、最も有力な儒者の1人であった荻生徂徠とその弟子の太宰春台が指摘したように、内蔵助たちが上野介を「君の仇」としたことは誤りではなかったかという見解につながっていくと指摘し、著者は「つまり、内匠頭の命を奪ったのは上野介ではなく、切腹を命じた幕府であったという事実をふまえれば、本来、内蔵助たちが戦いを挑むべき相手は幕府ということになります。にもかかわらず、主君の仇である幕府に城を明け渡した浅野家の判断は、伝統的な武士の価値観から逸脱していたことになるのです」と述べます。
「もし吉良上野介が病死していたら・・・・・・」では、赤穂事件に指摘される第2の異質性は、内匠頭の切腹から吉良屋敷の襲撃にいたるまでに2年近い年月が経っていることだといいます。この点も当時の議論の焦点となっていますが、伝統的な価値観に鑑みれば、武士に求められるのは「即断即決」が原則でした。いうまでもなく、時間の経過に従って状況が変わってしまうからです。著者は、「たとえば、襲撃を準備している間に高齢の上野介が病没してしまうことは、十分に考えられたことでした。結果として、上野介がその後も健在であったために襲撃事件が成立したものの、戦国時代の武士であれば内匠頭が切腹を命じられた直後に行動を起こしたに違いありません。また、その間に内蔵助たちが幕府に対して家名の再興を嘆願するなど、法的な手続きを重視していたことにも価値観の違いが表れています。戦国時代であれば、武士たちは直接的な実力行使を優先したでしょう」と述べています。
また、著者は死に対する認識についても指摘しています。泉岳寺で内匠頭の墓前に上野介の首を供えた後、内蔵助たちが幕府に法的な処分をゆだねた行為は、武家の伝統的な価値観とは異なっていました。戦国時代であれば、おそらく大半の武士は吉良屋敷での討死を願ったでしょう。内匠頭への報告を重視したとしても、その墓前で全員が切腹することを選択したと考えられます。著者は、「戦国の武士には、みずからの死を他者にゆだねるという発想はありませんでした。内蔵助たちの行動は、望ましい忠義のあり方を示した武士の模範として称えられてきましたが、意外にも、江戸時代の官僚機構や法制度を前提とした新しい時代の行動様式を反映したものといえます」と述べるのでした。
第四章「足軽と鉄砲が変えた戦国の合戦」の「戦国の武士たちは刀より弓矢で戦った」では、当時の武士が用いていた武器として、多くの人は真っ先に刀を思い浮かべるはずだとして、著者は「実際、刀は古くから武士の命とも、魂ともいわれる特別な存在で、武士を象徴する武器と認識されていました。しかしながら、刀の存在感が大きくなるのは戦乱の絶えた江戸時代以降のことで、戦国時代までは戦場における補助的な武器と位置づけられていました。それまでの武家社会で主力と考えられていた武器は弓矢です。武士の起源に遡ると、もともと武士に求められる技能として最も重視されていたのは弓術と馬術でした。古来、武家を『弓馬の家』と呼ぶのはそのためです」と述べています。
「蒙古軍を撃退した『神風』の真相とは」では、鎌倉時代の蒙古襲来が取り上げられます。一般的に蒙古軍が神風によって敗退したとされていますが、近年の研究では神風についての見解があらたまりつつあるといいます。著者は、「じつは、たしかに当時、北九州において暴風雨による被害が生じたことが記録されているのですが、どういうわけか、その大部分は蒙古側の史料なのです。日本側では、京都の公家の日記を除いて、台風に言及している一次史料は見あたりません。このことから、博多湾付近を通過した大型台風が周辺地域に甚大な被害をもたらしたことは事実と考えられるものの、そのときにはすでに勝敗が決まっていたのではないかという説が有力視されるようになりました」と述べています。
日本の武士たちは天佑に恵まれたおかげで蒙古軍を撃退したのではなく、軍事的な実力で勝利したというわけです。このあたりの事情については、日本中世史の研究家であるアメリカのトーマス・コンランが指摘したように、日本の勝因として神風が強調された背景には、日本と蒙古の双方に動機があったと考えられます。というのも、蒙古側は自然災害に敗因を求めることで、世界帝国としての面子を保つことができたからです。そして、日本側にとっても神仏の加護によって勝利を得たという構図は望ましいものでした。朝廷と宗教界の人々が、こぞって外敵の退散を祈禱していたからです。
「最高の名誉とされた一番槍と殿槍(しんがりやり)」では、武士のリアルな戦闘について詳しく説明されています。武士が刀を使用する最終局面では、敵の首を取るため、馬から降りて戦いました。その間、馬をつなぎとめておくのは従者の仕事です。通常、武士は少なくとも2人の従者を伴っており、必要に応じて馬の口取りや世話をするのが彼らの役割でした。そして、敵を組み伏せ、その首を取る際には脇差や短剣が用いられました。著者は、「ただし、この瞬間、武士の背後が無防備となるため、首を取る寸前で背後から襲われる例が少なくありませんでした。したがって、首を取る武士の背後を警戒するのも従者の役割であったと考えられます」と補足説明をしています。
「討ち取られた大量の首の行方」では、関ヶ原の戦いに関する軍記にも記されていたように、刀を抜いて首を取り合う局面では、一軍を率いる大将クラスの武将でさえ、みずから敵との組み打ちを挑む場面も見られました。こうした状況は、戦局が集団戦から個人戦の段階へ移ったことを示しています。首を取った直後に首を取られるという壮絶な場面も、混乱をきわめた個人戦ならではの現象といえるとして、著者は「討ち取った首は戦場における働きの重要な証拠とされたため、合戦が終わると軍奉行のもとへ届けられました。したがって、合戦が終わるまでの間、武士たちは首を紐で縛って腰に結びつけて戦闘を継続していました。戦闘が終わると、通常は左手で首を持ち運びましたが、なかには槍の先に突き刺して持ち運ぶ姿も見られました。何らかの理由で首を持参することができない場合には、敵が着用していた甲冑の一部や旗印、刀などで代用することもありました」と説明しています。
その後、身分の高い武将の首は総大将も参加する首実検の場に供され、首の人物の特定と手柄の確認が行われました。このとき、必要に応じて捕虜が召し出され、人物を特定するための証言を求められる場合もありました。著者は、「首実検を終えた敵将の首は、まず人通りの多い場所で晒しものにされましたが、一定期間が過ぎれば供養の対象となりました。たとえば、石田三成の首は三条河原での晒しの後、親交のあった禅僧に引き取られ、京都の大徳寺に葬られました。そして、とくに高位者の首は丁重に清められ、しばしば遺族のもとへ返還されました。それ以外の首は集合墓地に埋葬され、鎮魂の儀式が執り行われました。首実検を経て正式に戦功が確定されると、戦果は「首帳」に記録されました。慶長20(1615)年に刊行された『大坂物語』という仮名草子には、同年に行われた大坂夏の陣における幕府側の戦果が報告されています。それによると、徳川方で認定された首の数は約1万4000に及びました」と説明しています。
第五章「戦国時代の切腹と武士の名誉」の「もともと切腹は刑罰ではなかった」では、戦国時代の切腹について解説しています。そもそも切腹がいつごろから行われていたのか、その起源は定かではありません。史料をたどるかぎり、平氏や源氏が台頭してきた平安時代の末期にまで遡ることができます。ただ、散発的な事例に限られていました。日本で初めての武家政権が生まれた鎌倉時代には、武士の勇気を示す究極的な方法として認識され、数多くの事例が記録されるようになりました。著者は、「切腹ほど、江戸時代的なイメージが定着したものはありません。この時代には切腹が刑罰の一種として制度化されていましたが、もともと戦国時代の武士たちにとって、切腹は自身の名誉を守るための最終手段でした。自身の腹に刀を突き立てるには、人間としての限界を超えるほど、相当の覚悟と勇気が求められるからです」と述べています。
古来、腹は精神や意志を象徴する部位と考えられてきました。そこを切り裂くのは、武士としての内面的な姿をあらわにする行為でした。つまり、物理的な意味でも“腹のうち”をさらすことにより、自身の潔白や精神性の高さを証明するという意味合いが込められていたと考えられます。また、切腹に儀式としての要素が加わるのも江戸時代のことであると指摘し、著者は「戦国時代までは、各々が独自の方法で、さまざまな場面で、多数の観衆の前で行われる場合もあれば、少数の証人の前で静かに執り行ったりしていました。観衆が見守るなか、庭先に敷いた白い布の上に正座した武士が作法にのっとって腹を切る、という場面は、江戸時代の光景と考えてよいでしょう」と述べます。
戦国の武士たちは、合戦に敗れたとき、生きて敵の手に落ちるまいとして、みずから腹を切りました。また、何らかの理由で面目を失ってしまったときにも、名誉を回復するために腹を切りました。さらに、面目を失う状況の一種として、主君に対する不満や抗議の意思表示の手段としても切腹は行われました。著者は、「このような武士の死生観と名誉意識に基づく自害の習慣は、次第に武士階級の間で『名誉ある武士は窮地に立たされたときには潔く切腹すべきである』という価値観として定着していきました。武士としての誇りと節操を守るというこの認識が広まったからこそ、戦国時代末期には、失態や重罪を犯したとみられる家臣に主君が切腹を命じる場合も出てきました。これがのちに刑罰としての切腹へと発展していきました」とのおべるのでした。
「異教徒の心も打った勝家の振る舞い」では、柴田勝家の切腹に言及します。キリスト教では自害を大罪としているにもかかわらず、フロイスが勝家の決断を否定的に描いていないのは注目に値すると述べています。勝家の「名誉」を重んじる姿勢と、部下たちへの配慮がイエズス会士の心を打ったためと考えられるといいます。また、城内から「陽気な歌声」が聞こえたという描写は、ほかの当時の史料にも言及があるように、切腹前夜の宴の様子を示しているのでしょう。著者は、「死を覚悟して酒宴を催すのは、戦国の武家の慣習であり、よく見られる行為でした。当時の武士たちは、死を『ハレ』の場としてとらえていました。そして、宴会は『日常』から『非日常』への移行を示す儀礼的な場です。つまり、最期の宴会は、この世からあの世への移行における神聖な通過儀礼として機能していたのではないでしょうか」と述べています。
宴会という「祝いの場」で死を迎えることは、死を忌むべきものとしてではなく、人生の完成としてとらえる武士の精神世界の表れだと、著者は言います。陽気な歌声は、死への恐れや悲しみではなく、むしろ「よき死」への歓びを表現しています。日本古来の「生死一如」の思想に通じるものといえるとして、著者は「このように見ると、勝家たちの最期の宴会は、単なる演出を超えて、日本の伝統的な死生観の実践だったと解釈できます。人生の完成として祝い、共同体全体で受け入れていく文化的な営みだったのではないでしょうか。イエズス会士が驚きをもって記録したのも、このような死生観が、キリスト教的な死生観とは大きく異なっていたからこそだと考えられます」と述べます。
勝家が自身の最期を敵に伝えさせた行為は、歴史にみずからの名を刻もうとする意識的な行動だったといいます。秀吉が隆景に宛てた書状で勝家の最期を語れたのは、老女の証言があったからですが、誰かを証人として立て、後で敵陣や身内に伝えさせるという行為は、戦国時代の自害の際に欠かせませんでした。著者は「特筆すべきは、イエズス会士の記録が、異文化である日本の武将の死生観を、否定的な価値判断を加えることなく、むしろ理解を示しながら記録している点です。これは、勝家の人格と行動が、文化や宗教の違いを超えて、普遍的な人間の尊厳を体現していたことを示唆しています。逆にいえば、勝家が切腹していなかったら、歴史上これほどの印象を残すことはなかったでしょう」と述べるのでした。本書はベルギー人である著者が戦国武家の死生観を深く考察し、わかりやすく説明してくれる好著でした。わたしは、戦国武家には「死のロマンティシズム」としての「ロマンティック・デス」をたまらなく感じます。
*よろしければ、佐久間庸和ブログもお読み下さい!
2025年11月30日 一条真也拝


