一条真也です。
『死を見つめ、生をひらく』片山恭一著(NHK出版新書)を読みました。わたしは、「死」についての本はかなり多く読んできたつもりですが、この本を読んだときは唸りました。著者は1959年、愛媛県生まれ。作家。九州大学農学部卒業。同大学院博士課程中退。86年「気配」で文學界新人賞受賞。2001年『世界の中心で、愛をさけぶ』が300万部を超える大ベストセラーとなりました。小説に『愛について、なお語るべきこと』など多数。評論に『どこへ向かって死ぬか――森有正と生きまどう私たち』など。本書は2013年7月に刊行されていますが、ものすごい名著でした。あの『セカチュー』の作家がこんな凄い思想書を書いていたとは!
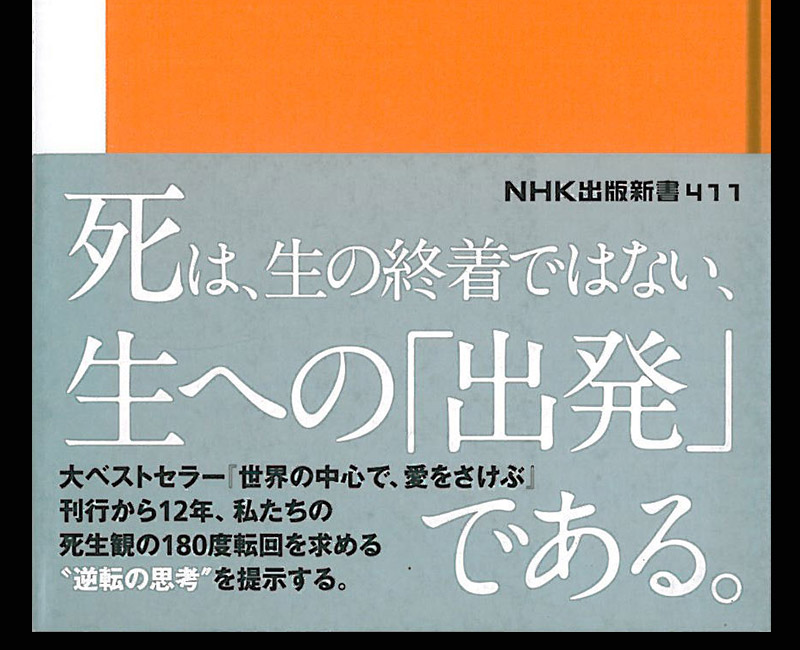
本書の帯
本書の帯には「死は、生への終着ではない、生への『出発』である。」と大書され、「大ベストセラー『世界の中心で、愛をさけぶ』刊行から12年、私たちの死生観の180度転回を求める“逆転の思考”を提示する」と書かれています。また、帯の裏には「いま、私たちは――本質においてではなく、可能性において、人間を問わねばならない」と書かれています。
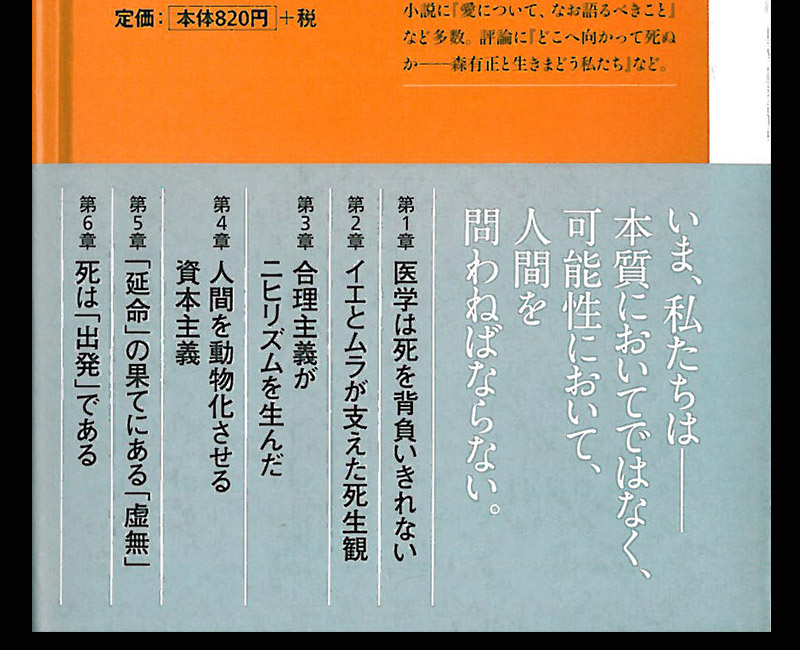
本書の帯の裏
アマゾンの「出版社からのコメント」には、以下のように本書の内容がまとめられています。
「なぜ、生きまどう人が増えているのか? その根源的な原因は『死の忘却にある』と著者はいいます。『死とは何か→虚無(終着)である』の“定説”が、未来への展望なしに私たちを『現在』に縛りつけ、それが寄る辺ない精神状態を生み出しているというのです。では、どうすればよいのか? 著者はある“逆転の思考”を提言します。『そもそも〈死とは何か〉という問い自体が間違っている。そこからは〈死=虚無〉以外の答えは出ない。正しい問い方は〈死とは何でありうるか〉だ。死を本質ではなく可能性において問うことで、一人一人が自らの責任で死と向き合える。それがひいては個々の生き方を定義づける。ベクトルが逆なのだ。死は生の終着ではなく、生への出発なのである』。そこで著者は、この“逆説”を証明するために歴史をたどり、作家ならではの筋道を立てて論を展開していきます。たとえば、前近代の日本では、先祖信仰という形で先祖(死者)が生者の生き方の指針となっていた。過去の死者を絶えず意識することで現在の『生』は充実し、それがいずれは訪れる未来の『死』を責任をもって受容することにつながった。そこに近代合理主義が到来し、生者が死者を排除(死を忘却)していったことでこの関係は逆転し、折からの資本主義の隆盛とともに卑近な『現在』への執着が生じた。しかし、いま資本主義が行き詰まっている。たとえ人の寿命が延びたとしても、やがては訪れる『死=虚無』の克服にはいたらない。だから、死から生への新たなる逆転、すなわち生への出発がはかられなければならない――と。文壇デビュー以来、一貫して『死』にこだわり続けてきた著者が到達した境地は、“逆転の思考”で現代文明に対峙することを説く、人間の新しい生き方を提示するものです」
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「はじめに」
第一章 医学は死を背負いきれない
第二章 イエとムラが支えた死生観
第三章 合理主義がニヒリズムを生んだ
第四章 人間を動物化させる資本主義
第五章 「延命」の果てにある「虚無」
第六章 死は「出発」である
「参考文献」
「はじめに」で、「死は虚無であり、それ自体は無意味である」と1つの社会全体がみなしているとすれば、非常に特異なことだと言えるとして、著者は「そんなふうに死を位置づけた社会は、過去にも現在にも、ほとんどないはずです。なぜなら死を虚無と考えることに、人間は耐えられないからです。だから死者は埋葬されたのです。様々な葬制が考え出されてきたのです。人間の歴史は死者たちとともにありました。死者や死後を考えるのが人間であると言っていいくらいです。この社会が死を虚無とみなすなら、それ以外の答えを死にたいしてもちえないなら、ぼくたちは人間以外のものになりつつあると考えるべきでしょう。人間の生は個体のものであるとともに、個体を超えたものでもあります。現在とともに、歴史や伝統のなかにある。そのようにして人は生き、死に赴いてきました」と述べています。冒頭から、拙著『唯葬論――なぜ人間は死者を想うのか』(三五館、サンガ文庫)のメッセージとまったく同じであり、わたしは大いに共感をおぼえました。
第一章「医学は死を背負いきれない」の「死を『諒解』できない社会」では、医学的に、あるいは生物学的に説明される死というものは、国や地域を超えて理解可能なものであると指摘し、著者は「その意味では、1つのクローバル・スタンダードと言えるでしょう。医学や生物学が扱うのは生命現象です。したがって死は生命活動の停止であり、生命システムの破壊として定義される。これが理解できる死です。その先には何もない。要するに、終焉ということになります。あらゆる関係の断絶であり、完全なる虚無である。いくら考えても、それ以外のものは出てこない」と述べています。
こうした死に対して、わたしたちは恐ろしいとか、悲しいとか、寂しいといった感情を抱くのだと思うとして、著者は「それは当然のことです。理解できる死だけで済まそうとすると、死は恐ろしく、悲しく、寂しいものでしかない。だから死のことは忘れて、当分は自分に起こらないこととして生きる。せいぜい元気なうちに楽しんでおく。そのくらいしか手立てがないわけです。これはあまり健全な生き方ではないような気がします。刹那的な生き方といいますか、一種のニヒリズムではないでしょうか。まさに夢も希望もないわけで、こんな死を目指して、人は生きることはできないと思うのです」と述べます。
「心のよりどころを失った日本」では、キリスト教文化圏の人々はダブル・スタンダードでやっていると言えるかもしれないとして、著者は「生きているあいだのことは、経済のことにしても自然科学やテクノロジーのことにしても、とにかく最先端のところでやっていく。一方で、死んだあとのことは神様におまかせする。そういう使い分けをしながら、うまくやっているようにも見えます。アメリカなどでは戦場で死んだ兵士の遺体が帰ってくると、『神のもとに召された』なんてことを平気で言うわけです。大統領とか国防長官とか、そういう偉い人たちが。日本ではちょっと考えられません。日本の首相が同じことを言えば、『あいつ、おかしいんじゃないか』ということになる。つまり人の死にかんして、アメリカやヨーロッパは、神にゆだねるという態度をごく自然にとれる社会なのだと思います。そのあたりはなお、伝統的なキリスト教の文化によって支えられている面が大きい気がします」と述べています。
欧米諸国と同じように資本主義が発達した日本ですが、彼らに比べると、日本人には何もないと言っていいのではないかとして、著者は「たとえば肉親の不慮の死に遭遇するといった場面で、遺された家族を支えてくれるもの、心のよりどころとなるものが見当たらない。結局、損害賠償や補償の問題にしかならないわけです。しかし死は何ものによっても贖いようのないものです。お金をやると言われたところで、なんの慰めにもならない。本来、宗教は死の問題を解決するために生まれてきたはずです。その宗教が、日本ではほとんど機能していない。死にたいして無力といいますか、死の問題も死後の問題も等閑視して、『葬式仏教』と揶揄されるようなものになっている」と述べます。
「倫理は『個人』に託された」では、死の問題に関しては、誰もが自分だけで対処しなければならなくなっているとして、著者は「死の意味は個人が見つけなければならないものになっている。その点では、どのような死であれ、すべて孤独死であると言っていいと思います。たとえ家族に見守られながら亡くなっても、孤独な個人の死であることには変わりない。そもそも葬式をどうするかとか、死んだあとはこうしてくれとか、一昔前までは個人が考えることではなかったのです。考える必要も余地もなかった。いまは葬式にしても遺骨の処理にしても、生前にアレンジする人が多くなってきています。そのくらい死も死後も、一人一人の恣意にゆだねられるものになっている。つまり社会的に共有される文脈の上にはないのです」と述べています。
第二章「イエとムラが支えた死生観」の「問題は『死後』にある」では、人間だけが垂直の視線をもち、垂直の視線を意識することができると指摘し、著者は「これは人間が『時間』を思考しうる動物であることを意味していると思います。つまり時間を時間として思考することができる。それにたいして動物たちは、空間だけを生きていると言えるかもしれません。彼らにとっての時間とは、たとえばA地点からB地点への移動に要する物理的時間の長さです。運動や移動の距離であり、本質的には空間なのだと思います」と述べています。
現代の宇宙物理学によると、何気なく夜空を見上げることで、じつは数百万年前を振り返っていることになるということを紹介し、著者は「高性能の電波望遠鏡を使えば、宇宙の起源や時間の起源を目撃することもできる。もちろん昔の人間には、そういった知識はなかったでしょうが、おそらく同じような気分で星空を見上げていたのではないかと思います。自分が存在しなかった過去や、自分が存在しない未来、あるいは『永遠』や『無限』について思いをめぐらせてきたのではないでしょうか」と述べます。この言葉は、『永遠葬〜想いは続く』(現代書林)という著書のあるわたしにとって、非常に説得力がありました。
時間を思考する能力が、人間に「死」の観念をもたらしたと言えるいう著者は「逆に、死の観念が時間をもたらした、と言っても同じです。人間にとって死とは時間である。時間とは、すなわち『死ななければならない』ということであり、死を自覚した人間の存在様態が『時間』と言ってもいいでしょう。人間は死を認識する動物だと言われますが、それは人間が時間を思考する動物であるということと同じです。ですから人間にとって、問題は死そのものではなくて、『死後』なのです。死んだあとのことが気になってしょうがない。これは人間が時間の観念をもっているからです。遠い未来のことや、遠い過去のことを思考しうるという能力が関与しているわけです」と述べます。
そこから埋葬ということもはじまったと考えられるとして、著者は「人間の大きな特徴の一つは、死者を放置しないということです。個体の生物学的な死を放置しない。それは人間が死後の観念をもっていることと裏腹の関係にあります。人間にとって、生物学的な死といえども時間の連続性の上で起こってくる。時間の断絶として立ち現われる死を解決しようとしたときに、葬礼のようなものが考え出されたのでしょう。また死後のあり方といいますか、死者の行方とか、他界観のようなものが思考の対象となってきたのだと思います」と述べます。
続いて、著者は「死後にしても他界にしても、体験によっては語りえないものです。どうしても想像力が介在してくる。死は人間の想像力の源泉であるとも言えます。死というものを意識したとき、人間の想像力は駆動しはじめた。人間の前に想像力の領域が立ち上がってきた。神話や宗教は、そうやって生まれてきたものでしょう。人間の思考には、どうしても自然科学的な認識だけでは片付かない部分があります。否応なしに想像力の領域にまたがってしまう。つまり存在しないものを思考する、ということが不可避なのです。だから『意味』が付きまとってくる。存在しないものを、『意味』によって補おうとするわけです」と述べるのでした。
「『家』単位の先祖信仰」では、先祖信仰について言及しています。名著『先祖の話』で、柳田國男は「霊融合の思想」というふうにとらえていますが、人は亡くなってある年限を過ぎると、「ご先祖さま」や「みたまさま」と呼ばれる1つの尊い霊体に融け込んでしまいます。それは多くの先祖たちが一体となった神であり、この先祖神が子孫後裔を守護してくれる、というのが柳田によって示された大まかな見取り図です。現在でも人が亡くなると、一周忌とか、三回忌とか、七回忌とか、いわゆる年忌供養を行います。そして三十三年忌くらいで弔い上げとなります。
これについて、著者は「宗派や地域によって異なるため、一概には言えませんが、長いところでも50年くらいだと思います。それ以上になると、亡くなった人のことをおぼえている者もいなくなる、という事情もあったでしょう。長い年月にわたり、年忌ごとの法要を受け、また盆や彼岸の行事で子や孫たちの供養を受けることによって、死者の霊魂は清められていき、生前の個別性を失いながら、最終的に先祖の霊(祖霊)のようなところへ集約されていく。なかなか合理的な説明です。誰もがいずれは『ご先祖さま』や『みたまさま』になるわけですから、死後はひとまず安心です」と述べています。
もともと死者の霊の往還という考え方は、日本にかぎらず、東アジアにおいては古くから見られたもののようであるとして、著者は「たとえば『鳥形霊』と呼ばれる信仰があります。白川静が中国の古代文字研究のなかで述べていることですが、中国には古くから、人の霊魂は鳥によってもたらされ、また鳥になって去るという考え方があったそうです。水辺に飛来する渡り鳥は、遠く霊界へ去った死者たちの魂が、時期を定めて帰ってくるものと考えられていました。だから鳥たちの飛来する沼沢のほとりは、しばしば神霊を祀る聖所とされました。おそらく四季がはっきりしていて、規則正しくめぐってくるという自然の条件が関与しているのでしょう。死者の霊が周期的に、『あの世』と『この世』のあいだを往還するという考え方は、東アジア一帯の他界観として、かなり古いものと考えていいかもしれません。
日本の仏教思想のなかには、「永遠」や「無限」といった観念がほとんど見られません。中国式の仏教なども、無限というよりは「段階」という考え方を好んだようだと紹介し、著者は「永遠や無限というのは、どちらかというとインド的な観念と言えるのかもしれません。『ゼロ』を発見したのもインド人だと言われています。現在では普通に使われている『永眠』という言葉などは、本来の日本人の感性からすると、死者にたいしては使いにくかったかもしれません」と述べています。
「『家』『村』に還れないぼくたち」では、先祖信仰を支えていたものは伝統的な「家」であり、自然崇拝を支えていたものは農村などの村落共同体であったと指摘して、著者は「もはや日本の社会にはないものばかりです。核家族化とか都市化とか市場経済の浸透とか、様々な原因が考えられます。いずれにしても、現在の日本の社会が、死を諒解するための環境や道具立てを失ってしまっていることは確かです。その結果、自分の死も他者の死も、うまく受け入れることができなくなっている。戦後の民主化の流れのなかで、伝統的な『家』と村落共同体は、天皇制ファシズムの温床として常に批判に曝されてきました。すなわち『家』は家父長的な天皇制を支えるイエとして、村落共同体は封建的なムラとして、批判的に論じられることが多かった」と述べています。
一方で、前近代的とされた「家」や村落共同体が、日本人の死生観や他界観を支えてきたことも事実であるとして、著者は「先祖信仰にしても自然崇拝にしても、知識や情報として持ち運ぶことはできません。つまり教育は不可能です。学校などで教えるというわけにはいかない。かつて子どもたちは共同体のしきたりや祭祀を通して、いつのまにか自然を崇め、敬い、畏れる気持ちを身につけていったことでしょう。山に入れば、いたるところに石仏が祀られ、聖なる樹や岩がある。そうした場所とのかかわりを通して、自然というものの存在を感じ、言葉としてうまく表出できないような感受性を培っていったのだと思います」と述べます。わたしも同じ意見です。
『先祖の話』を書いた柳田國男によると、亡くなった人の霊が登っていく山にしても、どこでもいいわけではなくて、この村はこの山というような管轄があったことを紹介し、著者は「だからこそ『ふるさと』が重要だったのでしょう。盆と正月に帰省するのは、たんなる休暇や骨休めといった意味だけではなかったはずです。自分がどこからやって来て、どこへ還っていくのかといったことを確認する、大切な儀式でもあったのだと思います」と述べます。また、『想像の共同体』を書いたベネディクト・アンダーソンの言葉を借りて、こうしたモナド的に切り離されてしまった人々の中に「つながり」を回復するものが国民国家だったと述べています。
なぜ人は偶然に死ぬのか。偶然でしかありえない死が、誰にとっても不可避であり必然であることを、どのように考え、いかに受け入れればいいのかと問う著者は、「ヨーロッパにおいてはキリスト教が、神への信仰を前提に死の偶然性と必然性を説明し、不死性と永遠性の暗示のもとに意味化してきました。では信仰の外にある者はどうなるのか。たとえばサルトルやボーヴォワールなどは、死は虚無であると言い切っています。無神論や唯物論の立場からすれば、当然そうなるわけです。しかし一般の人たちが、そこまで潔く割り切って考えられるかどうかは疑問です。そこでキリスト教が力を失った近代以降、宗教にかわってあらわれてきたものが、ナショナリズムとともに形作られる「国民国家」であった、とアンダーソンは言うのです」と述べます。
また、著者は「ぼくたちの精神世界は、個人のものであるとともに、個人を超えたものでもあります。現在とともに、歴史や伝統のなかにある。そうした歴史や伝統を支えてきたものが、姿を消してしまったということだと思います。とくに都市で核家族というユニットを営んでいると、死者を弔う儀式や習俗は簡略化され、形骸化しがちです。習い覚えたことを形式的にやっていても、由来やもとの意味はわからなくなっている。こうして死というものにかんして、伝統的な感情の受け渡しが困難になっていく、あるいは不可能になっていきます」とも述べています。
第三章「合理主義がニヒリズムを生んだ」では、近代以降、人間は死者と自然を排除することによって自分たちの世界を作ってきたと指摘し、著者は「生きている者が、死者や自然をコントロールできるようになった時代、人間が死者と自然から自由になった時代。それが『近代』であると言っていいかもしれません。いまやぼくたちは、真の意味で、ヒューマニズム(人間中心主義)を終わらせなければならない段階にいます。死者の眼差しで生者を見ることや、自然の眼差しで人間を見ることが必要です。それは経済的価値を超える新しい「価値」と出会うことを意味しています。ぼくたちがめざすべきは、そうした新しい価値の創出ではないでしょうか」と述べるのでした。
第四章「人間を動物化させる資本主義」の「資本主義には他者への回路がない」では、「死が虚無でしかありえなくなった世界で、倫理を問えるか」ということがドストエフスキーをとらえた最大の問題であったと紹介し、著者は「死が虚無であるなら、なぜ生きているあいだに、正しいことや善いことをしなければならないのか。生の意味が、限られた時間を使い果たすというだけなら、そのあいだに何をしても、最後は虚無の冷たい焔のなかに投じられて終わることになる。生の根本的な性格がそのようなるのであるなら、たとえば誰かのものを盗んだり奪ったりして、他人の労力と生命によって生きていくことさえも是とされるのではないか。然り。ぼくたちは、まさにそのようにして生きています。資本主義とは結局のところ、自分の手を汚さずに、誰かのものを盗んだり奪ったりして、他人の労力と生命によって生きていくことを是とするシステムではないでしょうか。その象徴がグローバル・スタンダードと呼ばれる、アメリカ型の金融経済だと思います。所得や富の格差が拡大していくことは、先進工業国や脱工業国において共通して見られる傾向です」と述べています。
資本主義について、著者はこうも述べています。
「住宅ローンを含めて、あらゆるものが証券化された上に、様々な評価の証券が組み合わされ、金融工学とやらを駆使した複雑怪奇な金融派生商品(デリバティブ)が生み出される。それらを売ったり買ったりすることで、巨額の富を得たり、巨額の損失を出したりする。いったい、何をやっていることになるのか? 要するに、誰かのものを盗んだり盗まれたり、奪ったり奪われたりしているということではないでしょうか。金融経済のなかで大儲けすることは、他人の労力と生命によって大儲けするということではないでしょうか」
資本主義というシステムの下で、人間はますます動物化し、ますます深いニヒリズムを生きるようになる。そのことは避けがたいように思わるという著者は、「こうした兆候は、あらゆる場面にあらわれています。貨幣を介在させることによって、人と人の関係は匿名化し、非人間化します。たとえばコンビニやスーパーで買い物をするとき、生産者の顔はほとんど見えません。誰がどんな思いで、この野菜を育てたのかといったことを、ぼくたちは考えずに済みます。ただ値段や品質のことしか考えない。生産者にとっても、消費者の顔は見えない。お互いに匿名化しています。このように貨幣を媒介とした関係においては、他者のことは考えなくていいし、また考えようがない」とも述べるのでした。
第五章「『延命』の果てにある『虚無』」の「引き継いだ過去を未来へ引き渡す」では、倫理的な問いは未来からやって来るとして、著者は「未来の者たちにたいして責務を負っている、と考えるところから倫理は生まれる。現在からは、本来的な倫理や善は生まれません。現在という様態においては、相対的あるいは限定的な倫理や善を実現することしかできません。したがって未来のことが考えられなくなることは、本来的に倫理を問えなくなることを意味しています」と述べています。
なぜ人々は死者を弔い、祀ることに、大きな労力を割いてきたのか。それは過去の死者とつながることが唯一、未来の他者とつながる縁になると考えられていたからではないかと考える著者は、「過去の死者を大切に祀ることによって、あるかなきかの細い通路を伝って、辛うじて未来の他者に触れることができる。そのように先人たちは、深い知恵と慎ましさをもって考えてきたのではないでしょうか。未来というものは本来的に、こうしたかたちでしか構想されないものかもしれません」と述べています。ここでいう「過去の死者」とは先祖であり、「未来の死者」とは子孫のことにほかなりません。
日本において過去100年ほどのあいだに起こったことは、未来のことを考えようとして過去に背を向け、現在から過去を切断してしまう、という事態であったという著者は「それが進歩だと錯覚されてきた。しかし進歩と思われてきたものは、一過性の異常な狂騒でしかなかった。日本にかぎった話ではないけれど、なんと愚かしく、盲目的に過去を破壊してきたのかと思わずにはいられません。断ち切られた過去は、けっして戻ってこない。失われたものは取り戻すことができない。それが歴史であり、伝統だろうと思います」と述べます。まったく同感です。
死の諒解が成り立たなくなることは、自らの生を、先祖から子孫への連続した時間のなかに位置づけることができなくなることを意味するとして、著者は「死後の実感を喪失するということは、自分が死者となった未来を、現実のものとして実感できないということです。ぼくたちにとって、未来は自分の不在を前提とした未来に過ぎません。それは本来の意味での未来ではなく、あくまで現在のなかにある『未来』です。いくら未来のことを考えるといっても、ぼくたちは現在の自分という場所からしか、未来を考えることができなくなっているのではないでしょうか」と述べます。
死後の実感を喪失することは、死者となった自分と交流してくれる他者を失うということであると指摘し、著者は「死者とは、未来の他者です。両者は互換性をもたないけれど、等価であると言える。死者とのつながりが不通になることは、未来の他者とのつながりが不通になることを意味しています。すなわちぼくたちは、死者の場所から、未来の他者とともに、未来を考えることができない。未来の他者と、未来を共有することができない。だから「未来の他者のために」という言い方が、自己欺瞞や思考停止をともなった空手形のようなものにならざるをえないのだと思います」と述べます。
「『延命』が資本主義を駆動させる」では、現在は永遠に死を知ることがないとして、著者は「それは死が正しくとらえられていないということです。さらに言えば、死は現在という視野の外にある。死は体験できない、ゆえに恐れる必要はない。死は常に誰かの死であって自分の死ではない・・・・・・といった類の通俗性において、死後は文字通りの無性(Nichtigkeit)として虚無とみなされます。現在・過去・未来という連続した時間の流れが断ち切られ、現在が過去からも未来からも孤絶するほど、死は虚無の色を濃くしていく。生が現在という時間の様態の上だけで営まれるようになるほど、ぼくたちは不可避的に虚無としての死につかみ取られてしまう。過去からも未来からも断ち切られた現在にのみ着生する自己にとって、自らの唯一の基盤である現在が失われるという事態は、虚無として実体化されるしかないからです」と述べます。
「延命」とは、死後を虚無とみなすところから生まれてくる欲望であると主張する著者は、「死後に意味を見出す人たちにとっては、死は忌むべきものでないのみならず、ときには望まれるものですらありうる。だから自爆テロや抗議の焼身自殺へ赴く人が跡を絶たないのでしょう。一方、人を虚無にたどり着かせてしまう死は、当然否定されます。つまり死後が虚無とみなされるとき、生は自ずと死に抗して『延命』されるものになるのです。しかしいくら『延命』したところで、最終的にたどり着くのは虚無でしかありません。だとすれば、『延命』という生き方が、すでに濃い虚無に覆われていると言える。経済成長の饗宴が終わってみれば、あり余る科学技術(テクノロジー)とともに、『延命』という空虚のなかに取り残されていた。それが現在の、ぼくたちの生の実感を形作っているように思います」と述べるのでした。
「環境から『超越』する人間」では、ハイデガーの哲学に言及します。ハイデガーは「超越」という存在構造を、現存在としての人間に普遍的なものとみなしていますが、これを1つの思考様式にまで昇華させ、超自然的な原理において自然を見たり、考えたりすることをはじめたのは、「ヨーロッパ」という文化圏に限られたことであったと指摘し、著者は木田元の『ハイデガー』『わたしの哲学入門』などを参照しながら、「その起源は、プラトンのイデア論にまで遡ることができます。さらにアリストテレスを経て、この特殊な思考様式は形而上学(哲学)として整備され、中世以降はキリスト教神学と結びついて発展していくことになります。そしてデカルトやカントによって近代化されたあと、ヘーゲルのもとで理論的に完成される。つまり形而上学(哲学)としては、それ以上展開しようのないものになります。ここにニーチェが反哲学(プラトニズムの転倒)を掲げて登場する必然性があるわけです。一方、哲学的思考は近代自然科学と結びつき、以後は技術として猛威を振るっていく、というのがハイデガーの描いたおおよその見取り図です」と整理しています。
「人間化する自然、動物化する人間」では、著者がハイデガーの言いたかったことを「人間が人間的であることは、とりもなおさず技術的であるということだ。そして技術的であればあるほど、人間は技術のなかで、その人間性を喪失していく」と要約します。同様のことを、マルクスは「疎外(Entfremdung)」という概念によって言おうとしています。人間が人間的に進歩していくほど、いわば人間的であることと人間性の乖離は大きくなっていく。歴史が進めば進むほど、人間の生き方から人間らしさが失われていくのです。著者は、「そのことを現在、ぼくたちは日々の暮しのなかで実感しています。だから人間らしい暮しを求めて、エコロジーのようなことを志す人が出てくるのでしょう。医療の面でも、薬剤や手術によって過剰に患者の身体へ介入する治療医学への反省から、人間に本来備わっている自然治癒力を見直そうという動きが出てきている。しかしマルクスの時代、彼が『疎外』と呼んだものは、現象としてそこまで広範には立ち現れていませんでした。せいぜい労働者の貧困化といった社会問題として、局所的に先鋭化している程度だった。ゆえに彼は疎外の問題を、まず労働という場面でとらえていくことになります」と述べています。
ここで、2013年に書かれた本書の中で、驚くべきことに著者はウイルスの脅威について次のように言及します。
「今日、なぜウイルスが脅威になっているのかを考えると、その原因はいずれも人為的なもの、人間的なものであることがわかります。たとえば品種改良や人工授精というかたちで、人間が動植物の性や生に介入しつづけることが、攻撃的な性格に変異したウイルスが出現するリスクを高めている。衛生的な生活環境のもとで病原体との接触が妨げられることが、人間の免疫的ポテンシャルを低下させている。薬剤の過剰な使用が、人類全体の生態系を混乱させている。グローバリゼーションの進展は未知のウイルスとの遭遇の機会を増やし、さらに高速化した交通網が、パンデミックの懸念される状況をつくり出している。これらが複合され、今日的な脅威や危機になっている。つまり脅威や危機の実態は、あまりに人間的であり、あまりに人間と同化しているために、二つのものを分離したり、切り離したりすることができないのです」
第六章「死は『出発』である」の「果てなき自己同一性への投資」では、良くも悪くも、資本主義は差別のない世界をめざすとして、著者は「あらゆる差別は拡大を疎外する要因として排除される。結果的に、資本主義は平等な社会を作り出してしまう。その一方で、ぼくたちは個々の差異を消去された均質な人格へ還元されてしまいます。つまり誰もが交換可能な存在になるわけです。自己と他者は交換可能であり、ときに主体であったり対象であったりする。意味をもつのは『場所』であり、そうした『場所』に、ぼくたちは確率的に分布する。ホテルのボーイは、勤務時間が終われば高級レストランの客でありうる。一人一人の人格を決定するのは、どの場所にどのくらいの確率で分布しているか、ということだけです。そして多くの場合、分布の仕方を決定するのはお金ということになります。このことは、ぼくたちが人格として、相互に決定不可能な存在であることを意味しています。なぜなら、お金で購入できるのは、その『場所』を占める権利であり、そこに人格のようなものは反映されていないからです」と述べています。
資本主義が創り出した奇妙な「平等」の下で、目につくかぎり他者の他者性は排除され、消去されていきます。いまや他者の他者性は小さな差異、ソフトな差異のなかにしかないと主張する著者は、「したがって微小な差異にたいして、過剰な知識や情報を身につけることが、『他者』と付き合う際のマナーになります。ぼくたちが出会うのは、自分と似た他者です。ソーシャルメディアの発達が、そのことに拍車をかけています。他者とは自分から近似値計算された人やモノでしかない。今日、様々なソーシャルネットワーク上で起こっていることは、どこか近親相姦めいた様相を呈しているのではないでしょうか。それほどまでに、似たような性向をもつ者たち同士が結びついている。そこには誹謗や中傷はあっても、本来の他者はいない。無菌化されたコミュニケーションのなかで、ハードな他者はあらかじめ排除されている」と述べます。
「未来から現在を規定し、他者から自己を規定する」では、現世的な善きもの、たとえば空や海や森や自然や動物たちが、自分の死んだあとも残りつづけるなどと、希望的に考えることはできないとして、著者は「すべてはあなたの死とともに奪われてしまう。あなたの世界は、あなたとともに消え去る。個人が死ぬとき、世界も滅ぶ。子孫を残しても慰めにはならない。子や孫も、あなたの生とともに消えてしまうのだから。無神論的な人間ほど、『人類』ということを考えたがる。類としての永続性に救いを求めようとする。人類のなかに自分の存在を消し去り、そのなかで新たに誕生し、無限の存在になる、などと虫のいいことを考えたがる。しかし人類とて永遠の存在ではない。何十億年後か、地球は冷却した太陽に呑み込まれてしまう。それよりもはるか前に、人類の死はやって来るだろう。そのとき死者は完全に消滅してしまう。誰一人として彼の存在をおぼえていないだけではなく、かつて彼が存在したという手がかりは何もなくなってしまう。言葉の完全な意味で、これまでに死んだすべての死者たちは殺されるのだ」と述べています。
また、著者は「遠からず人間は終わるのではないかという予感を、すでにぼくたちは生きはじめています。物理的な消滅の可能性も含めて、人間は終焉しかけているのではないか。70億という人間の数だけを見ても、地球上で生息するには明らかに多過ぎる。そのうち巨大化した恐竜のように、自らの体重を支えきれずに滅びてしまうのではないか。さほど遠くない将来に、大きな破局が訪れるのではないかという予感を、多くの人たちが共有している。実際に何が起こるのかはわからない。生存競争めいた恒常的な戦争なのか、もっと別のカタストロフなのか。いずれにせよ終末的なヴィジョンが、漠然とではあれ確実に、ぼくたちの視野に入ってきている」とも述べています。
「真理と誤謬の連鎖の外へ」では、ヘーゲルの哲学に言及します。ヘーゲルにとって人間とは、死すべきものとしての時間であり、自己意識であり、精神であり、自由であり、労働であり、技術であり・・・・・・といった規定を限りなく連ねていくことのできる存在であるとして、著者は「いずれの規定も正しい。人間学的にも、形而上学的にも、存在論的にも、非の打ちどころがないまでに、ヘーゲルは正しい。この『正しさ』をこそ、ぼくたちは問題にしなければなりません。なぜなら正しく規定された人間のなかから、まさにアウシュヴィッツは生まれたと言えるからです」と述べています。
続けて、著者は「ヘーゲルが規定したような人間、もっとも人間的な自己を認識しえた人間、地球上に現れた人間のなかでも、完全に自らの動物性を否定し、唯一『歴史』をつくりえた真に弁証法的な人間こそが、アウシュヴィッツを生み出したと言えるのです。『今日でもなお、私はアウシュヴィッツは超越的観念論の文明によって犯されたのだと思っています』(『暴力と聖性』)というエマニュエル・レヴィナスの言葉は、こうした文脈から発せられたものだと思います」と述べます。
「死は本質的にわからない」では、死を虚無化とみなすことは、なんの保留もなしに、死を存在論の範疇に取り込むことを意味するとして、著者は「存在の否定が虚無であり、存在と虚無が等価になる地点が死であると、彼らは無造作に考えている。この独断と無作法をこそ、咎めなければなりません。たしかにヘーゲルもハイデガーも、死についてこの上なく犀利に思考したかもしれない。しかし死にたいして、決定的にデリカシーを欠いている。このデリカシーの欠如が、おそらく彼らの思考を、自己への過剰な言及へと誘導していくことになったのです。死すべきものとして、自らが死すべきものであることを知っている存在者(現存在)として、人間とは時間であり、精神であり、概念であり、歴史であり、自由であり・・・・・・というふうに。これらを暴力に結びつけてみる必要があるとして、著者は「死を虚無化とみなすようなデリカシーの欠如が、あらゆる暴力を生み出すのではないか。なぜなら死を虚無化とみなすとき、自己のなかに『他なるもの』が介入する余地がなくなってしまうからです」と述べます。
ヘーゲル的な円環性の外へ出る必要があるという著者は、「そのために、ぼくたちは何よりもまず、死を『何か』であるかのごとく当て込んではなりません。言い換えれば、死を存在論の範疇で考えてはならない。死はたんに存在と虚無が等価になる地点を意味しているのではありません。それほど都合のいいものではないのです。近代主義的な軽率さでもって、死は虚無化であるなどと、軽々しく口にしないようにしたいものです。本気でそんなことを思っている者は一人もいないはずです。だから形骸化したとはいえ、ぼくたちの社会は葬制を欠くことができないのです」と述べます。
そして、著者は「もちろん生物学的な意味で、、死は虚無化には違いありませんが、それをはみ出すものであるし、それ以上のものでもあることは、誰もが体験的に知っていることです。死は虚無化であると言って済むなら、人間は生物学的な1つの種であって、人間ではないことになるでしょう。人間が社会的な動物であると言われるのは、死を虚無化とみなしえないからです。サルによって人間を定義できないのと同じように、生物学的な死によって人間的な死を定義できるわけがありません。しかしヘーゲルやハイデガーがやっているのは、そういうことです。生物学的なことを哲学的にやっているだけで、本当の意味で人間学のレベルには達していません」と述べるのでした。
わたしが本書を読んだのは2021年のことで、2015年に『唯葬論』や『永遠葬』を書き上げた6年も後のことですが、両著作をはじめ、わたしの死生観と非常に近いことに親近感をおぼえました。2013年の時点で新型コロナウイルスによるパンデミックを予見していたことにも驚きましたが、何よりも日本人がこれほどの高いレベルの「死」の哲学書を書いていたという事実に深い感銘を受けました。本書に登場するプラトン、ヘーゲル、ハイデガーらはもちろん哲学の歴史に燦然と輝く大哲学者ですが、本書ほど日本人が「死」について深く考えるための最高の哲学書はないと思います。300万部を数えた大ベストセラーを書いた著書ですが、本書はまったくといって言いほど知られておらず、いわば「幻の名著」です。ぜひ、1人でも多くの日本人に読んでいただきたいと思います。
2022年5月21日 一条真也拝





