
一条真也です。
『パンデミックの文明論』ヤマザキマリ・中野信子著(文春新書)を読みました。新型コロナウイルスの感染拡大によるパンデミックについての対談本です。
ヤマザキ氏は、1967年、東京都生まれ。漫画家・文筆家。東京造形大学客員教授。フィレンツェの国立アカデミア美術学院で美術史・油絵を専攻。2010年、『テルマエ・ロマエ』(エンターブレイン)で第3回マンガ大賞受賞、第14回手塚治虫文化賞短編賞受賞。2015年度芸術選奨文部科学大臣賞受賞。
中野氏は、1975年、東京都生まれ。東日本国際大学特任教授。脳科学者。東京大学工学部応用化学科卒業。東京大学大学院医学系研究科脳神経医学専攻博士課程修了。2008年から2010年までフランス国立研究所ニューロスピンに博士研究員として勤務。
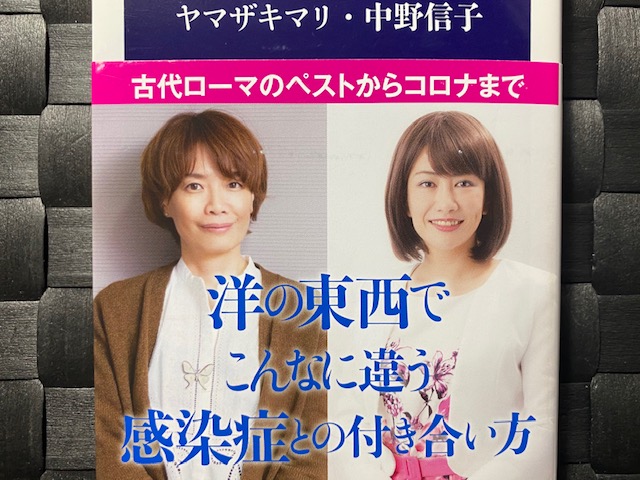
本書の帯
本書の帯にはヤマザキ氏、中野氏の上半身の写真とともに、「古代ローマのペストからコロナまで」「洋の東西でこんなに違う感染症との付き合い方」と書かれています。帯の裏には、以下の言葉が並んでいます。
「空気」を読む日本では
ウイルスも生きづらかった!?
イタリアで大流行したのは、ハンカチで洟をかむから
「自粛警察」は不倫カップルのことも許せない
欧米でマスクをしたら、病気に負けた証拠と思われる
日本の政治家は古代ローマの「お風呂外交」に学べ
パンデミック成金がルネッサンスを生んだ
ずっと前から日本はソーシャル・ディスタンス
オランダ人の50%はトイレの後に手を洗わない
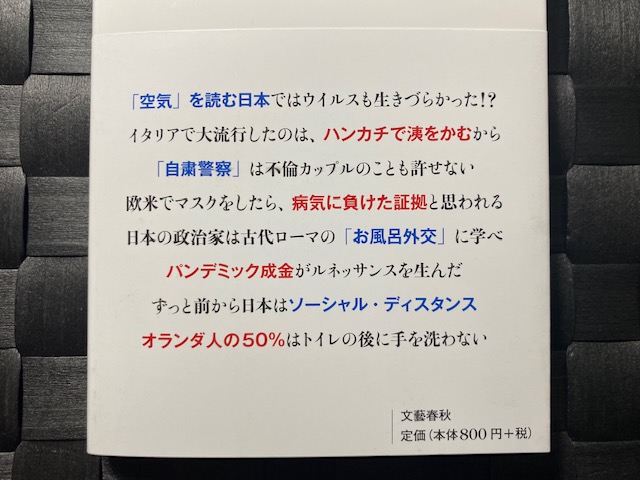
本書の帯の裏
カバー前そでには、こう書かれています。
「新型コロナの話で意気投合した、異色の二人が緊急対談。各国の感染症対策を見れば国民性がわかる。徹底して根絶を目指す欧米に対して、アジアはほどほどに共存しようとする。話題は古代ローマから現代まで時空を超えて、目からウロコの文明論が展開される」
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「対談のはじめに」
第1章 コロナでわかった世界各国「パンツの色」
第2章 パンデミックが変えた人類の歴史
第3章 古代ローマの女性と日本の女性
第4章 「新しい日常」への高いハードル
第5章 私たちのルネッサンス計画
「対談を終えて」
第1章「コロナでわかった世界各国『パンツの色』」では、ロックダウンについてのヤマザキ氏の以下の言葉が印象的です。
「ロックダウンなんてことをしたら、観光に大きく依存しているイタリアの経済は死んでしまいます。そういった弊害は考えていないのかと問えば、『経済は生き延びている人間がいればなんとかなる、歴史上でもそうだった。お金と人命、どっちが大事なの?』と返されました。『人命が大事って言うけれど、リーマンショックのとき日本では不景気で3万人以上も自殺したのよ』と反論しても、貧困が苦となって人が自殺することにリアリティが感じられないらしい。自殺を罪とするキリスト教の倫理観とともに生きている人たちと、日本みたいな国とで、対策が同じにならないのは当然なんですよ。イタリアだけではなく危機管理は国によってまったく違う。自分たち日本人の考える対策をスタンダードと捉えて、他国と比較する無意味さを痛感しました」
古代ローマ史に精通したヤマザキ氏はイタリア在住ですが、中野氏と以下のような対話を繰り広げます。
ヤマザキ イタリアでは、外出禁止令が解除された途端、「ああ、やっと解放された!」とマスクを外した人がニュースのインタビューに出ていました。マスクでパンデミックの意識を強制されるのが本当に嫌だったんでしょう。マスク姿は、感染予防というよりも、病気になったことを認めてしまうアイテムという意識が強いんだと思う。ちょっと鼻水や咳が出る程度なら、「病気なんて気持ちでねじ伏せてやる!」と気構えるのがあの人たちの傾向かもしれない。
中野 アメリカでは、そういったマッチョ思想の人は共和党員に多いと聞きました。トランプ大統領もいっときマスクをしないことを売りにしていましたし、オクラホマ州のトランプ陣営の選挙集会では、支持者のほとんどがマスクなし。相当の飛沫が飛び交ったことでしょう。彼らがマスクをしないのは、やっぱり病気に負けたと認めたくないというメンタリティの表れなんですね。
中野氏は著書『不倫』(文春新書)で、「社会が過剰な不倫バッシングに走りがちになるのはなぜなのか?」という問いの答えについて「フリーライダー」という概念を持ち出して持論を展開しましたが、本書でも、「ヒトは共同体を営む生物ですが、個人は共同体に一定の貢献をして犠牲を払い、その代わり共同体から利益を受け取ることで暮らしています。しかし、中には共同体に貢献をせず、利益だけを得て『ただ乗り』する者(フリーライダー)もいるわけです。フリーライダーとして標的になるわかりやすい例が、給食費を払わないのに給食を食べる人、でしょうか? また、脱税しているのに社会保障などはしっかり受けている人や、多くの人が守っているルールを逸脱して自分だけは楽しもうとする不倫カップルなどです。フリーライダーが増えてしまうと、ルールは死文化し、共同体は成り立たなくなってしまう。そこで人類の脳には、フリーライダーを見つけて、その人を罰することに快感を覚える仕組みが備えつけられているんです」と述べています。
フリーライダーだと認識した対象に「正義の制裁」を加えると、脳の快楽中枢が刺激され、快楽物質であるドーパミンが放出されるとして、中野氏は「この快楽は強烈です。有名人の不倫スキャンダルが報じられるたびにバッシングが横行するのも、人々の脳内でこのシステムが働いているからです。しかも『正義中毒』は共同体が危機に瀕すれば瀕するほど盛り上がりやすい」と述べます。それに対して、ヤマザキ氏は「他人の不倫にあれこれ批判をするなんて私的には余計なお世話だと思うけど、人類の脳の仕組みである以上、『正義中毒』は誰もが陥ってしまう可能性があるということですね」と語ります。
「各国指導者の演説力」では、両氏の対話が以下のように展開されています。
ヤマザキ 人と同じことをするのは想像力の欠落とみなされますから。学校の口頭試問でも人と同じことを言うと良い点はもらえません。個性や独立心を重視する。長いものに巻かれない人が評価される世界です。だから今回パンデミックが始まりかけた時、いちばん違いが顕著に出たのが各国首脳の演説です。ドイツのメルケル首相の演説がそれを示していました。
中野 彼女の演説はしびれましたね。かっこよかったですよね。
ヤマザキ まず、民主主義とはどういうものであるか、から入るわけですよ。「開かれた民主主義のもとでは、政治において下される決定の透明性を確保し、説明を尽くすことが必要です。私たちの取組について、できるだけ説得力のある形でその根拠を皆さんに説明し、発信し、理解してもらえるようにします」と。そしてカメラをじっと見つめて、「皆さん、頑張っていますか」「レジに座ってるあなた、いかがですか」と二人称で語りかける。あれは見事でした。
また、ヤマザキ氏は、「イタリアのコンテ首相は、自身が首相でもありますが弁護士であることを踏まえ、まずイタリアの法に則って、何があろうと国民の命が何よりも保障されるべきだと断言する。『ロックダウンにより皆さんを守るところから入ります』とズバリ言い切った。そしたらテレビの前の国民は皆、『そうだ、言われる通りだ』と納得するしかない。普段はあれだけ好き勝手に行動し、他者を容易には信用しないイタリア人も、あの演説で一気に団結しちゃった。ああいう演説パフォーマンスは、日本のリーダーにはできないですね」と述べています。
「ポピュリズム、そしてファシズム」では、ヤマザキ氏が「コロナ対策の違いはいろんなところに表れましたね。平時には隠れていた世界各国の『本性』が明らかになった気がする。下世話な表現を使うと、コロナが『お前はどんなパンツをはいているのか、脱いで見せてみろ』とそれぞれの国に迫ったような感があった」と語れば、中野氏は「ハハハ、確かに。各国の対応は驚くほど分かれて、普段はマッチョなことを言って格好つけてるけど、実は穴の空いたパンツをはいていたことが分かった、というような国や指導者もありました、どことは言いませんけど。民主主義って、やっぱり指導者を選ぶ側それぞれに、考える力がないと、あっという間にポピュリズムになるんですよね」と返しています。
さらに、ポピュリズム、それに続くファシズムをめぐって、2人は以下のような対話を展開します。
ヤマザキ ムッソリーニやヒトラーの持っている、あの演説力は大したものですよ。生きる気力を失っているところに、あんなに力強い思想と説得力のある言語を使える人が現れれば、皆目を輝かせて「この人についていこう」ってなるでしょう。
中野 ああいうのをいま振り返って考えると、もはやマジックとしか言いようがないほどの魔力なんですけれど、ちゃんとした道筋があるわけですね。
ヤマザキ 第1次世界大戦の最中にスペイン風邪がはやりだし、長い時間をかけて何千万人と言われる犠牲者を出してしまった。人々は疲弊していて、物事を自分たちの力で考えるエネルギーが残っていません。だから、リーダーになってくれる人が現れるのを待っていたわけです。それが政治家であっても宗教家であっても、卑弥呼みたいなシャーマンでもよかったんです。今、まだコロナは収束していないけど、カリスマ的なリーダー待望の空気が現れつつあるのかな。メルケルの演説を見ていて感じました。
中野 民主主義の健全性というものは、大きな物語に対して小さな物語をどれだけ確保できるかにあると思うんです。けれど、パンデミックのような大規模な危機があると、世の中は大きな物語のほうを優先しようという方向に動きます。パンデミックにつけ込むような形でポピュリズムが蔓延し、独裁者がもてはやされるようになるのは、民主主義の持つセキュリティホール――脆弱性のようなものなんでしょう。
日本が流動しない国であるということについては、以下の対話が展開されています。
中野 日本だけに限って見れば、実をいうと地域によって流動性が高いところ、低いところがあるんです。それに伴って気質も違ってくると考えられる。流動性の低さでいちばん顕著なのは北東北の内陸部です。その証拠といえるかどうか、岩手県ではいまだ1人の感染者も出していません(2020年7月14日現在)。
ヤマザキ あれは不思議ですよねえ。
中野 あの地域は、異質なものを受け入れず、異質な人も出さない、という傾向がやはり強くあるのかな、と感じさせられる現象ですね。それに比べて、北海道はかなり流動的な土地ですね。北東北と地理的にはそう遠くはないのですが、北海道は日本で最初期にクラスター感染が起きた場所でもありました。
「『浮気遺伝子』と感染率の関係」では、以下の対話が展開されています。
中野 日本のような流動性の低い社会においては、適応戦略は「集団の論理に従う」ことです。目立たず、自己主張せず、長いものに巻かれるのが、最もダメージを受けない、いわば「賢い」生き方になるんです。
ヤマザキ 存在していないように生きるわけですね。
中野 興味深いのは、今回の新型コロナはアメリカやブラジルなど、社会の流動性が高くて移民が多い地域で爆発的な感染拡大がみられたことです。一方、日本のような流動性の低い地域は、それほど大きな被害はなかった。この差はいったい何なのか。その謎を解くカギになるかもしれないのが、「新奇探索性」――新しもの好き――という観点かもしれません。これまでに、新奇探索性をつかさどる遺伝子が見つかっており、アメリカ人やブラジル人にその遺伝子を持つ人が多く、東アジアではそうではないことが分かっています。スペキュラティブ(推論的)な話ではありますが、どうもこの遺伝子の持ち主が多い地域は、爆発的な感染拡大地域と重なるように見えますね。なお、このタイプは性的にもアクティブで、一夜限りの性体験が多いという傾向がある。だから「浮気遺伝子」と呼ぶ研究者もいるぐらいです。
また、「普段からソーシャルディスタンス」では、中野氏が「もし本当に日本の感染率や死者数が低いとしたら、その理由のひとつはソーシャルディスタンスかもしれません。普段からベタベタくっつかないですからね。家族内でもハグしない、街中で抱き合ってキスするなんてもってのほか、現代ではもはや高齢者と同居もしない、それに握手の習慣もほぼないという」と言えば、ヤマザキ氏も「イタリア人のように飛沫を飛ばしあって喋る感じではないですからね。それにイタリアだと毎日とにかく誰かしらとは接触があるわけですよ。店に行ってもそこのおじさんと『やあ』なんて握手するし、馴染みのレストランに行けば、そこで働いている人たちと一通りハグするし、知り合いと通りで出会ってもやはりキスにハグだし、そしてその場でお喋りが始まるし」と言います。ブログ「コロナ禍の中で礼を考える」でも紹介したように、コロナ禍の中にあって、わたしは改めて「礼」というものを考え直しています。特に「ソーシャルディスタンス」と「礼」の関係に注目し、相手と接触せずにお辞儀などによって敬意を表すことのできる小笠原流礼法が「礼儀正しさ」におけるグローバル・スタンダードにならないかなどと考えています。ですので、日本の感染率や死者数が低い理由のひとつはソーシャルディスタンスという説は正しいと思っています。
「疫病には打ち勝つのか、交渉するのか」では、ヤマザキ氏は「私が思うに、古代の人は感染症を天災と同じように捉えていたのではないでしょうか。日本人にもそれは当てはまりませんかね。一言でいうなら『しょうがないな』と――。一方で、中世からヨーロッパでは感染症を敵だとみなすようになり、これは敵だ戦争だと形容していますけど、ああいう解釈は人間至上主義でなければ発生しないかなと。他の生き物は感染症を敵扱いなんかしませんよ」と述べています。また、以下の対話が展開されるのでした。
ヤマザキ ヨーロッパに「疫病に打ち勝つ」という概念が生まれたのは、14世紀の黒死病パンデミックのときですかね。あのときキリスト教がペストを逆手に取って、主導権を握ったわけです。キリスト教会は美術界にとってもとても大きなパトロンで、教会に掲げる絵画を媒体にして、「ペストは信仰を持たない者への天罰だ」と大キャンペーンを繰り広げたわけですよ。
中野 ペストを骸骨の姿に描いて、死神のイメージを強調したわけですね。
ヤマザキ そうやってキリスト教は死神と戦っているんだという意識を植え付け、民衆の信頼と信望を得ようとした。あれが大きかったように思います。
第2章「パンデミックが変えた人類の歴史」では、「ヨーロッパを変えた黒死病」として、以下の対話が展開されています。
中野 人類史の転換点では、パンデミックが大きなファクターとなってきました。ローマ帝国でも、ペストをはじめ大規模な疫病の流行が何度もあり、それが結果として歴史を動かす源にもなって来ました。疫病などの危機に直面すると、人々の経済的・社会的不安が一気に高まります。この時に最も攻撃の標的となりやすいのは、その共同体にとって「異質」な者――例えば、移民などのマイノリティたちです。現代のアメリカでも「Black Lives Matter」などの運動が起こってくるほど、黒人への差別が過激化しているわけですが、ローマ帝国では、疫病の流行とともに、こうした人たちへ「迫害」や「差別」は起こらなかったのでしょうか?
ヤマザキ 古代ローマ時代のパンデミックで感染者への迫害があったという記録は、私の知る限りありませんね。そもそも、差別による排除が彼らにとっては非合理的だったということもあります。ローマ帝国があそこまで領土を広げることができたのは、属州にした地域の民族の文化や習慣を、積極的に帝国内に取り込んでいったからだという話は先ほどもしました。「すべての道はローマに通ず」と言われるように、属州と都市を道路で結び、流通を活発化させ、人と物の行き来が盛んになっていった。今とは違った形ですが、グローバル社会を築き上げ、繁栄を享受しました。
また、ヤマザキ氏が「14世紀のヨーロッパを中心に猛威を振るった黒死病は、これまでの歴史で最もインパクトが大きいパンデミックだったと言えますね。2500万~5000万人が死んだと言われますが、欧州全体の3分の1~3分の2が亡くなったとされていることから、実際の全死者数は億単位だったとも言われています。死者の数もさることながら、パンデミックのあとに農奴たちの猛反乱が起きて、仕方なく領主たちは農奴を解放するようになり、なんとか人間扱いされるようになった。これは大きな変化でしたね。その影響は、封建社会の崩壊へとつながり、ある種の精神改革の領域にまで及んだのですから」と述べます。また、「けっこう高位にある王侯貴族も黒死病で亡くなっているんです。つまり、死は誰にでも襲いかかる不幸だ、みたいな捉え方が社会に拡がっていった。そこにキリスト教が入り込む余地があったわけです」とも述べています。
黒死病とキリスト教の関係については、以下の対話が展開されています。
中野 個々人の行いが悪かったからというよりも、お前たちがキリスト教を信じなかったからこうなったんだぞ、という考え方でしょうか。
ヤマザキ その通りです。それで教会は「死の舞踏」という一連の絵画を描いて啓蒙を始めました。
中野 骸骨やミイラとなった死者が生きている者たちと手をつないで踊っている絵ですね。行列を成して死へと導かれる絵だったりするのですが、なかなか迫力があり、かなりインパクトのある画面です。
ヤマザキ あれがまた、ユダヤ人の迫害につながるわけです。ユダヤ人がイエス・キリストを処刑したその仕返しが、今このような黒死病となって襲ってきたのだというユダヤ陰謀説まで飛び交って、ま、一種のスケープゴートなんですけれどね。
古代ローマでは、「アントニヌスのペスト」と言う疫病が流行しましたが、「疫病が帝国瓦解の遠因に」として、ヤマザキ氏は「メソポタミアから兵士たちが持ち帰った疫病によって、総死亡者数は1000万を超えたとも言われ、経済機能が止まってしまいます。生活インフラを担う商人たちが軒並み倒れたので、食料が尽きてしまった。さらに貿易を扱う人も船を漕ぐ人もいなくなってしまったので、物資が港に入ってこない。都市全体が飢餓に直面する中、兵士たちも次々と死んで軍隊が脆弱化する。そうした負の連鎖が続いた結果、ついに広大な帝国を監視・維持できるだけの国家の体力が奪われてしまったのです。ローマの国力が衰亡していったところへ、それまでは奴隷を中心に広まっていた一種のカルト宗教的な存在だったキリスト教の信仰が、一般の人にまで及ぶようになった。こうした疫病の広がりとそれによって引き起こされた社会の変化がローマ帝国瓦解の第1段階となった、と指摘する歴史家は少なくありません」と述べています。
また、「キリスト教を受け入れる心理作用」では、中野氏は「危機に際しては、善なるものであるかどうかを吟味する以前に、理性で判断するのを放棄するようになる、という傾向が強くなりますよね。理性の代わりに、勘だとか、情報の分かりやすさだとかに頼ってしまうようになる。というのも、正しいかどうかの検証には、時間と労力というコストがかかるからです。危機に際しては、それにコストをかける余裕がなくなるため、平時の余裕のある冷静な状態における判断とは異なる、極端に言えばあり得ない選択をしてしまったりすることも十分起こり得ます。実は『真・善・美』という3つの価値は、脳のほぼ同じところで処理されているんです。その領域は進化の過程ではかなり遅い時期にできてきたところなので、あまり効率的には働かない――例えば、酸素や栄養、睡眠の不足、アルコールの摂取などで、容易に働きが落ちてしまう。そういうときは、いつにもまして対象を冷静に吟味することなく、直感でわかりやすいリーダーを選んだり、難しいことを四の五の言わずに手っ取り早く道を示してくれそうな宗教家に頼ったり、ということが起こりやすくなるのではないでしょうか」と述べています。非常に興味深い指摘ですね。
中野氏は、「考えるのって、意外にエネルギーを食うんですよ。脳の重さは全体重の2~3%にすぎないのに、カロリー消費量は全体の5分の1~4分の1にもなる。すごい浪費家ですよね。なので、体の方から予算をカットしろと要求される時があるんです。危機が迫ると特に、逃げたり闘ったりしなくてはなりませんから、体の方にもリソースを分けないとならない。そんな状況下で脳は特に前頭葉の機能がオフにさせられやすいものですから、ゆっくりと時間をかけた理性的な判断をしにくくなります」とも述べています。気鋭の脳科学者の意見だけに、説得力がありますね。
「メディチ家の系譜はパンデミック成金」では、以下の対話が展開されます。
ヤマザキ 14世紀のペスト(黒死病)が終息したあと、ヨーロッパにルネッサンスが芽吹き始めます。ヨーロッパ人口の3分の1とか3分の2が死んだといわれる黒死病のあとに、なぜルネッサンスみたいなエネルギッシュな精神と文化の改革が生じ得たのか? 実はルネッサンスの種火というものは、すでに11世紀、12世紀ごろからあったわけです。個々に、散発的に、面白いことをやる人間が現われて、いってみればサブカルチャー的な現象としてあったんですね。そこへ襲ってきたのがペストです。これによって大災害と大凶作が重なり、ヨーロッパ中が混乱しました。農地が広がっても耕作する人間がいない。そんなときフィレンツェに勃興したのがメディチ家です。
中野 ローマ教皇も輩出したフィレンツェの名門貴族ですね。
ヤマザキ メディチはその名が示すように、もともとは医療関係――医師か薬種問屋をなりわいにしていた家柄だったと言います。銀行業で財を成してローマ教皇庁のパトロンとして名を馳せる2世紀ほど前は、村で丸薬を売っていたメディチ家ですが、それが銀行業に進出できたのは、ペストのお蔭でもある。
中野 言葉は悪いですが、いわばパンデミック成金だったんですね。
「ヨーロッパにパンデミックが起きると、そのたびにキリスト教が拡大していることが分かりますね」という中野氏に対して、ヤマザキ氏は「疫病が流行れば、キリスト教会は『さあ俺たちの出番だ』とばかりに、『これらの疫病や凶作は不信心な者どものせいだ』というプロパガンダをくりひろげたので、すごい勢いで信者が増えています。地獄では死者が炎で焼かれる、というイメージを持っていた人々の目に、疫病で死んだ人たちが焼かれている有様は地獄絵図として映っていた。本来は土葬なのに、感染死した者は火葬に付されていましたからね」と答えます。それに対して、中野氏は「視覚イメージが強烈に植え付けられたわけですね」と言うのでした。
「イデアのギリシャとリアルのローマ」では、ギリシャ文化とローマ文化を対比しつつ、ヤマザキ氏が「ローマの建築技術にしても、もともとはギリシャ人がつくり上げた概念を合理的につくり直したものです。たとえば劇場。ギリシャの場合は、市民が倫理観や道徳観を養うために喜劇や悲劇を見る場として設けられたもの。心を洗って、おのれのあり方を考える機会を提供したわけです。それがローマになると、観衆の前に自分を晒し、承認欲求を満たす場となっていった。ギリシャで遺跡を巡っていると、厳かな神殿の敷地の外側に商業施設の遺構のようなものが残っているんですが、それは全部古代ローマの支配下に置かれてからできたものなんです。お土産の他に、他人様に見せるためのアクセサリーとか素敵なトーガ(1枚布の上着)とか売ってたのかもしれない」と述べます。また、「集団としての成熟」として、ヤマザキ氏は「ギリシャの市民は、劇場で父殺しとか近親相姦とかスキャンダラスな題材の悲劇・喜劇を観て、そこに思い入れを持ったり反感を覚えたりしながら自分たちの生き方・思想を育てていくんですね。それが時代をへて、ローマでは大観衆の盛り上がりの中で剣闘士が殺し合ったり、時にはライオンと闘ったりするのを目にして、なんて野蛮なことを、と思う人が出てくる。これも人類としての成長であって、そこに至るにはそれだけの時間が必要だったのかなと思うんです」とも述べます。
「『排除』の心理的メカニズム」では、以下の対話が展開されます。
中野 ローマでは、属州出身の人は嫌な目にあったりしましたか?
ヤマザキ それがそうでもないんです。初めのうちはそういう排除の動きもあったと思うけれど、でも、ローマは急速にグローバリズムが進んで、次々に属州が増えていく。属州が増えると経済的には裕福になり、奴隷もたくさん入ってくる。異質な人が増えることのデメリットよりは、先ほどの話にあったように、異文化をうまい具合に商業化することも含め、メリットのほうが大きいと捉えている。その果てに、属州出身の皇帝まで出てきますしね。
中野 それがトラヤヌス帝(在位98~117年)ですね。
ヤマザキ 1世紀が終わるころ、トラヤヌス帝が誕生します。彼の治世においてローマの版図が最大になるんですが、私はバラク・オバマが米国大統領になった時、ちょうどシカゴに暮らしていて、アメリカ人の熱狂を見ながら、トラヤヌスが皇帝になった時もこんな感じだったのでは、と思ったんです。
属州はただ拡大させるだけではなく、そこで生まれる利点をしっかりと活用の方向へ持っていくとして、ヤマザキ氏は「版図を拡大したローマ帝国では、属州の出身者や奴隷たちの手を借りないと市民社会が成り立たないことを、本土の人は早くから認識していたわけです」と述べるのですが、それに対して、中野氏が「ああ、やっぱり古代ローマの人々は現実主義的ですね」と言うと、ヤマザキ氏は「ですから、ローマは多種多様な民族や文化を抱えてしまったので、『これこそがスタンダード』という物差しがなくなった。いってみれば混沌の世界――。そのへんが、どこを見ても金太郎飴のような今の日本の社会状況とは違いますよね」と述べます。さらに、「ローマは版図を広げた結果、疫病にかかるリスクも広がったのではないですか?」という中野氏の問いに対して、ヤマザキ氏は「まったくその通りですね。すべての道に通ずるローマの道は疫病も運んできてしまうわけです」とし、最後に「すべての感染症はローマに通ず」と述べるます。
第4章「『新しい日常(ニューノーマル)への高いハードル』では、「日本の若者の『圧』」として、以下の対話が展開されています。
中野 日本の高齢者がいちばん嫌う死に方は、若い人たちと同居している家で孤独死することなんですって。
ヤマザキ 同居してるのに孤独死?
中野 ひとつ屋根の下でも別々の部屋にいるから。
ヤマザキ 「ご飯ですよ」とか「お風呂ですよ」とか声かけはしないのですか?
中野 二世帯住宅だと、食事やお風呂も別なんです。東京にはものすごい人口がいて、とっても密な生活をしているようでも、それぞれ異なるレイヤーで生きているんです。
ヤマザキ だからコロナの感染が拡がらなかったんじゃないですか。子どもが帰宅しても「ただいま」も言わずに部屋に入っちゃうとか、夫婦が別々の部屋で寝ているとか、家庭内ですでにソーシャル・ディスタンスになってるんだもの。イタリアだったらあり得ないですものね。どんなにケンカをしていようと険悪だろうと、食事は家族一緒にするものと、儀式のように決まっていますから。
また、「集団の中で生き延びるためには」として、以下の対話が展開されます。
中野 確かに感染症対策の観点からすれば、排除されているほうがずっと安全ですよね。日本の人々が無意識に行ってきた工夫としては、明文化されない厳しい掟のある集団を形成しはするけれど、やはり、“密”の中で暮らしているのにアクリル板で隔てられているかのように、見えないアクリル板を私たちのマインドセット(思考様式)の中に作った、というところじゃないでしょうか。それはすごいなと思う。
ヤマザキ 満員電車の中でみんなつらい状況にいるのに、誰ひとりストレスを表に出すことなく、目的地まで黙って揺れに身を委ねている様子を、常々すごいなあと感じます。
中野 そう、私もそれを強く感じます。日本って、コロナ以前から通勤電車の中でしゃべってる人がいないですよね、ヨーロッパは電車内での会話の声がすごい。
中野氏は、「もし生活習慣の違いで感染率に差が出るとわかれば、その生活習慣をすべての国でニューノーマルにすればいいわけです。それがとてもシンプルな解決策だと思いますね。アジア人は罹りにくいとわかっただけでは、それが感染防止策に採り入れられるわけでもないですから」と語りますが、その後、「もしも鎖国をしなかったら?」として、以下の対話が展開されます。
ヤマザキ 人類はもともと狩猟で生活の糧を得てきた、移動性の生物です。ところが多くの祖先は農耕の始まりとともに定住生活に落ち着いた。だから農耕民族と遊牧民族とでは、メンタリティがまったく違いますね。日本ではあまり遊牧民族系のメンタルは根付かなかった。
中野 日本の地形が移動を阻むんでしょうね。山あり海ありで。それに、東日本と西日本との通婚率が最近までかなり低くて、他の地域との婚姻が少ない。だから方言がわりと残っているといわれますね。
移動しない日本人について、対話は続きます。
ヤマザキ この、移動をしないという民俗的傾向が、パンデミックの拡がり具合にかなり関係があるようにも思います。古代ローマ人は、北はスコットランド、東はユーフラテス川まで領地を広げましたが、その分ペストなどの疫病もローマの道を通じてどんどん入ってきてしまった。その後の大航海時代は、コルテスやピサロがヨーロッパの疫病をアステカ王国とかインカ帝国に持ち込んで先住民をほぼ全滅させてしまったし、スペイン風邪は第1次世界大戦の軍隊の遠征によって拡大していった。結局、流動性が高ければパンデミックを招き、低いと疫病は蔓延しない。そう考えると、日本から外へ病原菌が運び出される機会は他より少ない。
中野 本人の意思にかかわらず移動させないというのは、意外と重要なことだったのかもしれません。その意味では、日本が鎖国をせずにキリスト教も入り放題、海外からの移住大歓迎となっていたら、けっこうなパンデミックが発生していたと思います。戦国時代から江戸期にかけて海外から梅毒が持ち込まれて、大流行したわけですから。
第5章「私たちのルネッサンス計画」では、「コロナウイルスが考えていること」として、ヤマザキ氏は「そもそも私には、ウイルス対策を勝ち負けで捉えることに違和感があります。根絶を目指すのではなく、コロナと共存していくという東洋的なあり方のほうが、むしろ合理的なのではないかと感じています。実はウイルスの立場から見ても、共存のほうが本望だったのかも知れませんよ。ネズミにしてもレミングにしても、ものすごい数まで増えると自然に病気に罹って数が減少する――そういう摂理が生き物の世界にはある。だから人間にも同じことが起きないはずはないんであって、人間は素晴らしい万物の霊長だから、他の動物に優越して生きる価値がある、資格がある、だから今回のコロナは不条理なものである――という西洋式の人類至上主義的考えはどうも納得がいかない」と述べています。
14世紀のペストで何千万という単位の人が死んだ後、ルネッサンスがなぜあそこまで盛り上がったのでしょうか。ヤマザキ氏は、「疫病というものは、人間を混乱させもしますが、考える時間というものを与えてくれる、ある意味で貴重な機会です。何せ未曽有の天変地異を経験させられるわけですから、人間とはなにか、ウイルスとはなにか、社会とは、生きるとはと、様々な思いが頭をめぐる。今はテレビだネットだと、誰かの意見に自分の考えを便乗させるという思考の怠惰が顕著ですが、むかしはとにかく自分の想像力をたくましくするしかないわけですよ。想像力の訓練なしにはルネッサンスなんていう精神改革は発生しません」と述べています。
100年前のスペイン風邪の後、ナチズムやファシズムが待ち構えていました。そうならないためには、どうすればいいのでしょうか。この問題をめぐって、以下の対話が展開されます。
中野 「合成の誤謬」という行動経済学でよく言及される概念があるでしょう。みんなが少しずつ自分のためにいいと思ってふるまっても、それらが合わさると全体としては間違った方向に行ってしまうというものです。その誤謬に気づいて、1人だけで正そうとすると、正そうとした人が最も損をする。なので、一気にみんなで正さなくてはいけないし、一斉にやり方を変えないと、絶対に誤謬は修正されないんですね。でも、こういうパンデミックの後というのは、「いっせーのー、せ」で変える機会になり得るんです。
ヤマザキ 私は、今回のパンデミックにはスペイン風邪の後とは違う流れになる可能性を感じています。今の時代は、エンターテインメントというものが経済的な生産性を持つようになっているから、経済を元に戻そうとする勢いがエンタメと繋がれば、新たな世界を作り上げることもできるんじゃないかと。それこそ14世紀のルネッサンスが一気に力を帯びたのに似た兆候です。つまり、昔だったらナチズムやファシズムの勢いに囚われた、不安や怒りや鬱憤を抱えた人たちが、奇抜で凶暴な思想に夢中になる代わりに、もっと楽しい方向性を選ぶのかなって。それがエンタメなのか、あるいはグルメなのか、そこはまだ分かっていないんですけど。
この合成の誤謬に関連していうと、中野氏は「私、一斉に変えられたものとしては『テレワーク』が典型的な例かなと思うんです。一人だけ『テレワークします』と言い出しても、怠け者のレッテルを貼られてしまうけど、コロナの自粛でみんな一斉にやってみたところ、意外と効率的だったり、メリットがたくさんあると分かったわけです」と述べています。たしかに、そうですね。わたしも同感です。
「土葬が火葬に変わる?」では、新型コロナウイルス感染による死者の遺体について、以下のような対話が展開されています。
中野 死亡者が大量に発生したニューヨークでは、埋葬待ちの棺が山積みでしたが、お葬式のあり方も変わりますかね。ヨーロッパは土葬でしょ?
ヤマザキ いや、今はイタリアでも、火葬が推奨される傾向になってきています。土葬をする土地がもう足りなくなってきているんですよ。イタリアの場合、20年ほど前までは、「火葬にしてほしい」という遺言を残しておかないと許可してもらえなかったんです。今から30年ほど前ですが、知り合いの日本人の男性がフィレンツェでがんで亡くなった時は、遺言を書いていなかったために、火葬の許可をなかなか出してもらえず、大変でした。
中野 土葬するにもスペースが足りないのですね。
ヤマザキ そうなんです。壁の棚に棺を収めるという、集合式のシステムもありますが、それすらスペースがなくなってきた。埋葬前の棺を安置する場所っていうのが墓地などにもあるわけですけど、積み重ねられた棺の中でガスが発生して破裂してしまう。40年ほど前のものですが、その埋葬問題を揶揄している映画作品すらあります。
中野 それはそれで大変なんだ。
さらに、火葬について対話は続きます。
ヤマザキ それが、今回のコロナで火葬をためらっている場合ではなくなりました。
中野 それがヨーロッパのニューノーマルになるかも知れないですね。何十年か前までは、「あの人は火葬したらしい」というだけで変人扱いされたものですが。
ヤマザキ キリスト教は復活が中心概念の宗教ですから、肉体への思い入れが強いわけですよね。焼かれるなんて、ましてや。
中野 しかも煉獄をイメージさせる。
ヤマザキ 早い話が火あぶりですものね。ちなみにイタリアの火葬は、日本と違って完全に灰にしちゃうんです。
中野 骨も残らないんですか。ヤマザキ 完全にパラパラサラサラの灰みたいな感じでしたね。だから、お骨を拾うなんていうこともしないし、できない。
中野 そのニューノーマルは死生観にも影響を与えそうですね。
「対談を終えて」では、ヤマザキ氏が「新型コロナウイルスの感染拡大が始まってからというもの、それまで視野を遮っていた靄がはらわれて、あまり輪郭のはっきりしていなかった、いろんなことが開けて見えてきた気がするんです。普段見えないものが突然視界に入ってきたような感覚ですかね。実際、しばらく中国の経済活動が停止していたおかげで、だいぶ空気がきれいになって、エベレストなんかも何百キロも離れたところから見えるらしいですけど」と述べれば、中野氏は「マリさんがおっしゃってるのは、コロナのお蔭で立ち止まって考えたことで、今までと違ったいろんな風景が見えてきたという意味でしょう。私もそうなんですよ。改めて考えてみると、こんなに世界の全体の動きを身近に意識したことって、初めての経験だったんじゃないかな」と述べます。
そして最後に、ヤマザキ氏が「歴史を振り返ってみても、感染症は人類にそのような思索の機会を導き入れる、時空の節目なのかもしれません。できれば感染による死は避けたいし、感染症で亡くなった方とそのご家族には本当にお気の毒なんですけど、自分の人生でこのようなパンデミックを経験し、普段であれば気がつかない人類という生き物の動向を、綿密に分析することができたというのは、とても貴重なことだと感じています」と述べるのでした。本書は、ヤマザキ氏と中野氏の話のテンポが見事に噛み合って、非常にわかりやすいパンデミック文明論となっています。なにより、2人ともユーモアに溢れており、面白い本でした。パンデミックというのは深刻なテーマですが、楽しみながら読みました。
2020年10月14日 一条真也拝
 松柏園ホテルのレストランで
松柏園ホテルのレストランで





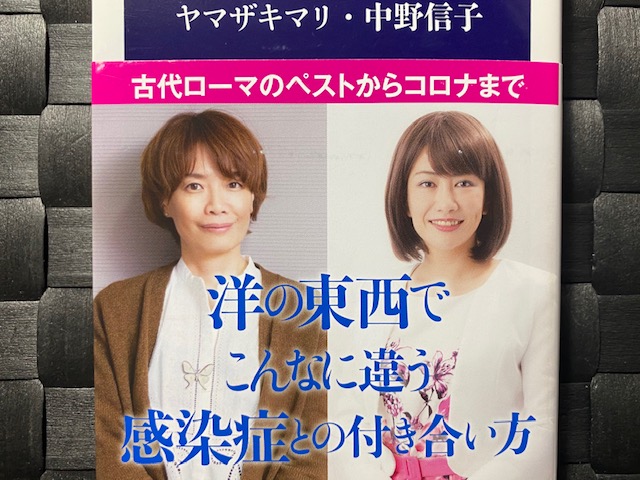
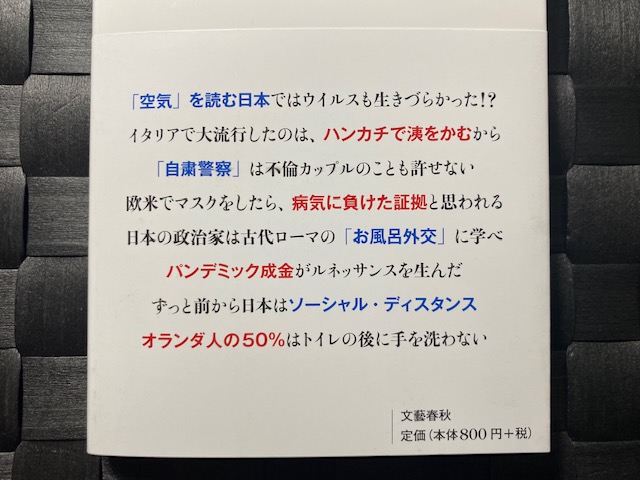



















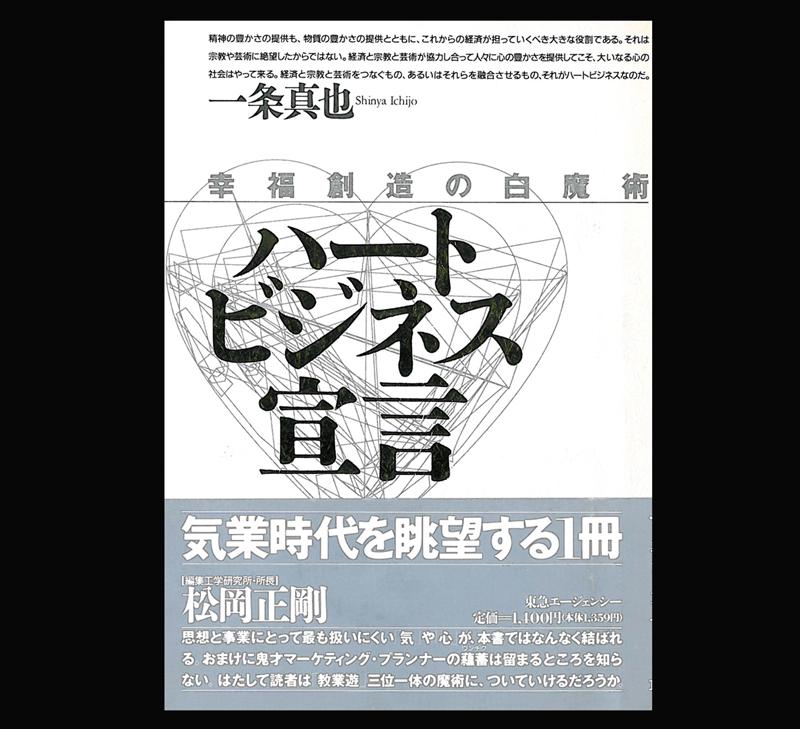
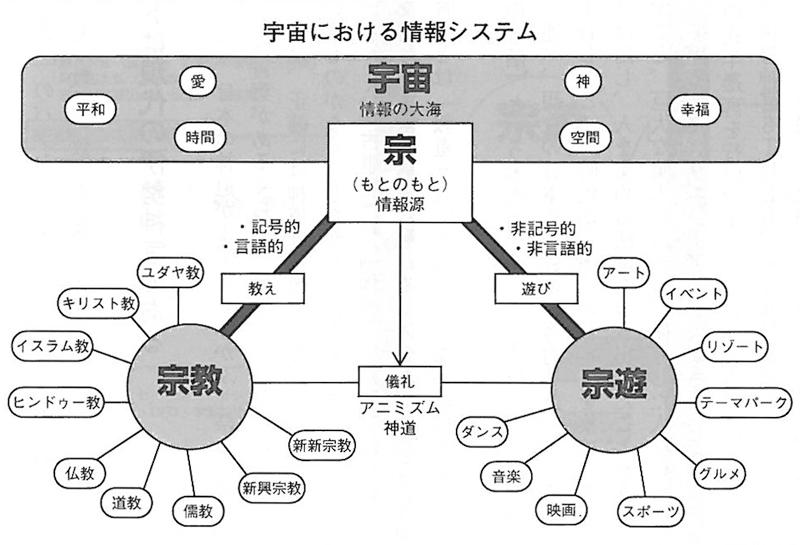
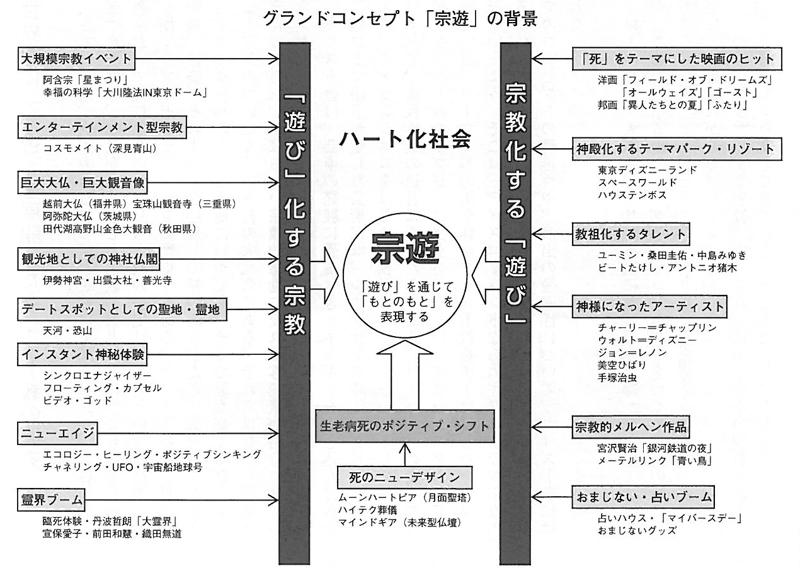



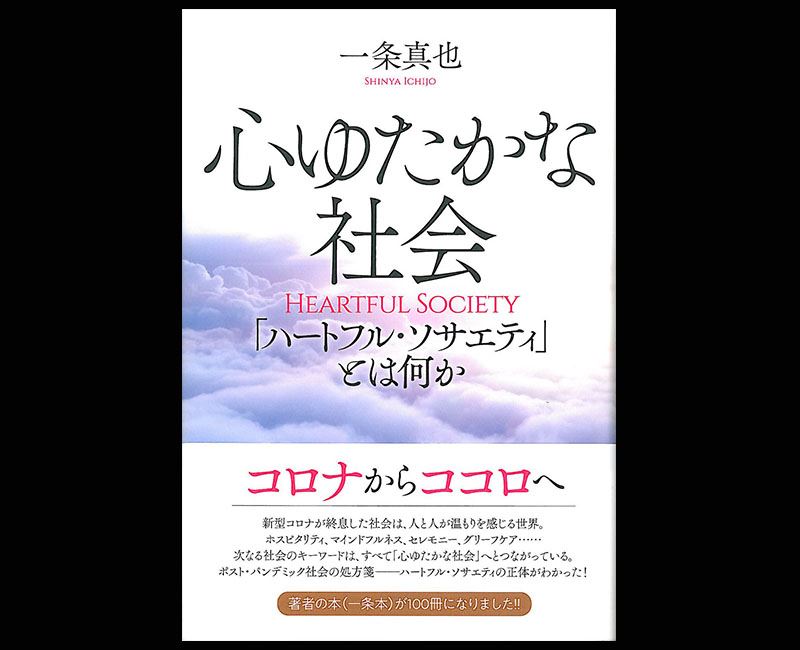 『
『